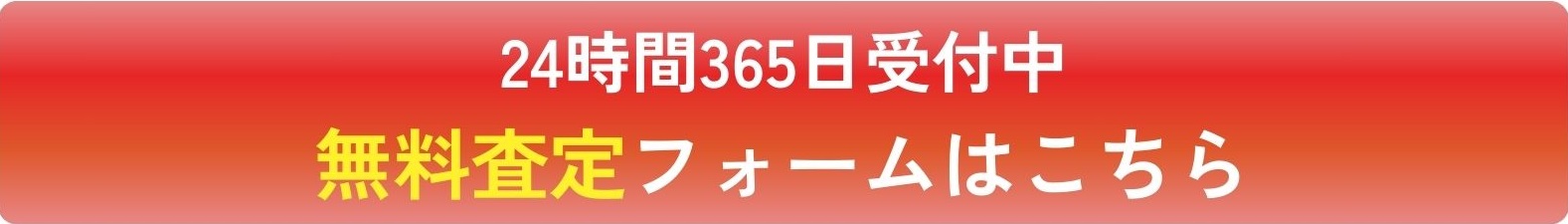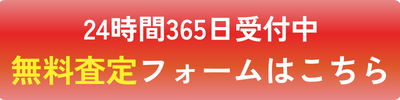適切な維持管理がなされていない空き家の数は年々増加しており、これらの空き家は物件の所有者だけでなく、近隣住民にも影響を及ぼす大きな問題となるケースが増加しています。空き家はさまざまな法的リスクを抱えており、それを放置することは決して賢明な選択ではありません。このブログでは、空き家が抱える様々な法的リスク、過去の判例、そしてそれぞれのケースに応じた対処法について詳しく解説します。
はじめに、空き家が引き起こす問題
空き家が引き起こす問題には空き家の管理不足に伴う問題や、空き家そのものが犯罪行為の温床となりかねない場合などさまざまなリスクがあります。
景観・衛生環境の悪化
空き家による景観と衛生環境の悪化リスク 空き家が引き起こす問題の中で、特に近隣住民からの苦情が多いのは、景観と衛生環境の悪化です。長期間手入れされない雑草は敷地を覆い尽くし、隣接する家屋にも悪影響を及ぼす可能性があります。また、放置されたゴミが不法投棄の場と化し、さらに多くのゴミが不法に投棄されることで、空き家はゴミ屋敷へと変わり果てる恐れがあります。
不審者の侵入や犯罪の温床となる
不審者による安全性の問題 管理不足で人目につかない空き家は、不審者が侵入しやすく、彼らの潜伏場所になり得るリスクがあります。
放火の危険
犯罪発生の懸念 放置された空き家は、不審者による容易な侵入を許し、放火などの犯罪の発生源となる可能性があります。長期間放置された空き家は、これらの犯罪行為を助長する場となり得ます。
倒壊の危険
倒壊の危険性とその法的責任 適切な維持管理がなされていない空き家は、老朽化が進み、地震や台風、積雪による倒壊のリスクが増大します。空き家が倒壊し、その結果近隣住民や通行人に損害を与えた場合、所有者は土地工作物設置責任に基づき損害賠償を負う可能性があります。
土地工作物設置責任について 民法第717条によれば、土地の工作物の設置または維持の不備が他人に損害をもたらした場合、その工作物の占有者は、被害者に対して損害賠償の責任を負います。しかし、占有者が損害発生を防ぐために必要な注意を払っていた場合、その責任は所有者に移ります。
空き家対策特別措置法
空き家問題は深刻な社会的課題となっており、これに対応するための具体的な法律が必要とされてきました。この要請に応える形で、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空き家対策特別措置法」と称する)が2014年11月19日に国会で可決され、2015年5月26日から施行されています。この法律は、適切な管理がなされていない空き家が地域住民の安全、衛生、景観に及ぼす悪影響に対処することを目的としています。
空き家対策特別措置法の主旨 この法律は、放置された空き家が地域住民の生活環境に及ぼす負の影響に対処し、住民の生命、身体、財産の保護及び生活環境の保全を目指しています。さらに、空き家の有効活用を促進することにも焦点を当てています。
用語の定義
用語の定義 空き家対策特別措置法は、法の目的達成に向けた具体的な措置を定める上で、「空家等」「特定空家等」「所有者等」といった重要な用語を定義しています。
- 「空家等」は、居住やその他の使用が行われていない建築物やその敷地を指し、国や地方公共団体が所有、管理するものは含まれません。
- 「特定空家等」は、放置することによって倒壊の危険や衛生上の害、景観の損失など、周囲の生活環境に著しく悪影響を及ぼす状態にある空き家を指します。
- 「所有者等」には、空き家の所有者や管理者が含まれ、これらの者には特定の義務が課されます。
行政の権限や手続き
空き家問題に効果的に取り組むためには、行政が空き家の存在や所有者情報を素早く把握するシステムの重要性が高まっています。空き家対策特別措置法は、このような情報収集と具体的な対策を行うための行政の権限を明確に規定しています。
- 立入調査の実施(第9条)
- 市町村長は、地域内の空き家の所在地と所有者情報を把握するために必要な調査を行う権限を持っています。これには、空き家対策特別措置法の施行に必要な限り、空き家に立ち入っての調査も含まれます。立入調査の際の拒否や妨害は、20万円以下の過料に処されます。
- 空き家情報の利用と共有(第10条)
- 市町村長は、固定資産税の課税等の目的で保有する情報を、空き家対策特別措置法の施行のために必要な限り利用することができます。また、空き家の所有者情報を把握するために必要があれば、関係する地方公共団体や他の関係者から情報提供を求めることが可能です。
行政の、特定空家等に対する段階的な措置は下記の手順を踏むこととなっています。
- 助言または指導
- 市町村長は、特定空家等の状況を改善するため、所有者等に対して除却、修繕、立木の伐採等、必要な措置を取るよう助言または指導を行います。
- 勧告
- 助言や指導にもかかわらず状況が改善されない場合、市町村長は、猶予期限を設けた上で、必要な措置を取ることを勧告します。
- 命令
- 勧告に正当な理由なく従わない場合、市町村長は、必要な措置を取るよう命令を下します。命令に違反した場合、50万円以下の過料が課されます。
- 代執行
- 命令に従わない場合、市町村長は代執行により必要な措置を行い、その費用は後に所有者等から徴収します。
空き家問題のケーススタディ
空き家問題に関する具体的なケーススタディを3つ紹介します。予期せぬ理由で空き家となる事例が多く、これらの事例は解決が非常に困難です。
成年後見人が必要な場合
空き家となってしまうケースには、しばしば入居者の認知症によって実家の処分がままならなくなったことをきっかけにして発生するケースなどがあります。
ケーススタディの概要
ある家庭では、認知症を患う母親が約10年前から介護施設に入所しており、母親名義の実家が空き家となっています。仕事の忙しさから、この空き家の維持管理が疎かになっており、近隣への影響も懸念される状況です。家族は実家を売却し、この問題を解決したいと考えていますが、母親名義のため直接的な売却ができません。
成年後見人による解決策
この状況では、母親が自ら契約を結ぶ能力が認められないため、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、成年後見人の選任を求める必要があります。成年後見人が選任されれば、その人が法的な代理人として、母親の財産管理を含む一連の決定を行うことになります。実家の売却が母親の最善の利益に適うと判断されれば、成年後見人は家庭裁判所の許可を得て、実家を売却することができます。
弁護士への依頼の利点
成年後見制度に関する手続きは複雑であり、適切な知識と書類準備が必要です。このプロセスを弁護士に依頼することで、専門的なサポートを受けられるため、申立て手続きの負担が大幅に軽減されます。弁護士は申立てから裁判所での手続きまでを代行し、家族に代わって最適な解決策を導き出します。
参考:成年後見制度とは、認知症の親を持つ子どもが直面する法的問題を解決するための制度であり、適切な手続きを踏むことで、空き家問題の解決にもつながります。この制度を利用することで、親の財産を守りつつ、子どもが合法的に空き家の売却などの決定を行うことが可能になります。
共有物分割請求を行う場合
相続が発生した際に、実家などが相続人である兄弟などによって共有物となってしまい、それをきっかけとして売却など処分が立ち行かなり空き家となってしまうケースなどがあります。
ケーススタディの概要
父の遺産として相続した実家は、私と兄、妹の3人で共有する形になりましたが、実家は現在空き家状態です。私の転勤により実家の管理が今後難しくなるため、実家の売却と売却代金の分配を提案しましたが、兄の反対により合意に至っていません。
共有物分割請求による解決を探る
共有物分割請求とは 共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要ですが、一致しない場合、共有状態を解消する方法として共有物分割請求があります。共有物分割請求により、不動産の分割または売却を求めることができ、不動産の売却が可能となります。これは民法に基づく権利であり、協議による解決が困難な場合には裁判所への請求が可能です。
法的枠組み
- 共有物の変更禁止(民法251条): 共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要です。
- 共有物分割請求の権利(民法256条1項): 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。
- 裁判による共有物分割(民法258条1項): 協議による分割が不可能な場合、裁判所に分割を請求することができます。
弁護士のサポート
共有物分割請求は複雑な法的手続きを伴うため、専門家である弁護士の支援を受けるメリットが大きいです。不動産取引に精通した弁護士は、関連する専門家との連携、専門知識を活用した交渉、必要に応じて調停や裁判手続きの進行など、効果的な解決策を提供します。
参考:共有不動産の分割請求は、共有者間の合意が得られない場合の有効な解決策です。法的手続きを通じて共有状態の解消を目指すことで、空き家問題の解決につながります
空き家を不審者が不法に占拠している場合のケーススタディ
驚くことに、空き家を見知らぬ不審者が勝手に住み着いて不法占拠してしまうケースは多々あります。不法占拠者に対して立ち退きを要求するには
ケーススタディの概要
結婚を機に都心へ移住し、実家が空き家となった依頼者は、ある日実家を訪れると、不審者が実家を占拠しているのを発見しました。不審者に退出を求めましたが、応じてもらえず、不法占拠の状態にあります。この状況で不審者を如何にして実家から追い出すかが問題です。
法的手続きによる解決策
不法占拠者を実家から追い出すには、自力での追い出しは違法な自力執行となり得るため、法的手続きのもとで行う必要があります。不法占拠に対処するには、まず裁判所に建物明渡し請求訴訟を提起し、法的な判断を求めることが適切です。
弁護士への依頼の重要性
このプロセスでは、訴訟提起の前に、不審者による実家の占有状態が他者へ移転されないよう、裁判所に対し占有移転禁止の仮処分を申し立てることが重要です。弁護士に依頼することで、仮処分命令の申し立てから建物明渡し請求訴訟まで、法的な対応を総合的に進めることが可能になります。専門知識を活用し、スムーズかつ効果的に不法占拠者を実家から追い出すための適切な手続きを実行します。
参考: 不法占拠された空き家に対処する際は、法律の枠組み内で適切な手続きを踏むことが不可欠です。裁判所の介入を通じて法的な解決を図ることで、所有者の権利を守りつつ、問題を解決することが目指されます。この過程で弁護士の専門的支援を受けることにより、問題の迅速かつ正確な解決に繋がります。
空き家対策としては空き家の状況をそもそも作らせないことが重要
空き家問題に関連する法的な課題に対処する過程で、法的専門家への依頼が必要となることが多く、これには高額な報酬が伴います。さらに、問題解決までには長期間がかかり、依頼人にとっては精神的なストレスも大きな負担となります。このような困難に直面しないためにも、空き家の問題を未然に防ぐための事前の対策が極めて重要です。
最も重要な家族間でのコミュニケーション
事前対策として最も効果的なのは、家族間での早期からのコミュニケーションです。相続が発生する可能性がある場合、事前に家族内で実家の今後について話し合い、具体的な計画を立てておくことが重要です。この過程で、遺言の作成が非常に有効な手段となります。遺言により、財産の分配や処分に関する意志を明確にし、将来発生しうる共有状態の問題を回避できます。
特に、認知症などで本人の判断能力が低下する前に、遺言を残しておくことは、後のトラブルを防ぐためにも必須の対策です。遺言によって、相続人間の意見の対立を避け、スムーズな財産の移転を実現することが可能になります。
相続が発生した後の対応としても、相続人間での円滑な話し合いが求められます。空き家の利用方法について、売却するか、誰かが住むかなど、可能な限り早期に決定することが望ましいです。この段階での迅速な決断は、不動産の価値を維持し、有利な条件での売却や再利用を可能にします。不動産の価値は時間が経つにつれて低下する傾向があるため、老朽化の進行を抑え、最適なタイミングでの処置を図ることが重要です。
以上のように、空き家問題に対しては、予防的な視点から早期の計画立案と実行が不可欠です。家族間でのオープンなコミュニケーション、遺言の作成、及び相続発生後の迅速な対応が、問題を未然に防ぐ鍵となります。これにより、法的な複雑化や精神的な負担を最小限に抑え、財産の有効活用を実現することができます。
専門家に相談することも重要
空き家の問題は多面的で複雑なため、家族間での話し合いだけでは解決が難しい場合があります。このような状況では、外部の専門家の知識と経験を活用することが極めて重要になります。具体的には、法律面でのアドバイスを提供できる弁護士や、相続税や遺言作成に関する専門知識を持つ税理士などが挙げられます。これらの専門家に事前に相談することで、相続が発生する前に、家族が直面する可能性のある法的・財政的な問題について的確な指南を受けることができます。
さらに、不動産の売却や有効活用の方法については、市場の動向や法規制を熟知した不動産専門家の意見が不可欠です。不動産業者は、空き家の現状評価や最適な売却時期、利活用の提案など、具体的な実行計画を立案する上で有力なパートナーとなります。
弊社には、相続や税務問題に精通した専門家が在籍しています。空き家の売買だけでなく、その管理や再活用、さらには包括的なコンサルティングサービスを提供しております。空き家問題に直面している方、または将来的に親の遺産を引き継ぐ予定があり、実家の取り扱いについて悩んでいる方は、私たちの豊富な経験と専門知識を活用してください。
私たちは、相続がスムーズに行われるようサポートし、空き家問題の未然防止や解決策の提案を行います。最適な遺言の作成支援から財産の効率的な分割、空き家の有効活用まで、ご家族にとって最良の選択肢を一緒に模索します。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)