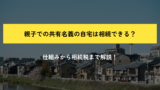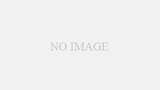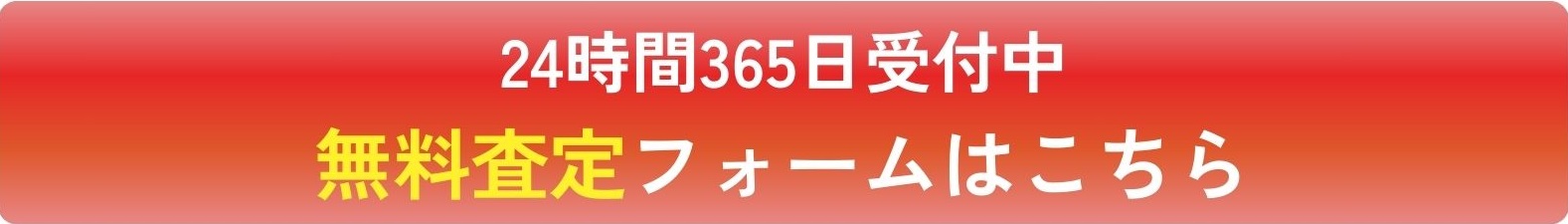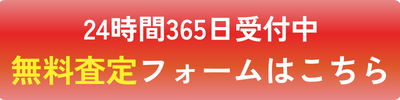親の相続に伴い自宅などを取得するケースは稀ではありませんが、相続後の売却については方法やメリットなどがよくわからず躊躇される方も多いかと思います。相続税の納付や、名義変更のための登録免許税、譲渡所得税、そして印紙税など、様々な税金の概要を解説します。また、相続後の早期売却が推奨される状況やそのメリットを分かりやすく解説しています。相続に伴う税金の基本から、売却を検討すべき理由、節税のための具体的なステップまで、相続土地の売却に関わる重要な情報を網羅しています。
相続に伴い発生する税金
相続税
相続税とは、故人から財産(金銭、土地など)を引き継いだ際に課される税金です。この税金は、受け取った財産の価値に基づいて計算されます。
相続税の計算には、次の式が用いられます。
相続税=課税遺産額×税率相続税
ここで、課税遺産額は以下の式により求められます。
課税遺産額=遺産総額−基礎控除額
基礎控除額とは、3,000万円に相続人一人あたり600万円を加えた額です。例えば、遺産総額が8,000万円で、相続人が3人いる場合、課税遺産額は以下のように計算されます。
課税遺産額=8,000万円−(3,000万円+600万円×3)=3,200万円
この場合、課税遺産額に適用される税率により、相続税が算出されます。
相続税が課されるのは、遺産総額が基礎控除額を超えた場合のみです。遺産総額が基礎控除額以下であれば、課税遺産額は0円となり、相続税は発生しません。
相続税の具体的な計算方法は以下のステップに従います。
- 全遺産総額から基礎控除額を差し引き、課税遺産額を算出する。
- 法定相続分に基づき、各相続人が相続する遺産額を計算する。
- 各相続人の遺産額に適用される税率を乗じて相続税の総額を求める。
- 実際の遺産取得割合に基づいて、各相続人ごとの正式な相続税額を計算する。
以上のプロセスにより、各相続人の負担する相続税額が決定されます。
名義変更のための登録免許税
相続によって土地を取得した場合、その土地を売却する前には、売主が法的にその土地の所有者であることを明確にする必要があります。これを実現するためには、土地の名義変更手続き、すなわち相続登記が必要です。2024年4月からは、この相続登記が法律により義務付けられる予定です。
名義変更を行う際には、登録免許税がかかります。相続による名義変更の場合、この税金は土地の固定資産税評価額に0.4%を乗じた額となります。これは、相続に伴う土地の名義変更を正式に行い、新しい所有者の名義で土地登記簿を更新するために必要な費用です。
相続した土地を売却する際には、この登録免許税を含めた諸経費を考慮することが重要です。売却前に名義変更の手続きを完了させることで、土地の売買契約がスムーズに進行し、将来的なトラブルを避けることができます。
譲渡に係る譲渡所得税
譲渡所得税は、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を売却することにより得られる利益に対して課される税金です。この税金は、資産の譲渡から生じる所得に基づいて計算されます。
土地を売却した際に発生する譲渡所得税は以下の式で求められます。
譲渡所得税=譲渡所得×適用税率
ここで、譲渡所得は土地の売却価格から土地の取得価格および譲渡にかかった費用を差し引いた金額です。譲渡費用には、不動産会社への仲介手数料や建物の解体費用などが含まれます。
税率は、資産の保有期間によって異なり、5年以下の保有であれば総合税率は39.63%、5年超の保有であれば20.315%が適用されます。この税率には、所得税、住民税、復興特別所得税が含まれます。
例として、売却価格が4,000万円、取得価格が3,000万円、譲渡費用が200万円で、所有期間が5年を超える場合の譲渡所得税の計算は次のようになります。
譲渡所得=4,000万円−3,000万円−200万円=800万円
譲渡所得税=800万円×20.315%=約162万円
また、所有年数には相続した土地に関しても、被相続人が所有していた期間が相続人の所有期間に加算されます。その結果、相続してから5年未満であっても、被相続人の所有期間を合わせて5年以上になる場合は、5年超の税率が適用される点が重要です。
譲渡契約書に貼る印紙税
相続した土地を売却する際、取引を正式に記録する「売買契約書」を作成し、その契約書には印紙税が適用されます。印紙税は、契約書に貼付される収入印紙を通じて納付される税金で、契約金額に応じて印紙税の額が決定されます。
売買契約書に記された契約金額に基づき、必要な収入印紙の金額(印紙税額)が定められています。この印紙税の額は、契約金額が一定の基準を超えるごとに異なり、売買の規模によって印紙税の負担が変わります。
売買契約書への収入印紙の貼付は、税務上の義務であり、適切な金額の印紙を購入し、契約書に貼り付けることで、印紙税の納付が完了します。収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入可能です。
どのような場合に早期に売却した方が良いのか
相続税の納税資金がない場合
相続税の納税資金が不足している状況では、迅速な現金化が求められることがあります。特に、更地のように売却しやすい土地は、早期に売却することを推奨します。相続税の申告および納税期限は、「相続の開始を知った日から翌日を含めて10ヶ月以内」に設定されています。
国税庁が発表した「令和2年分相続税の申告事績の概要」によると、2020年の時点で相続税の納税義務が生じたのは、日本における相続発生のうち、全体の約8.8%に当たる人々でした。これは、相続が発生した際に残された財産が居住用の住宅(被相続人が相続人の生前に一緒に住んでいた自宅については相続税の軽減措置があり)以外に不動産がある場合など、相続税の発生が一部の方にのみ発生していることを示しています。
相続税は高額な負担となりがちなため、納税資金を確保するために、土地を売却し現金化することは一つの有効な手段です。相続税の負担に対処するための資金計画を立てる際は、相続した資産の売却を含めた様々な選択肢を検討することが重要です。
遺産分割がしずらい・遺産分割協議でもめる場合
遺産分割の過程で相続人間で意見が対立し、合意に至りにくい場合、特に土地のような不動産の早期売却が望ましいと考えられます。相続人が多数存在する状況や、相続人間の間で公平な分配が難しいと感じられる場合は、売却が一つの有効な解決策となり得ます。
相続によって土地が相続人の共有物となると、その売却には全ての相続人の同意が必要です。共有状態で一人でも反対者がいれば、売却は実現しないため、全員の合意形成が必要となります。相続人の数が増えると、この合意形成はより複雑かつ困難になります。時間が経過するにつれて二次相続や三次相続が発生し、共有者の数が増え続けると、共有物件の管理や売却が一層困難になります。
相続人が多い場合や、遺産分割協議が難航するような場合には、共有者が比較的少ないうちに、早期に売却し現金化することで、後の複雑化を避け、相続人間での公平性を確保しやすくなります。土地などの不動産を売却して現金化することで、遺産をより分けやすくし、相続人間の合意を形成しやすくなります。
なお、親子で共有の不動産を相続した際の相続税の仕組みや手続き、税金を減らす方法などはこちらを参照ください。
相続した土地を必ずしも急いで売却する必要がないのはどのような時か
相続税が発生しない又は納税資金が十分にある場合
相続税の負担がない、または納税のための資金がすでに確保されている場合、相続した土地を急いで売却する必要は必ずしもありません。このような状況では、土地を保持し続ける選択肢も考慮に値します。
相続税が発生しない場合、つまり遺産の総額が基礎控除額を下回る場合、土地の売却を急ぐ理由は少なくなります。このような状況では、相続税の納税義務が生じないため、土地の利用計画を慎重に練る時間があります。また、「取得費加算の特例」のような特定の税務上のメリットを考慮する必要がないため、売却に関する期限を特に意識することなく、土地の将来的な活用や価値向上に向けた戦略を立てることが可能です。
しかしながら、相続した不動産は空き家のまま放置することで急速に老朽化が進むことも事実です。相続後に特定空き家と認定されることによる固定資産税の増加や、害獣・害虫被害など不動産の価値そのものを損なう危険性もあります。このようなリスクを避けるためにも一度相続した土地や建物の利用方法を検討することが望ましいでしょう。
遺産分割がうまくまとまる場合
遺産分割が円滑に進み、問題なく単独所有となった場合、土地を急いで売却する必要はありません。このような状況では、新たな単独所有者は、土地の利用や売却に関して完全な自由を享受することができます。自分の望むタイミングで、自分にとって最適な方法で土地を活用または売却する選択肢が開かれます。
土地活用については、既に土地を所有している人々、特に相続によって土地を引き継いだ人々にとって、大きなチャンスがあります。相続によって土地を得た場合、その土地を活用することで、収益を生み出す機会があります。例えば、賃貸住宅を建てる、農業や商業用地として活用するなど、様々な選択肢が考えられます。
特に、土地を新規に購入する場合に比べて、相続によって土地を所有する場合の方が、財務的な負担が少なく、土地活用のための追加投資に対するハードルが低くなります。新規購入の場合、土地の購入資金に加えて、活用計画の実現のための追加資金が必要となることが多く、収益性の面で不利になることがあります。しかし、相続によって土地を得た場合は、そのような初期投資の負担がなく、より効率的に土地を活用することが可能です。
相続した土地を早めに売却するメリット
支払った相続税の取得費加算の特例が3年10ヶ月以内であれば使える
取得費加算の特例は、相続開始から3年10ヶ月以内に相続財産を売却した場合に適用される制度であり、譲渡所得税の負担を軽減することができます。この特例により、相続税額の一部を不動産の取得費に加算することが可能となり、結果的に譲渡所得を減少させ、譲渡所得税の軽減を図ることができます。
譲渡所得の計算は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額で行われます。ここで、「売却価格」は相続不動産の売却時の価格、「取得費」は相続によって取得した不動産の購入価格や相続税額の一部が加算された額、「譲渡費用」は売却に際して発生した諸費用(仲介手数料や登記費用など)を指します。相続税額の一部を取得費に加算することにより、譲渡所得が減少し、譲渡所得にかかる税金の軽減が実現します。
取得費加算の特例を適用するための要件は以下の通りです:
- 相続または遺贈によって財産を取得した者であること。
- その財産を取得した者に相続税が課税されていること。
- その財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること。
これらの要件を満たす場合、相続開始から3年10ヶ月以内の売却により、相続税の申告期限から3年を経過する日までの売却を含め、特例の適用が可能です。
空き家の3,000万円特別控除:相続開始から3年以内に空き家を売却し売却益を控除
相続開始から3年以内に空き家を売却した場合、最大3,000万円の特別控除を利用できる「空き家の3,000万円特別控除」は、相続税の計画や不動産の売却戦略において重要な選択肢の一つです。この特例は、相続した居住用家屋やその敷地を対象とし、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。特に、空き家を取り壊した後の土地売却において適用されるため、相続した不動産の最適な活用方法を検討する際に有効です。
適用要件は以下の通りです:
- 相続または遺贈により不動産を取得したこと。
- 被相続人が居住していた家屋とその土地を売却するか、家屋を取り壊してから土地を売却すること。
- 家屋と土地が相続から売却まで空き家状態であること。
- 売却が相続の開始から3年を経過する年の12月31日までに行われること。
- 土地売却価格が1億円以下であること。
- 建築された家屋が昭和56年5月31日以前のものであること。
- 耐震基準に適合しているか、取り壊して売却されること。
この特例を利用することで、譲渡所得が3,000万円以下であれば、実質的に譲渡所得税がゼロになる可能性があります。これにより、相続した不動産を売却する際の税負担を大幅に軽減することが可能となります。特に、耐震基準に適合しない家屋の場合は、修繕するか取り壊して更地にして売却する必要があるため、事前の計画と準備が重要です。
なお、これらの税的なメリットについては、改正などにより条件が変更となる場合もあり、最新の税法を調べることをおすすめします。
相続した土地を放置することだけは避けたほうが良い理由
納税資金が十分にあるなど、早急に売却する必要がない場合においても、空き家として放置することは決しておすすめしません。空き家の放置は不動産の老朽化が急速に進む原因となります。その結果として特定空き家となり固定資産税の負担が上がる場合や、近隣からのクレームなどのリスクもあります。
固定資産税評価の負担がある
相続によって土地を手に入れたが活用予定がない場合、その土地をただ保持しておくことは避け、早期の売却を検討すべきです。土地を所有している間、所有者は固定資産税を毎年納める義務があります。特に、その土地に建物がない、または建設計画が立てられていない場合、固定資産税は一定の金額を継続して支払う必要があります。しかし、居住用地として利用される土地には、「住宅用地の特例措置」として固定資産税が1/3から1/6まで軽減される制度があります。空き家を放置するなどして、特定空き家など一定の条件を満たしてしまう場合には、この特例を受けられなくなります。その場合、土地の所有者は、活用していないにも関わらず高額な固定資産税を支払い続けることになります。このような状況を避け、無用な費用を節約するためにも、相続土地の売却を検討することが賢明です。
近隣住民からのクレームや損害賠償などのリスク
相続により土地を得たが、その管理を怠り放置してしまうと、最悪のシナリオとして近隣住民から損害賠償を請求されるリスクがあります。放置された土地では、雑草や雑木の過剰な成長が隣地に影響を及ぼしたり、害虫や野生動物が繁殖して近隣住民に不快感や損害を与える可能性があります。さらに、土地が荒れ放題になると、不法投棄の誘因にもなり得ます。不法投棄によるゴミ撤去費用は意外と高額になり、後悔するケースも少なくありません。たとえば、不法投棄されたゴミの撤去に20万円の費用がかかる場合もあります。これらのリスクや追加費用を避けるため、もし相続土地の具体的な活用計画がなければ、売却を積極的に検討することをお勧めします。
共有名義の不動産の管理をめぐって相続人同士で争うことが多い
遺産分割がまとまったものの、他の相続人と共有名義で土地を受け継いだ場合、その土地を放置することは後のトラブルの原因となることがあります。共有名義であることにより、土地の管理方針や維持費用の分担に関して意見の対立が生じやすく、これが相続人同士の不和を引き起こす可能性があります。
特に、固定資産税の支払いは共有者間での意見の相違を引き起こす典型的な例です。法律では、固定資産税は所有者全員がその持分に応じて支払うことになっていますが、現実には一人が前面に出て支払うことが多く、他の共有者が負担を回避するケースもあります。
実際に、親から相続した土地を兄弟で共有するケースで、一方が固定資産税の全額を支払い、もう一方が支払いを怠る事例は少なくありません。このような状況は、親族関係の悪化だけでなく、法的な対立に発展するリスクも孕んでいます。
このため、共有名義で相続した土地があり、その活用計画が立っていない場合は、相続人間のトラブルを避けるためにも早期に売却を検討することが推奨されます。
せっかく相続しても再建築不可な物件の場合には用途が限られてしまう
相続した土地が「再建築不可物件」の場合、売却の選択肢を優先的に検討することを推奨します。再建築不可物件とは、一旦建物が解体されると、新たに建築が許可されない土地を指します。このような土地は、建築制限があるため、利用方法が限られており、一般的な土地活用の知識がない場合、効果的な活用が困難になります。
活用オプションとしては、駐車場、駐輪場、トランクルーム、資材置き場の貸出、または太陽光発電パネルの設置などが挙げられますが、これらの活用方法は事業としての運営が必要であり、相応の手間とリスクが伴います。計画立案から許可申請、事業運営に至るまで、多大な労力と投資が求められ、それでいて収益性が保証されるわけではありません。
特に再建築不可物件は、土地の価値が制限されるため、活用によって得られる収益が期待よりも低い場合や、最悪の場合、経済的損失をもたらす可能性も考慮する必要があります。
したがって、このような土地を保有し続けるリスクと比較した場合、売却によって得られる一時的な資金の確保の方が、長期的に見ても経済的メリットが大きいと言えます。再建築不可物件の売却は専門知識を要するため、この分野に詳しい不動産業者への相談が重要です。専門の不動産業者を通じて適切な売却手続きを進めることで、土地の有効活用と経済的負担の軽減を図ることが可能になります。
譲渡所得税を軽減するための重要なステップ
取得費(取得価格)を明確にするための資料収集
相続した土地を売却する際に譲渡所得税が想定以上に高くなる主要な原因は、土地の取得費を正確に証明できないことにあります。節税のためには、取得費を確認できる資料の収集が非常に効果的です。
購入当時の売買契約書が見つからない場合でも、以下の方法で取得費に関する資料を探求できます:
- 不動産会社や売主からの売買契約書のコピー入手
- 銀行の出金履歴による購入価格の推定
- 住宅ローンの契約書からの購入価格の推定
- 抵当権設定額による購入価格の推定
- 日本不動産研究所が提供する市街地価格指数を利用した取得費の算出
これらの資料が手元にある場合は、それらが取得費として認められるか税務署で個別に相談することが重要です。
さらに、取得費には土地の購入価格のみならず、以下の費用も含めることが可能です:
- 相続時の不動産登記費用
- 仲介手数料
- 印紙代
- 登録免許税
- 司法書士手数料
- 不動産取得税
- 立退料や移転料
- 測量費
- 取り壊し費用
- 整地や埋め立て、擁壁設置等の費用
土地を売却する場合、原則として全所有者の取得費を継承します。取得費に関する資料が残っていれば、これらを取得費に加算することにより、譲渡所得税の節税が可能になります。このアプローチは、売却に際しての税負担を軽減させるために重要な手段となります。
参考:取得費がわからない時の計算方法
相続土地の売却に際して、取得費が不明な場合があります。このような状況では、概算取得費を用いることが一つの解決策です。概算取得費は、譲渡価額の5%として計算されます。以下に、取得費不明の状態での税金計算例を示します。
仮定条件:
- 譲渡価額: 3,000万円
- 取得費: 不明
- 譲渡費用: 150万円
- 所有期間: 5年超(長期譲渡所得)
計算例:
- 譲渡所得 = 譲渡価額 – 概算取得費(譲渡価額の5%) – 譲渡費用
- 譲渡所得 = 3,000万円 – (3,000万円 × 5%) – 150万円
- 譲渡所得 = 3,000万円 – 150万円 – 150万円
- 譲渡所得 = 2,700万円
税金計算:
- 所得税 = 譲渡所得 × 15% = 2,700万円 × 15% = 405万円
- 復興特別所得税 = 所得税 × 2.1% ≈ 8.5万円
- 住民税 = 譲渡所得 × 5% = 2,700万円 × 5% = 135万円
総税額:
- 総税額 ≈ 所得税 + 復興特別所得税 + 住民税 = 405万円 + 8.5万円 + 135万円 ≈ 548.5万円
この計算により、譲渡価額3,000万円の土地売却に対する総税額は約548.5万円、譲渡価額に対する税負担率は約18%となります。特に、相続土地の売却で長期譲渡所得の場合、取得費が不明でも、概算取得費の適用により、税負担の概算が可能です。ただし非常に高い税金が発生するため、なんとか取得時の価格を調べることが大切です。
譲渡にかかった費用を漏れなく集計する
相続土地の売却において、譲渡費用を完全に計上することは、税額を軽減する上で重要な方法の一つです。譲渡費用とは、土地売却に直接関連する費用のことを指し、これらを正確に計上することにより、譲渡所得税の負担を減らすことができます。
以下は、譲渡費用として計上可能な主な項目です:
- 売却に伴う仲介手数料
- 売買契約書の印紙代
- 広告料(売却を促進するための広告にかかった費用)
- 測量費(売却目的での土地測量に要した費用)
- 鑑定料(売却価格の査定のために要した鑑定費用)
- 立退き料(借家人を移転させるために支払った費用)
- 登記費用の負担額(買主のために負担した登記関連費用)
- 建物の取得費および解体費用(売却のために建物を解体した場合)
- 解約違約金(より有利な条件での再売却を目的とした契約解除に伴う違約金)
- 建物補修費(売却前の建物の価値を高めるための修繕費)
- 交渉や契約のための交通費や通信費
- 名義書換料(借地権売却時の地主承諾に伴う費用)
特に、相続土地を売却する際には測量を行うことが多いため、「売却のために測量した測量費」は譲渡費用として計上でき、節税の一助となります。
ただし、以下のような費用は譲渡費用として認められません:
- 抵当権の抹消に要した費用
- 遺産分割に関わる支出
- 新居の購入や修繕、移転にかかる費用
- 資産の維持管理に関する費用
- 引越し費用
譲渡費用の適用可能性については、税務上の解釈が複雑な場合があるため、最終的な判断を得るには税務署での個別相談が必要です。このプロセスを通じて、正確な譲渡費用の計上を行い、税負担を最小限に抑えることが重要です。
まとめ
相続税は通常親から子供へ発生するものが多く、かつ税額も多額になりがちです。これらの税金をせっかく払ってもほとんど利用価値がなく金銭的負担が大きかったりその後の相続人同士で揉め事に至ってしまう場合などもあり、より慎重に相続対策と売却後の手続きを行うことが求められています。本ブログでは主に税金の負担を軽減することを目的として相続した不動産を早期売買することのメリットを記載してきました。ぜひこちらのブログを参考に相続予定の資産や遊休状態の資産について弊社にご相談いただけますと幸いです。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)