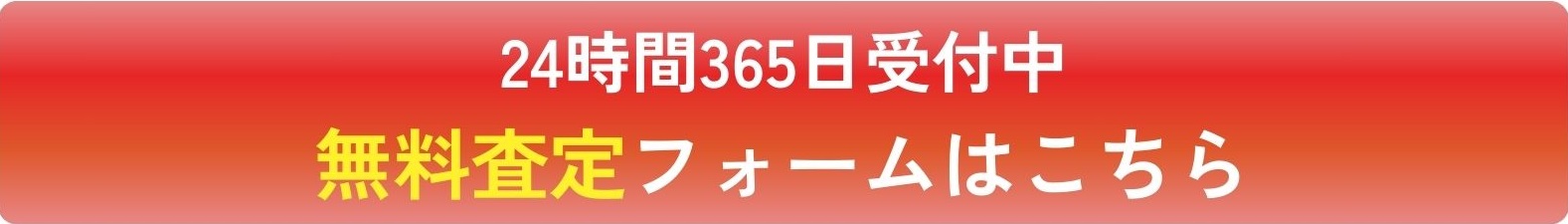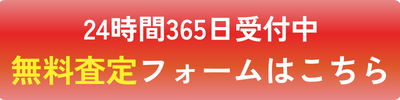両親の逝去後、愛着のある自宅の処分方法について、どのように進めればよいか悩む方は多いです。相続のプロセスを開始するにあたり、まずは遺言書の有無を確認し、法定相続分を把握し、相続登記の手続きについて理解することが重要です。また、相続放棄が最善の選択肢かどうかを慎重に考えることも必要です。不動産の売却方法としては、仲介を利用する方法と、買取業者に直接売却する方法があり、それぞれの方法のメリット・デメリットを考慮した上で選択することが求められます。
親の死後、家の処分前に確認すべき7つのステップ
親の死後、相続を行うにあたっては下記の手順を踏む必要があります。
1.遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には故人の意思を尊重して遺言書どおりに財産を相続します。
2.相続人を確定する
故人の前妻の子供や認知している婚外子がいる場合には相続人となるので、戸籍謄本や除籍謄本で確認します。
3.相続財産を調べる
故人保有の不動産、自動車、骨董、株式、預金、そして忘れてはいけない借金について調査する必要があります。
4.遺産分割協議
遺言がない場合には相続人が集まり遺産の分割について協議を行う必要があります
5.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議について合意したことを証するために協議書を作成します。相続登記を依頼する司法書士が作成する場合や、税務申告を行う税理士が作成する場合が多いです。
6.相続登記を行う
まとまった協議書をもとに不動産等については相続による所有権の移転の登記を行います。
7.相続税を納付する
相続財産から相続税を計算し、各相続人が相続した財産の割合に応じて納税します。税理士が計算と申告を行い、納付は相続人が行います。
遺言書とは何か?
まず、遺言書が存在するか否かを明確にし、その内容に従って行動を取ることが求められます。
遺言書は3つの種類があり、それぞれ公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。うち、秘密証書遺言はほとんど利用されていないこともあり、本ブログでは割愛します。自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴については下記の通りです。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成方法 | 自分で記述 | 公証人が記述 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 (法務局に預けない場合) | 不要 |
| 保管方法 | 自分 (法務局保管も可能) | 原本は公証役場 |
| 費用 | 0円 (法務局保管なら3,900円) | 16,000円〜 (財産に応じ加算) |
| メリット | 手軽に作成可能 費用がかからない | 無効になりにくい 紛失のリスクがない 作成に署名と押印で済む |
| デメリット | 無効になる可能性 自筆である必要がある | 費用と手間がかかる |
遺言書の探し方
自筆証書遺言と、公正証書遺言、秘密証書遺言とではそれぞれ相続人が亡くなった後の相続手続きの進め方が異なります。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、相続人の中の誰かが保管していることが多いものの、そうでなければ発見が難しいケースがあります。遺言が見つからずに遺産分割が進んでしまうリスクがあるため、改ざんや隠匿の可能性にも注意が必要です。これを防ぐため、2020年7月10日からは遺言書保管法に基づき、法務局が自筆証書遺言の保管所として機能するようになりました。これにより、遺言書の紛失や隠匿を防ぎ、その存在を容易に確認できるようになりました。
しかし、遺言書を必ず保管所に預けなければならないわけではありません。そのため、自筆証書遺言の発見方法には主に2つの方法があります。一つは法務局(遺言書保管所)への確認であり、遺言書を保管している場合は「保管証」の存在が手がかりとなります。保管証が見つかれば、法務局で遺言書の情報を含む「遺言書情報証明書」を請求できます。これは遺言書のスキャン画像を印刷したもので、相続手続きにおいて原本同様に使用可能です。
保管証がない場合は、「遺言書保管事実証明書」を請求して遺言書が保管されているかを確認します。ただし、この証明書では遺言書の内容はわかりません。内容を知るには「遺言書情報証明書」の請求や保管所への直接確認が必要です。相続人には遺言書の保管や閲覧の事実が通知され、遺言者の死亡確認時や証明書交付時には指定された人への通知も行われます。
遺言書保管事実証明書の請求には、遺言者の死亡事実が確認できる書類、請求者の住民票、相続人であることを示す戸籍謄本などが必要です。請求は全国の法務局で行え、窓口または郵送での請求が可能です。手数料は1通につき800円が必要です。
遺言書が法務局に保管されていない場合、自宅の金庫や仏壇、銀行の貸金庫、信託銀行、弁護士や税理士、行政書士、信頼できる親戚や友人、菩提寺の住職など、遺言書が置かれている可能性のある場所を探します。遺言書を発見した際の注意点については、別途確認することが重要です。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言には、遺言者、公証人、証人の署名押印が施された唯一無二の原本と、公証人がそのコピーであることを証明した正本と謄本が存在します。原本は法律に基づき公証役場に20年間保管されることとなっていますが、実際にはこれを超える期間保管されることもあります。1989年からは、コンピュータを利用した検索システムが導入されており、相続人や利害関係者は近隣の公証役場に問い合わせることで、無料で全国の公正証書遺言を検索できます。
公正証書遺言の謄本は、原本が保管されている公証役場からのみ請求可能です。この手続きには、遺言者の死亡を証明する戸籍謄本、請求者が利害関係者であることを示す書類(戸籍謄本等)、請求者の身分を証明する書類が必要になります。これにより、相続手続きに必要な遺言書のコピーを取得することが可能です。
遺言書を見つけた時にすべきこと
遺言書を発見した時、または預かっている状況では、正しい手続きを踏むことが非常に重要です。まず、遺言書の種類を特定しましょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が遺言書保管所以外で見つかった場合、その遺言書を開封せずに家庭裁判所で検認を請求する必要があります。遺言書を裁判所の監督なしに開封することは、民法により罰則の対象とされています。検認は遺言の形式や状態を確認し、将来的な改ざんやすり替えを防ぐためのものであり、遺言内容の判断ではありません。たとえ遺言書に不備が見られる場合でも、検認手続きを行うことは必須です。
検認が終わったら、検認済証明書を裁判所から申請して、それを遺言書に添付してもらいます。これにより、遺言に基づいた相続手続きを進めることができます。
一方、自筆証書遺言が遺言書保管所に預けられていた場合や、公正証書遺言の場合は、検認手続きを行う必要はありません。これらの遺言書は、それぞれ遺言書保管所の管理や公証人による作成・保管によって、改ざんやすり替えのリスクが排除されているためです。
遺言書保管所から交付された「遺言書情報証明書」や、公正証書遺言の正本、謄本に従って相続手続きを行いましょう。このプロセスを通じて、遺言者の意志に沿った適切な相続が実現されます。
遺言が見つからないときは遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、亡くなった人が残した遺産を相続人間でどのように分配するかを決める重要なプロセスです。遺言書が存在する場合、その指示に従って遺産を分けます。しかし、遺言書がない時は、民法に定められた法定相続分に基づいて遺産を分割します。
それにもかかわらず、相続人全員が合意すれば、遺言や法定相続分とは異なる方法で遺産を分割することが可能です。この合意に基づき遺産を分配する過程を「遺産分割協議」と呼びます。遺産分割協議は全ての相続人が同意しなければ無効であり、行方不明者を除外したり、未知の相続人が後から現れた場合には、以前の協議は無効になる可能性があります。
遺産分割協議で合意に至らない場合、家庭裁判所による調停や審判を求めることができます。この過程では、調停委員や家事審判官が間に入り、双方の意見を聞きながら解決策を模索します。調停が決裂した場合には審判に移り、裁判所が遺産の分割方法を決定します。
家庭裁判所での手続きは専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することが推奨されます。司法書士は簡易裁判所での代理権はありますが、家庭裁判所での手続きに関しては代理権がないため、遺産分割に関する家事手続きの代理は行えません。
相続登記の確認とその重要性
相続登記は、故人(被相続人)の不動産を引き継ぐ際に、所有権の名義を変更するために必要な手続きです。不動産の所有者は法務省の登記簿に記録されており、その変更手続きは法務局で行われます。相続登記を適切に行わないと、第三者への所有権の主張ができなくなります。
相続登記の重要性は、不動産の売却、活用、担保設定時に特に明らかになります。不動産を含む相続が発生した場合、将来的なトラブルを防ぐためにも、相続登記は非常に重要です。
以前は、相続登記をいつ行うべきかに関する法的な義務や期限は設けられていませんでしたが、相続登記の義務化が決定され、期限内に登記を行わないとペナルティが課されるようになりました。
相続登記が義務化される背景には、所有者不明の空き家や空き地が増加し、これが不動産取引や都市開発の障害となる問題があります。国土交通省の報告によると、所有者の所在が不明な土地は全体の20.1%にも及び、その多くが相続による未登記の土地です。所有者不明土地は経済損失や行政の有効活用の妨げとなっており、相続登記の義務化はこの問題への対応策の一つとされています。
相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されます。新たな法律により、相続開始と不動産の所有権を知った日から3年以内に相続登記を完了させなければなりません。複数の相続人がいる場合は、最後に相続の事実を知った人の認知日から3年以内に登記を行う必要があります。この新規定は、相続に関するトラブルの解消と所有権の明確化を目的としています。
忘れてはいけない相続税の納税
親の遺産として不動産を相続する際、考慮すべき税金には主に相続税と登録免許税があります。これらの税金は、一定額以上の財産を相続した場合に適用されます。
- 相続税は、故人から引き継いだ財産に対して発生する税金で、全ての相続人に適用されるわけではありません。相続税が発生するかどうかは、故人の財産総額から基礎控除額を差し引いた後の金額によって決まります。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出され、この額を超える財産を相続した場合にのみ、相続税の申告と納税が必要になります。
- 登録免許税は、相続によって不動産の名義変更を行う際に発生する税金です。この税金は、不動産の固定資産税評価額に基づき、その0.4%の額で計算されます。
相続税の申告期限は、故人の死を知った日の翌日から10か月以内です。この期限を遵守しない場合、無申告加算税などのペナルティが適用される可能性があります。相続した不動産は、現金などと比較して相続税負担を軽減する特例や評価のルールがあるため、適切な対策を講じることが重要です。
また、相続不動産の売却に際しては、遺産分割協議を通じて相続人間で財産の分配方法を決定することが一般的です。遺産分割協議では、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割などの方法が検討され、相続人全員の合意に基づいて不動産の扱いが決定されます。相続税の納税義務や遺産分割の方法を事前に理解し、適切な準備と計画を行うことが、スムーズな相続プロセスのために不可欠です。
あなたが相続人の時に行う3つの選択肢
相続が発生した際に、相続人は相続の開始があったときから3ヶ月以内に下記のいずれかを選択する必要があります。
1.相続放棄
2.限定承認
3.単純承認
このうち、相続放棄と限定承認を選ばなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄は全ての財産を放棄する選択肢
相続放棄は、相続人が故人から遺された財産全体を引き継ぐことを拒否する法的手続きです。この選択肢を選ぶと、プラスの財産だけでなく、借金やその他の負債などマイナスの財産も含めて、すべての相続から手を引くことができます。
通常、相続にはプラスの資産だけでなく、負債も含まれるため、故人の借金が多い場合には相続放棄が有効です。相続放棄を行うためには、故人の死を知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したとみなされる場合がありますので、注意が必要です。
手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。相続放棄が認められると、その相続人は法的に、初めから相続人ではなかったかのように扱われます。このプロセスを通じて、故人の負債を引き継ぐことなく、相続から解放されることが可能になります。
限定承認は相続で得た資産の範囲を限度として負債も相続する
故人の残した債務の全貌が不明な場合、相続により得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ「限定承認」という手続きが選択肢としてあります。これは、故人の負債が明らかでない一方で、プラスの財産が存在し、相続によって何らかの財産が手元に残る可能性がある場合に適用されます。
限定承認を行う場合、相続放棄と同様に、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。ただし、相続放棄が個々の相続人によって独立して行えるのに対し、限定承認は相続人全員が一致して行う必要があります。
単純承認の場合、後になって発見された債務も相続財産に含まれますが、限定承認を選ぶと、相続によって得られる財産を上限として債務を負担します。これにより、故人のマイナスの財産がプラスの財産を上回るリスクを回避でき、相続人の財産保護に役立つ選択肢と言えます。
全ての権利や義務を引き継ぐのが単純承認
相続放棄や限定承認を行わない場合、法的には単純承認をしたとみなされます。これは、故人の全ての権利と義務を引き継ぐことを意味し、相続放棄や限定承認の申し立てが可能な3ヶ月の熟慮期間内に特に行動を起こさなかった場合に自動的に適用されます。この期間内に、相続人は自分の選択を慎重に考え、必要に応じて行動を起こすことが期待されます。
プラスの財産が豊富な場合、多くの法定相続人は遺産分割協議を選択し、故人からの財産をどのように分配するかを決定します。これには、相続人全員の協議と合意が必要となり、遺産の分配について意見が一致しない場合もあります。また、預金の引き出しを含む多くの手続きには、法定相続人全員の同意が求められるのが通常です。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄には、故人からの資産を一切受け取れなくなる等の複数のデメリットが伴います。相続放棄を選択すると、プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合でも、その財産を受け取る機会を失ってしまいます。特に、全相続人が相続放棄した場合、長年家族に受け継がれてきた財産が国庫に帰属してしまうリスクもあります。また、先順位の相続人が放棄すると、後順位の相続人に不意に負担が移ることがあります。加えて、相続放棄後も相続財産の管理義務が残るケースが存在し、放棄が原則として撤回不可能であるため、後になって財産の価値を認識したとしても手遅れになります。さらに、死亡保険金や死亡退職金に関する非課税枠の利用が制限されることもデメリットの一つです。
これらのデメリットを踏まえ、相続放棄を検討する際は、亡くなった方の財産状況を詳しく把握し、相続資産の重要性を考慮して、慎重に判断する必要があります。生前の家族とのコミュニケーションやエンディングノートの作成、遺言書の活用など、事前の準備が将来的な混乱を避けるためにも重要です。また、相続に関する複雑な手続きについては、専門家への相談を通じて、正確な情報とアドバイスを得ることが推奨されます。
相続した家を売却するために注意すべきこと
実家の処分は時間のかかる手続きだということを理解する
実家の売却プロセスは予想以上に時間がかかることを理解することが重要です。具体的には、「アットホーム」による首都圏の売却事例調査では、自宅の売却完了まで平均で8ヶ月が必要で、これはマンションが平均6ヶ月、戸建てが平均11ヶ月を要することを示しています。これには、不動産会社への依頼から価格査定、売却活動開始、そして売買契約から引き渡しまでの期間が含まれます。
出典:アットホーム調べ・アットホーム株式会社「中古物件の“売り手”と“買い手”のキモチ調査」
相続においては、遺言の有無の確認、相続人の特定、財産調査、遺産分割協議といったさらに複雑な手続きが加わり、これらには追加で平均4ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要となります。このため、相続による家の売却は全体として1年半から2年程度の時間を見込む必要があります。特に、遺産分割協議が長引く場合、売却プロセスに着手すること自体が遅れるため、計画的な売却戦略と資金計画の立案が不可欠です。相続による家の売却は長期戦になることを前提に、早めの準備と相続人間での協力が重要になります。
遺産分割で揉めないように注意する
遺言な残されなかった場合には、遺産分割協議を相続人で行い残された相続財産を分けることになりますが、遺産分割協議で合意がなされないとその後の不動産の売却も困難になります。
遺産分割協議がスムーズに進まない場合は、様々な原因が考えられます。特に、以下のようなケースでは遺産分割でトラブルが発生しやすくなります。
- 不動産を含む相続財産がある場合、その分割方法を巡って相続人間で意見が対立しやすくなります。
- 再婚していた被相続人の場合、前婚と後婚の家族間で相続に関する対立が生じる可能性があります。
- 相続人同士が疎遠であったり、仲が悪い場合、遺産分割協議が困難になります。
- 一部の相続人と連絡が取れないと、遺産分割協議を開始すること自体ができません。
- 一次相続が未解決の状態で二次相続が発生すると、さらに協議が複雑化します。
- 遺産を独占しようとする相続人がいる場合、協議は難航し、法的な手続きが必要になることもあります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、弁護士に仲介を依頼するか、遺産分割調停や審判を家庭裁判所に申し立てることが一つの解決策です。弁護士は遺産分割に関する争点を整理し、適切なアドバイスを提供することで協議を前進させることが期待できます。また、調停や審判を通じて、相続人全員が納得できる合意に至ることが可能です。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、互いの立場を理解し合い、感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが重要です。また、遺産に関する法的知識を持つ専門家のアドバイスを参考にすることで、公平な解決策を見つけることができるでしょう。遺産分割が難しい状況であればあるほど、専門家への相談が解決の鍵となります。
不動産は代償分割などを利用して、単独所有とすること
共有の不動産の売却にあたっては共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対する共有者がいる場合、売却を実行することができません。またそのような共有状態が長く続くことで、2次相続が発生し、さらに分割が進むことで、権利関係がさらに複雑化する可能性があります。これらの障害を取り除くために、相続発生時に共有状態を作らないことが重要です。具体的には代償分割の手続きを活用し、不動産の全ての権利を依頼者が相続し、その代わりに、他の相続人へ現金や他の相続する金融資産を分割する手続きを言います。代償分割のデメリットは不動産を取得する依頼者が十分な現金を持っているか、不動産以外の相続財産が十分である場合にのみ可能な手続きということになります。また遺産分割協議で他の相続人の合意を得る必要があるため、他の相続人とよく話し合う必要があります。相続した不動産を売却することについて抵抗感を感じる相続人もいるため、注意が必要です。
換価分割も一つの方法
換価分割は、遺産を売却して現金化した後、その収益を相続人間で分配する方法です。この選択肢は、特に納税資金の確保が必要な場合や、現物の財産が分割しにくい時、使用予定のない不動産がある場合に適しています。換価分割には、代償分割、現物分割、共有分割といった他の遺産分割方法と比較して、特定の利点がありますが、一方で独自のデメリットも伴います。
換価分割の主なメリットは、財産を公平に分割できる点と、納税資金の確保が可能であることです。現物では分割が難しい財産を現金化することで、相続人間での納得感を高め、相続におけるトラブルを防ぐことができます。また、相続税の納付に必要な現金を確保できるため、財産の売却が相続税納税の解決策となり得ます。
しかし、換価分割には売却益に税金が発生する、売却の手間と時間がかかる、市場の状況によっては希望通りの売却価格が得られない可能性があるというデメリットも存在します。特に、売却過程で相続人全員の同意が必要になることが多く、売却に時間がかかるため、相続税の申告期限内に資金を確保できないリスクも考慮する必要があります。また、売れ残りが生じた場合には、その期間中も固定資産税が発生しますので、これらの税金の負担についても相続人間で事前に合意しておくことが重要です。
換価分割を選択する場合の流れは、まず遺産分割の方法として換価分割に合意し、遺産分割協議書を作成します。その後、不動産登記を行い名義変更をしてから不動産を売却し、売買代金を受領します。最終的に、受け取った売買代金を遺産分割協議書に基づき相続人間で分配します。この過程では、相続人全員の協力と合意が必要であるため、事前の準備と計画が重要となります。
不動産の売却方法としては仲介と買取の2通り
不動産の売却方法としては不動産業者に売買を依頼し、売り手と買い手を探してもらう仲介と、不動産業者が直接買い取る買取の2種類があります。これらの特徴を説明します。
仲介の場合には時間がかかる、売れるかどうかわからない
不動産の仲介による売却は、売り手と買い手の最適なマッチングを目指す方法で、理想的には市場価格またはそれ以上での取引が可能になるメリットがあります。このプロセスでは、不動産会社が売り手の代理として条件の良い買い手を見つけ出す役割を担います。仲介を通じた売却では、売買契約が成立した際には不動産売買価格の約3%(売買価格によって異なる場合があり)の手数料が発生する点も理解しておく必要があります。
仲介の大きなメリットは高額での売却可能性にあるものの、売出価格に見合うオファーがなければ売却に至らず、長期化するリスクも伴います。当初想定した金額での売却が叶わず、徐々に売買価格を切り下げることは多々あります。また、物件が空き家の状態である場合、維持管理やメンテナンスの状況が買主の購買意欲に大きく影響します。空き家の状態が長引くと、内装のカビや外壁の劣化、庭の荒れ具合などが悪化し、これらが売却活動においてマイナスの印象を与える要因となり得ます。そのため、売却活動期間中も定期的な清掃やメンテナンスが非常に重要です。売却プロセスをスムーズに進めるためには、物件の状態を適切に維持し、買い手が好印象を持つよう努めることが求められます。
さらに個人間での売買の場合、購入者の住宅ローンについても検討する必要があります。例えば老朽化した不動産の場合、新築と異なり建物の担保価格がほとんどつかず、銀行からの住宅ローンがつかないケースも想定されます。また接道義務を満たさない再建築不可不動産の場合、住宅ローンが基本的につきません。せっかく買主を見つけてきても、ローンが降りなければ売買契約が白紙に戻るなど、手続きも複雑です。
買取の場合には現金化が早く手続きも迅速
不動産の買取は、業者が直接買主となる方式で、この方法の最大の利点は、売却プロセスが迅速であることです。買取によって、売却から現金化までの期間を大幅に短縮でき、即座に資金を得ることが可能になります。仲介手数料が不要な点も、買取の大きなメリットとして挙げられます。直接業者への売却であるため、売主は仲介に伴う手数料の支払いを省略でき、結果的に売却に関わる追加費用を抑えることができます。
結論:相続による不動産の売買は買取業者への買取がおすすめ
結論として、相続による不動産の売買は買取業者への売却を強くおすすめします。
理由1:相続の発生から現金化までの期間が短い
相続による不動産売却について検討する際、仲介を利用した場合の平均的な売却期間は約1年半から2年となることがあります。さらに、売却価格が希望通りにならないリスクも考慮する必要があります。長期間にわたり空き家の管理を行うことは、経済的負担だけでなく、精神的なストレスも伴います。また、相続が発生すると、不動産だけでなく他の遺産についても分割協議が必要となり、その手続きには多大な時間と労力がかかります。これらの点を踏まえ、日常業務と並行して相続に関する問題を解決することは、大きな負担となりがちです。
そのため、相続不動産の売却方法としては、買取業者による買取をおすすめします。買取による売却は、相続発生後の早期に現金化を実現できるため、相続に伴う負担を大幅に軽減できる利点があります。買取業者による速やかな手続きにより、遺産分割に関する手間や精神的ストレスを最小限に抑えることが可能です。加えて、不動産の状態による価格の変動リスクや、売却活動中の維持管理費用などの経済的負担を避けることができます。
理由2:現金化の確実性
不動産買取において、業者は迅速な査定を通じて市場価格に基づいた買取を提供します。この方法の最大の利点は、売却の確実性が非常に高いことです。特に、ローンの残債がある不動産でも、買取業者は現金での直接買取を行うため、売却がスムーズに進行します。さらに、再建築不可の物件など、一般の市場での売買が困難な不動産についても、買取専門の業者であれば取引が可能な場合が多いです。これは、個人間取引では住宅ローンの利用が難しいようなケースでも、買取ならば解決できるケースがあるため、売却の不確実性を避けることができます。このように、買取による不動産売却は、売却の確実性と迅速性を求める場合に特に推奨される方法です。
理由3:売主の瑕疵担保責任が免除される
個人間での不動産取引では、契約後に予期せぬ瑕疵(かし)が見つかった場合、売主がその修繕責任を負うことが一般的です。これには、年月が経過した建物の雨漏り、床下のカビ、白アリ被害などが含まれます。特に空き家の場合、放置されている間に老朽化が進み、売り出し期間中に瑕疵が顕在化するリスクが高まります。これは、相続により不動産を取得し、相続税を支払った後でも、売却によって予期せぬ追加費用が発生する可能性があるという意味で、売主にとっては大きなリスクとなります。
一方で、専門の不動産業者への買取では、このような契約不適合責任を免除する特約を設定することが一般的であり、多くの場合、売却時にこの責任が免除されます。これにより、売主は瑕疵に関連する責任から解放され、心理的な負担や追加的な費用のリスクを避けることが可能になります。
不動産買取の選択は、売却プロセスを迅速に進めるとともに、売主の瑕疵担保責任のリスクを最小限に抑える有効な手段です。このため、相続による不動産の売却を検討する際は、専門業者への買取が推奨されます。
他にも空き家について注意すべき点
相続によって自宅を引き継いだ際、買取専門業者を通じた迅速な売却を推奨しました。その理由の一つとして、空き家の所有が伴う費用とリスクを最小限に抑えることが挙げられます。空き家を保有し続けることのデメリットは多岐にわたりますが、主な問題点としては、空き家の老朽化、法的なリスクの増加、税金などの固定費の増加や維持管理の問題があります。これらのリスクを考慮すると、相続した不動産は早期に適切な処理を行うことが賢明です。
空き家は急速に老朽化する
人が住まなくなった空き家は、換気不足や定期的なメンテナンスの欠如により、老朽化が急速に進む傾向にあります。この現象は、将来的に物件を自己使用する場合や、賃貸市場への供給を考えている場合に特に重要です。なぜなら、物件を利用可能な状態に戻すためには、想定外の修繕費用や改修費用が発生するからです。したがって、空き家の維持管理は、その後の利用計画に応じて、適切に計画し実行する必要があります。定期的な換気、清掃、及び設備の点検は、物件の価値を維持し、将来的なコスト増加を避けるために不可欠です。
法的なリスクは増加する
空き家を長期間放置することは、様々な法的なリスクを高めることにつながります。具体的には、近隣からの苦情や放火、盗難、そして不法占拠など、多岐にわたる問題が発生する可能性があります。これらの問題が発生した場合、弁護士費用や訴訟関連の賠償費用など、予期せぬ出費が生じることがあります。また、愛着のある実家が犯罪に関連する事態に巻き込まれることで、心理的なストレスを感じる場合もあります。もし避けられない事情で空き家を所有し続ける必要がある場合は、定期的な巡回や保守、周囲との良好な関係維持など、適切な管理策を講じることが重要です。
放置すると増える固定資産税
特定空き家として指定された場合、固定資産税が現行の最大6倍まで増加するリスクがあります。この増税は、不動産の放置が周囲の環境や景観に悪影響を及ぼすと見なされた場合に適用されるものです。また、行政からの厳しい指導や、場合によっては立ち入り調査が行われる可能性もあり、これに伴う時間的、精神的な負担も考慮する必要があります。このような追加の負担を避けるためにも、空き家の状態を適切に管理するか、タイムリーに売却するなどの対策を検討することが重要です。
維持管理の方法と費用
空き家を所有し続ける必要がある場合、その将来的な活用計画に応じた維持管理方法を選択することが重要です。主に、自主管理と委託管理の2つの選択肢がありますが、それぞれには利点と欠点が存在します。自主管理では、所有者が直接、物件の状態をチェックし、必要なメンテナンスを行いますが、時間や労力の負担が大きくなります。一方、委託管理では不動産管理会社に維持管理を任せることで、所有者の手間を省くことができますが、管理費用が発生します。空き家の活用計画に基づいて最適な管理方法を選択し、空き家がもたらすリスクを最小限に抑え、財産価値の維持に努めることが求められます。
まとめ
相続による不動産の取得から売却までのプロセスは、法的な手続きや精神的な負担、そして時間を要する複雑な作業です。このプロセスを少しでもスムーズに進めるためには、相続が発生する前から家族での事前の話し合いが非常に重要となります。また、相続の手続きや資金計画に関して専門家からの意見を事前に聞いておくことも有効です。
私たちは相続に関するサービス、資産管理、資金計画の立案、不動産売買や仲介、さらにはリノベーションに至るまで、一貫したサポートを提供しています。特に相続と資金計画においては、専門的な知識を活かした多角的なアドバイスを提供しています。不動産の相続や売却でご不安やご相談がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)

画像-1-160x90.png)