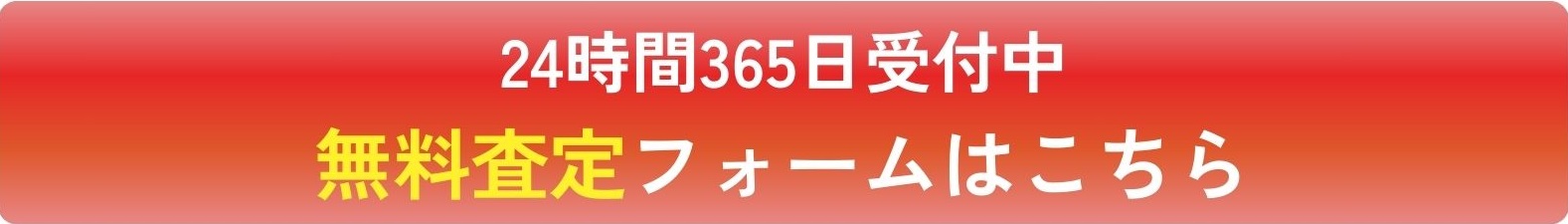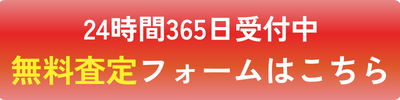再建築不可物件に関する包括的なガイドを提供します。本ガイドでは、建築基準法第43条第2項の救済措置、再建築不可物件の定義、接道義務、道路の種類、そして再建築に関する様々な調査方法について解説します。また、裏ワザや抜け道として知られる「43条2項の認定・許可」の詳細、横浜市や東京・神奈川の事例を交えながら、包括同意基準や個別提案基準についても深掘りします。
再建築不可物件って何?
再建築不可物件とは、建築基準法や都市計画法などの法規制により、敷地上の建物を新たに建て替えることが許可されない物件のことを指します。これらの物件は、主に以下の2つの理由により建て替えが制限されます。
- 建築基準法における接道義務を満たしていないケース
- 都市計画法により建築が禁止されているエリアに指定されているケース
本記事では、これらの再建築不可物件に対する救済措置について、「建築基準法上の再建築不可物件」として詳細に解説します。
接道義務とは何か
建築基準法第43条に基づく接道義務とは、建築物が位置する敷地が特定の要件を満たすことが求められる制度です。この要件には、敷地が建築基準法に準拠した幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが含まれます。
敷地がこの接道義務を満たさない場合、既存の建築物の解体後の再建築が制限されるなど、土地の活用方法や資産価値に大きな影響を及ぼすことがあります。しかし、接道義務には例外も存在します。道路の造成時期や周辺環境に応じて、再建築が許可されるケースもありますし、土地の状況を改善することで後から接道義務を満たすことも可能です。
建築基準法42条に規定する道路って何?
道路に2メートル接道しているからといって、全ての建物が建て替え可能というわけではありません。肝心なのは、接道している道路が「建築基準法第42条で規定する道路」であるかどうかです。再建築が許可されるためには、この条件を満たす必要があります。
建築基準法第42条で規定されている道路には、以下の種類があります。
- 第1項1号道路:道路法に基づく道路(例:国道、都道府県道、市町村道)
- 第1項2号道路:都市計画法に基づく開発許可や土地区画整理事業によって造られた道路(例:大規模開発分譲地内の道路)
- 第1項3号道路:昭和25年11月23日以降、基準法施行時または都市計画法区域指定時に存在する幅員4メートル以上の道路(例:昭和25年以前の道路)
- 第1項4号道路:道路法等による新設等の事業計画があり、2年以内にその事業が執行される予定の道路(例:新設予定道路)
- 第1項5号道路:土地の所有者が築造する幅員4メートル以上の道路(例:位置指定道路)
- 第2項道路:第1項3号に該当するが幅員4メートル未満の道路(例:第2項道路)
これらの道路は、一見して区別がつかない場合も多いです。例えば、農道や私道など、これらには該当しない道路も存在します。そのため、建築を計画する際は、敷地が建築基準法第42条に規定される道路に接しているかどうかを正確に調査する必要があります。
建築基準法42条の道路か調べる方法
再建築が可能かどうかを判断する際には、まず、該当不動産が接道している道路が建築基準法第42条に定められた道路かどうかを確認する必要があります。
この「建築基準法第42条のどの項及び号に該当する道路か」を示すものを『建築基準法道路種別』と呼びます。多くの自治体では、この道路種別をインターネット上で提供している地図を公開しています。例えば、世田谷区では「せたがやiMap(世田谷区電子地図情報配信サービス)」のように、自治体の公式ウェブサイトで情報を得ることが可能です。
インターネット検索で「[行政名]+道路種別」と入力して情報を探してみてください。もしオンラインで情報が見つからない場合は、各自治体の建築指導課や都市計画課などに直接問い合わせることで、道路の種別を確認することができます。
間口が2mあるか調べる方法
再建築が可能かどうかを判断する際には、不動産が建築基準法第42条に定められた道路に接していることだけでなく、その接道部分が最低2メートル存在するかどうかも重要です。通路部分を含む場合でも、どこか一部分が2メートル未満であれば、再建築は許可されません。また、通路部分に空中越境(隣地からの建物のはみ出し等)がある場合、その部分は建築確認の際の敷地面積に含まれず、越境により2メートル未満の箇所があると再建築はできません。
接道部分が2メートルあるかどうかの確認には、専門家である土地家屋調査士による測量が必要です。土地家屋調査士を探す際には、「日本土地家屋調査士会連合会」の公式ウェブサイトを利用すると良いでしょう。そこでは土地家屋調査士の検索が可能で、地域や専門分野に応じた専門家を見つけることができます。
再建築不可物件の救済措置(裏ワザ・抜け道)には何がある?
再建築不可物件の救済措置には、建築基準法第43条第2項に基づく認定や許可の手続きがあります。しかし、この手続きは単純ではなく、物件ごとに手続きの難易度が大きく異なります。そのため、どの手続きが必要かによって、金融機関の担保評価や不動産としての価値も大きく変わってきます。
この認定や許可を受ける過程は、物件が接する道路の種類や、物件及び周辺環境の状況によって異なります。この救済措置を受けるための方法や難易度をより詳しく理解するために、以下のポイントについて解説します。
- 43条第2項第1号の認定:特定の条件を満たす場合に認定を受ける手続き
- 43条第2項第2号の許可・一括許可基準(包括同意基準):一定の基準に基づき、特定行政庁から包括的な同意を得る方法
- 43条第2項第2号の許可・個別提案基準:個別の提案に基づく許可を求める手続き
- 43条第2項第2号の許可、個別審査:物件ごとの特性を考慮した個別の審査を受けるプロセス
これらの救済措置を適切に理解し、活用することで、再建築不可物件に新たな価値をもたらすことができるのです。
43条2項1号の認定
建築基準法第43条第2項第1号による認定は、再建築不可物件に対する比較的容易な救済措置の一つです。この認定は、市長や県知事などが安全上問題ないと判断する特定の基準に基づきます。
建築許可の難易度は比較的低いですが、担保評価の難易度は高いとされます。43条2項1号の認定に基づき再建築が可能な物件は、通常の再建築可能物件とほぼ同様に扱われます。
しかし、この認定を受けるためには、自治体が定める具体的な要件を満たす必要があります。これらの要件は自治体によって異なり、例えば「接する道に雨水・汚水処理施設があること」「幅員4メートル以上の道路に面していること」「境界が明示されていること」「道の勾配が9%以内であること」などがあります。
世田谷区の場合、以下のような認定基準が設定されています。
- 基準1: 敷地と道路の間に以下のいずれかに該当するものが存在し、道路に有効に接続する幅員4メートル以上の通路が確保されている敷地であり、さらに特定の基準に適合する計画であること。
- 管理者の占用許可、承諾または同意が得られた水路
- 地方公共団体が管理する認定外道路等の公有地
- 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地
- 建築物の用途及び規模が、延べ面積500平方メートル以内で特殊建築物以外のものであること
- 隣地境界線から建築物の部分までの水平距離が50センチメートル以上であること
- 基準2: 道路に有効に接続する地方公共団体の管理通路で幅員4メートル以上の道が確保され、道の延長が35メートル以下であり、この道に2メートル以上接する敷地で、特定の条件に該当するもの。
- 建築物の用途及び規模が、延べ面積500平方メートル以内で特殊建築物以外のものであること
- 隣地境界線から建築物の部分までの水平距離が50センチメートル以上であること
- 基準3: 位置指定道路の基準に適合する道に2メートル以上接する敷地であり、特定の条件に該当するもの。
- 敷地分割をする場合は、特定の日付現在の敷地に対して4以下であること
- 建築物の用途及び規模が、延べ面積500平方メートル以内で一戸建ての住宅、長屋または兼用住宅とすること
- 隣地境界線から建築物の部分までの水平距離が50センチメートル以上であること
- 申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについて、特定の者の承諾が得られたものであること
このように、43条2項1号の認定は、再建築不可物件の救済に有効な手段ですが、その基準は自治体によって異なり、それぞれの要件を十分に理解し遵守することが重要です。
43条2項2号の許可・一括許可基準(包括同意基準)
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可は、再建築不可物件の救済措置の一環として重要な役割を担っています。この許可を得る際の建築許可の難易度は中程度、担保評価の難易度はやや高いとされます。
43条2項2号の許可を得るプロセスには、建築審査会の同意を経て、市長や県知事などの許可が必要です。建築審査会は通常、5~10名の委員と1~3名の専門調査委員で構成されており、会合は月に1回程度の頻度で開催されます。
この審査会では、43条2項2号の許可に限らず、建築基準法に適合できない建物の新築や用途変更などの案件も判断されます。このため、個々の案件に対して同意を得るのは容易ではありません。
このような状況を踏まえ、効率的な判断を行うために「一括許可基準(包括同意基準)」というものが設けられています。この基準に合致する案件は、再建築が可能とされています。包括同意基準には、具体的な条件や要件が定められており、これらを満たすことが再建築の許可に直結します。
世田谷区を例にした43条2項2号の一括許可基準(包括同意基準)
世田谷区の例を挙げると、建築基準法第43条第2項第2号に関連する一括許可基準(包括同意基準)には、いくつかの具体的な条件が設定されています。
基準1: 敷地と道路の関係
- 敷地と道路の間に以下の条件のいずれかを満たすものが存在し、幅員2メートル以上の通行上支障がない措置が講じられていること。
- 管理者の占用許可、承諾、または同意が得られた水路
- 地方公共団体が管理する認定外道路等の公有地
- 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地
- 隣地境界線から建築物の部分までの水平距離が50センチメートル以上であること
基準2: 地方公共団体の管理通路
- 地方公共団体の管理通路で幅員4メートル以上の道が確保されており、道の延長が35メートル以下であること。
- 平成11年5月1日以降の敷地分割がされていないこと
- 建築物の延べ面積が200平方メートル以下であること
- 隣地境界線から建築物の部分までの水平距離が50センチメートル以上であること
基準3: 幅員2.7メートル以上の道
- 幅員2.7メートル以上の道が確保されており、道の延長が35メートル以下であること。
- 平成11年5月1日以降の敷地分割がされていないこと
- 道の中心から水平距離2メートルの線又は一方後退等により幅員4メートル以上となる線を道の境界線とし、全員の承諾が得られたものであること
- 建築物の基準(階数、規模、高さ、防火指定など)が法によるほか、特定の条件を満たすこと
基準4: 幅員1.8メートル以上2メートル未満の路地状の敷地
- 道路に幅員1.8メートル以上2メートル未満で長さ20メートル以下の路地状で接続する敷地で、以下の条件を満たすこと。
- 平成11年5月1日以降の敷地分割がされていないこと
- 建築物の出入口まで有効幅員1.8メートル以上の通路を確保すること
- 建築物の階数及び規模が地上2階(地階無し)まで、延べ面積が200平方メートル以下であること
- 最高の高さは8メートル以下、軒の高さは7メートル以下であること
- 建蔽率、容積率の算定に用いる敷地面積は路地状部分を除外すること
- 準耐火建築物または耐火建築物であること
- 隣地境界線から建築物の部分までの水平距離が1メートル以上であること
これらの基準は、例外的な状況下での建築許可に関する一括審査基準を定めたもので、世田谷区における建築計画の手続きを簡素化することを目的としています。
43条2項2号の許可・個別提案基準
建築基準法第43条第2項第2号の許可には、一括許可基準(包括同意基準)とは別に「個別提案基準」というアプローチが存在します。この個別提案基準は、自治体によって名称は異なりますが、包括同意基準に当てはまらない特定の案件に適用される手法です。
建築許可の難易度は高め、担保評価の難易度は比較的低いとされています。
一括許可基準(包括同意基準)は事前に建築審査会の同意を得ているため、市長や県知事などの許可後に建築審査会に報告するだけで済みます。これに対し、個別提案基準では、各案件ごとに建築審査会の同意を得る必要があります。これは、審査会が月に1回程度しか開催されないため、プロセスが時間を要し、また、必ずしも同意が得られるとは限りません。
多くの自治体では、この個別提案基準は設けられていないことが一般的です。包括同意基準に比べると、個別提案基準はより複雑で時間がかかるプロセスとなるため、再建築不可物件の救済策として利用する際には、これらの点を考慮する必要があります。
全国の43条2項2号、個別提案基準
全国の建築基準法第43条第2項第2号に関する個別提案基準は、包括同意基準に該当しない再建築案件に適用される、定型的な許可基準です。この個別提案基準を設けている自治体は多くありませんが、存在する場合、再建築不可物件に再建築の可能性を与える重要な役割を果たします。
個別提案基準では、各案件を個別に建築審査会に提案し、その同意を得てから許可が下りる仕組みになっています。ただし、個別提案基準が設定されている自治体であっても、その基準に合致しない物件の場合、再建築が許可される可能性は極めて低くなります。
以下は、全国のいくつかの自治体における個別提案基準の例です:
- 横浜市:専用通路部分の最低間口が0.9メートル以上、2階以下、通路部分が15メートル以下、終端に2メートル四方の空地などの条件。
- 兵庫県:専用通路部分の最低間口が0.6メートル以上、2階以下、通路2か所が道路に接道し合計2メートルなどの条件。
- 大阪府:専用通路部分の最低間口が1.5メートル以上、2階以下、通路部分が35メートル以下などの条件。
これらの基準によって、全国の自治体が再建築不可物件に対してどの程度柔軟な対応をしているかが明確になります。再建築を検討している場合、個別提案基準が存在するかどうか、そしてその詳細を確認することが非常に重要です。
43条2項2号の許可、個別審査
建築基準法第43条第2項第2号に関連する個別審査基準は、包括同意基準に当てはまらない特殊な再建築案件に対応するためのものです。建築許可の難易度は非常に高く、しかし、担保評価の難易度は低いです。
個別提案基準を設けている自治体では、物件がその基準に合致しない場合、建築審査会への提案自体が困難になります。一方で、個別提案基準が設けられていない自治体では、包括同意基準に該当しなくても、個別審査を通じて例外的に再建築が許可される可能性がわずかながら存在します。
また、建築審査会では、間口2メートルのない物件の建て替え(法43条)だけでなく、用途地域による建物の制限の緩和(法48条)、低層住居専用地域の高さ制限の緩和(法55条)など、幅広い事項について審査しています。
これらの点から、包括同意基準や個別提案基準に当てはまらない場合、再建築が非常に難しいという現実を理解する必要があります。個別の審査は多岐にわたるため、特殊な案件に対する審査は複雑であり、再建築不可物件の救済が容易でないことが多いのです。
43条但書き道路(43条2項2号許可)で想定される4つのトラブル
43条但書き道路(43条2項2号許可)に関わる物件には、以下のような4つの主要なトラブルが存在します。
- 建て替えの不確実性:国の基準を満たしていても、建て替えが必ずしも可能になるわけではありません。
- 共有者の合意の必要性:敷地が接する道路を複数の共有者が所有している場合、全員の合意がなければ、申請が困難です。
- 住宅ローン審査の厳しさ:この種の物件を購入する際、住宅ローンの審査が通りにくくなる傾向があります。
- 低い売却価格:通常の物件に比べて、安価に設定しなければ売却が難しい場合が多いです。
これらのトラブルに巻き込まれるリスクを減らすためには、43条但書き道路(43条2項2号許可)に関する認可が必要な物件の売却や、認可を得るための申請(43条但書き申請)を検討する際は、事前にしっかりとした確認が必要です。
建て替えの不確実性
お持ちの不動産が国土交通省の基準を満たしていても、必ずしも100%建て替えが可能とは限りません。特に、不動産が接する道路の幅が4メートル未満の場合、建築審査会の同意が必要となります。この同意が得られない場合、再建築は認められない可能性があります。
この点を踏まえ、建築審査会の同意を得ずに不動産を売却すると、将来的に再建築が不可能であることが判明した場合、買主からのクレームやトラブルの原因となる恐れがあります。また、建築審査会の同意が得られていないことを買主に伝えていなければ、契約不適合責任に問われ、契約解除や損害賠償請求のリスクが生じます。
契約不適合責任とは、売却後に契約書に記載のない不具合が発生した際、売主が買主に対して負う責任のことを指します。
そのため、但書き申請(43条2項2号許可申請)が必要で再建築が困難な不動産を売却する場合は、事前に建築審査会の同意を得て、「再建築可能な物件」として売却活動を行うことが重要です。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
共有者の合意の必要性
多くの土地では、現状の道路が複数の所有者によって共有されていることがあります。このようなケースでは、但書き申請(43条2項2号許可申請)を行う際、共有者全員の合意が必要になることがあります。例えば、横浜市では、道の権利者(共有者)全員の同意が得られなければ申請を進めることができません。
このため、共有者との関係が良好でない場合、同意を得るのが難しくなり、結果的に申請が行えない状況に陥ることがあります。そして、申請が行えなければ、物件の再建築が不可能になってしまう可能性があります。
したがって、共有者同士の関係が良好でない場合や、合意を得ることが難しいと判断される場合には、現状のまま不動産を専門の買取業者に売却する選択肢も検討することが賢明です。これにより、将来的なトラブルや不利益を避けることができます。
住宅ローン審査の厳しさ
再建築を可能にするための43条但書き申請(43条2項2号申請)が必要な物件の場合、購入時の住宅ローン審査が厳しくなる傾向があります。この理由は、但書き申請が必要な物件が実際に再建築可能であるかに不確実性があるため、金融機関が担保評価額を低く見積もることにあります。
担保とは、債務者が債務を果たさない場合に、債権者の損害を補うために設けられたものです。具体的には、不動産や車などが担保となります。担保評価額とは、住宅ローンなどの融資に際して、不動産を担保として設定する際の評価金額を指します。
担保となる不動産の評価額が低い場合、金融機関は買主の年収や借入時の年齢など、他の審査項目をより厳しく評価します。その結果、43条但書き申請が必要な物件は、購入時に住宅ローンの承認を得ることが難しくなり、結果としてこれらの物件の売却が一般の買手に対して困難になることがあります。
低い売却価格
43条但書き申請(43条2項2号許可申請)が必要な物件は、再建築のための特別な手続きが必要であるため、様々なトラブルが発生するリスクが高まります。このため、これらの物件は通常の物件に比べて売却価格が低く設定される傾向にあります。多くの購入者は、リスクを伴う物件の購入を避ける傾向にあるためです。また、売却価格を下げても、必ずしも速やかに売れるとは限りません。
このような状況において、43条但書き申請を行わないと建て替えができない物件を迅速かつ適正な価格で売却したい場合は、専門知識を持つ不動産買取業者に相談することを推奨します。専門の買取業者は、このような特殊な状況の物件に対して適切な評価を行い、適正な価格での売却をサポートしてくれるため、より良い売却結果を期待できます。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)
とは?再建築不可物件の救済措置!.png)