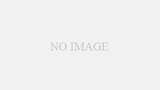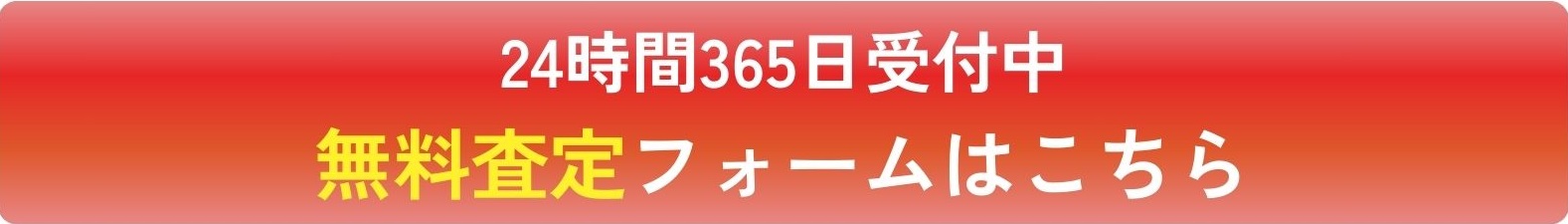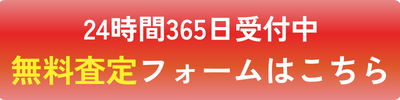市街化調整区域内での建築は一見難しそうですが、知られざる裏技を使えば土地活用が可能です。本ガイドでは、市街化調整区域の基本的な定義から、開発許可の取得方法、さまざまな建築手法(宅地利用、住宅兼用店舗、分家住宅など)について詳しく解説します。また、土地購入時の注意点や建築する際の利点と短所、さらには建築が難しい場合の裏技的な土地活用法も紹介していきます。
市街化調整区域の定義
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき定められた「市街化を抑制すべき区域」を指します。この制度は、都市部の乱開発を防ぐことを主な目的としています。特に、政令指定都市や県庁所在地、中核市などの大きな自治体で見られるこの区域は、戦後の高度成長期に住宅地の乱開発が問題となった背景を持ちます。当時、人口増加が著しい都市近郊では、農業が盛んであり、乱開発により貴重な農地が失われる危険性がありました。このため、開発を規制し、農村地帯を守るために市街化調整区域が設けられました。
都市計画法により、市街化の進展が懸念される地域を市街化区域と市街化調整区域の二つに分類しました。この分類は多くの自治体で昭和40年代に行われました。市街化区域は、「既に市街化が進んでいる区域、または今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進めるべき区域」と定義され、市街化を促進する地域です。これに対して市街化調整区域は建築に制限があり、その結果、宅地の乱開発が抑えられ、農業地帯が守られました。
しかし、市街化調整区域制度は50年近く経過しており、時代の変化に伴い問題点も生じています。現代では就農者が減少し、制度の設計当初とは異なる状況になっているため、市街化調整区域内の不動産所有者の間で新たな悩みが増えています。
建築に必要な開発許可と条件とは
市街化調整区域で建物を建てる際には、原則として開発許可が必要です。開発許可とは、行政からの特別な許可であり、通常は土地の開発行為に対して必要とされるものです。開発行為には「区画の変更」、「形状の変更」、「形質の変更」の三種類が含まれます。
「区画の変更」は、例えば敷地内に新しい道路を設置する行為を指します。「形状の変更」は、一定の高さを超える盛り土や切り土などを意味し、「形質の変更」は非宅地(例:雑種地、原野、山林)を宅地に変更することです。宅地とは、建物を建てるための土地のことを指します。
市街化調整区域では、土地の規模に関わらず、これらの開発行為を行う場合は開発許可が必要です。たとえば、未開発の土地に建物を建てることは、非宅地を宅地に変更する「形質の変更」に該当し、この場合も開発許可が必須となります。しかし、許可に必要な要件を満たしていれば、市街化調整区域内であっても建物の建設は可能です。
ただし、許可要件を満たさない場合、開発許可は下りず、その結果、建物を建てることができなくなります。市街化調整区域での建物建設には、これらの法的要件を理解し、遵守することが不可欠です。
市街化調整区域で家を建てるには
宅地利用が認められた土地の場合で一定の建物を建てる(34条)
市街化調整区域において、宅地利用が認められている土地では、一定の条件を満たした建物を建てることが可能です。具体的には、既に建物が存在する土地では「宅地以外の土地」を「宅地」に変更するための開発許可は不要です。しかし、このような土地であっても、どのような建物でも建てられるわけではありません。
都市計画法第34条に基づき、許可される建物の種類は限られています。これには「住宅兼用店舗」、「分家住宅」、「既存住宅の建て替え」が含まれます。
「住宅兼用店舗」は、住居と店舗が一体化した建物で、日常生活に必要な商品の販売、加工、修理などを行う自営の店舗が対象です。
「分家住宅」とは、農業を営む家族から独立した分家が建てる住宅を指し、これも市街化調整区域内で許可される建築物の一つです。
また、既存の住宅がある土地では、同じ規模・用途の建物への建て替えが可能です。これは、建て替えが乱開発に繋がらない限りにおいて許可されます。
ただし、これらの建築を行うには、宅地利用が認められているとしても、市街化調整区域内での建築許可(都市計画法第43条に基づく許可)の取得が必要です。この点は、市街化調整区域での建築活動を検討する際に重要な要素となります。
住宅兼用店舗
市街化調整区域内で建築可能な特定の建物の一例として「住宅兼店舗」があります。住宅兼店舗は、住居と商業スペースが一体となった建物で、個人商店において特に一般的な形態です。このタイプの建物では、例えば1階部分を店舗スペースとして、2階を居住スペースとして利用する構造がよく見られます。
建築可能な店舗としては、自営業の形態で日用品の販売や修理サービスを行うような店舗が該当します。重要な点として、店舗面積は建物の延床面積の少なくとも半分以上である必要があります。この面積に関する具体的な基準は、自治体によって異なることがありますので、計画を進める際にはその地域の規定を確認することが重要です。
住宅兼店舗は、市街化調整区域内での建築が認められる特殊なケースの一つであり、住宅と商業の両方の機能を併せ持つことから、特定の条件下での建設が可能となっています。
分家住宅
市街化調整区域内で宅地利用が認められた土地上に建てることが可能な特定の建物の一例として、「分家住宅」があります。分家住宅とは、農業を営む家族の中から本家から分家した新たな世帯が住むために建てる住宅を指します。これには子供や孫、兄弟などの家族が含まれます。
分家住宅の建設にはいくつかの条件があります。まず、建築主は本家の3親等以内の血族である必要があります。次に、建築主自身に他の持ち家がないことが求められます。さらに、本家の跡取りが明確である必要があります。
これらの条件を満たすことで、市街化調整区域内での分家住宅の建築が許可されます。これは、農業を営む家族にとって、土地の有効活用や世代間の住宅問題を解決する上で重要な選択肢の一つとなっています。
既存住宅の建て替え
市街化調整区域内で宅地利用が認められた土地において、既存の住宅を建て替える方法があります。この場合、既に市街化調整区域の指定がなされる前、つまり線引きの日よりも以前に建てられた住宅に該当する場合、宅地に変更するための特別な許可は必要ではありません。
既存住宅の建て替えにおいては、原則として現在の敷地で同じ規模および同じ用途の建物に限り建て替えや増築が可能です。これにより、市街化調整区域内でも既存の住宅を現代のニーズや様式に合わせて更新することが許可されています。
この規定は、市街化調整区域内における住宅の維持や改善に役立ち、住民が長年にわたりその土地で生活を続けることを支援するものです。ただし、建築計画を進める際には、該当する自治体の規則や指導を遵守する必要があります。
立地基準を満たした土地(都市計画法第34条11号)
市街化調整区域内で家を建てることは、特定の条件を満たした場合に可能です。特に、都市計画法第34条11号に定められた立地基準を満たす土地上では、家を建設する可能性が高まります。
都市計画法第34条11号は、市街化区域と市街化調整区域の境界近くなど、一定の条件を満たす土地に関する規定です。この規定に基づくと、市街化区域に近接し、一定の要件を満たす土地では、建築制限が緩和されることがあります。
このため、市街化調整区域に位置しながらも、市街化区域との境界付近など、法34条11号の条件を満たしている土地では、家を建てることが許可されるケースが存在します。これは市街化調整区域内での住宅建設において重要な選択肢の一つとなっています。
ただし、具体的にどの土地がこの条件を満たすかは、地域の都市計画や該当地域の具体的な条件によって異なるため、個々のケースについては専門家の意見や自治体の指導を受けることが推奨されます。
ディベロッパーが既に開発許可を得た土地の利用
市街化調整区域内でも、ディベロッパーによって開発された分譲住宅地が存在する場合、そこでは家を建てることが可能です。これらの分譲地は、ディベロッパーがあらかじめ開発許可を取得しているため、土地を購入した一般の個人も通常の方法で家を建設することができます。
ディベロッパーによる大規模な開発が行われた住宅地は、外観上、市街化区域内の住宅地とほぼ区別がつかないほど整備されています。ただし、建築可能な建物には一定の要件があり、例えば低層の戸建て住宅に限られることが一般的です。これらの要件の範囲内であれば、個人は自由に家を建てることが可能です。
市街化調整区域内の分譲住宅地は、開発許可がすでに取得されているため、個人が追加の許可を取得する必要はありません。このようにディベロッパーが開発した住宅地は、市街化調整区域内で家を建てる際の便利な選択肢の一つとなっています。
農業者は許可が不要
市街化調整区域内で家を建てる際の一つの方法は、開発許可が不要な特定の建築物を建てることです。このケースで注目すべき例は、「農林漁業を営む者の居住用建築物」の建設です。市街化調整区域において、農林漁業を営む者は、居住用の建築物を建てる際に開発許可を必要としません。つまり、農家や漁師など、農林漁業に従事している人々は、市街化調整区域内でも比較的容易に自宅を建設することが可能です。
この規定は、市街化調整区域内での過剰な開発を防ぎつつ、地域特有の産業と生活様式を維持するためのものです。そのため、農林漁業に携わる者が自宅を建てる場合、他の開発行為に比べて手続きが簡略化されることが一つの特徴です。
市街化調整区域で建物を建てるために必要な開発許可とは
都市計画法第34条の開発許可の基準について
市街化調整区域に家を建てるための開発許可は、都市計画法第34条に基づく基準に従って決定されます。ここでは、都市計画法第34条第11号および第12号の基準に焦点を当てて説明します。
都市計画法第34条第11号の内容
都市計画法第34条第11号によれば、市街化区域に隣接もしくは近接し、自然的および社会的な条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域では、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で指定された土地内での開発行為が許可されます。重要な点は、予定される建築物等の用途が、開発区域およびその周辺の環境保全上支障がないものとして条例で定められていることです。
この第34条第11号は、市街化調整区域内の既存集落に関する規定として知られており、おおむね50戸以上の建築物が連続して存在する地域を対象としています。これは市街化地域と日常的な生活圏が一体化している地域において、自治体の条例に適合する用途の建築物を建てることを可能にします。
市街化調整区域で家を建てる計画がある場合、このような規定に従う必要があるため、関連する自治体の条例を確認することが重要です。これにより、市街化調整区域内での住宅建設における法的要件と可能性を理解することができます。
都市計画法第34条第12号の内容
市街化調整区域内で建物を建てるために必要な開発許可に関する都市計画法第34条第12号の基準について説明します。この条項では、市街化区域の周辺における市街化を促進する恐れがない、かつ、市街化区域内での実施が困難または明らかに不適当と認められる開発行為について規定しています。これは、災害防止やその他の特別な事情を考慮し、政令に基づいて都道府県の条例で区域、目的、または予定建築物等の用途を限定して定めるものです。
この規定に基づく一例として、市街化調整区域内で長期的に居住する人の親族用住宅の建築が挙げられます。これは、親族が近距離に居住することが適切と判断された場合などに該当します。
都市計画法第34条第12号に従うと、自治体が定めた特定の区域および用途に限定された建築物のみが許可されます。このため、市街化調整区域での建築計画を進める際には、関連する自治体の条例を確認し、そのガイドラインに従うことが重要です。これにより、市街化調整区域内での建築に関する法的な要件と制約を理解し、適切な計画を立てることができます。
許可申請の方法について
市街化調整区域内で建物を建てるためには、都市計画法第43条に基づいて、都道府県知事からの許可が必要です。原則として、市街化調整区域では住宅の建築は認められていませんが、特定の条件下では許可を得て建築することが可能です。
市街化区域から1キロメートル以内に位置する場合や、市街化区域まで4メートル以上の道路が接続している場合などがその条件に当たります。こうした状況下であれば、許可申請を通じて建築が許可される可能性があります。重要なのは、申請する土地に大規模な造成工事が行われていないことです。
ただし、既に住居を所有している人はこの申請を行うことができません。許可を申請する際には、該当する自治体に対して申請を行い、個別に審査を受ける必要があります。これにより、市街化調整区域内での建築計画が実現可能かどうかが決定されます。
次の項では、具体的な許可申請の手続きについて詳しく解説する予定です。これにより、市街化調整区域で家を建てる際の法的プロセスについての理解が深まります。
市街化調整区域で建築物を建てる場合の手続きの流れ
自治体へ事前相談及び事前協議
市街化調整区域で建築物を建てる際の手続きには、自治体への事前相談及び事前協議が不可欠です。このプロセスを開始するには、まず自治体に提出する事前相談書の作成が必要です。事前相談書の作成にあたっては、必要な書類を集めるために自治体の担当部署や不動産会社との連携が重要です。
事前相談書に添付する必要がある書類は以下の通りです:
- 建築相談票:建築計画の概要を記載した書類。
- 提案基準第4号(分家住宅)事前相談票:分家住宅に関する具体的な計画を説明する書類。
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物に関する申告書:農業従事者の住宅建築に関する詳細を記載した書類。
- 農産物の直売所の用に供する建築物に関する申告書:農産物直売所の建築計画に関する情報を記載した書類。
- 貨物自動車運送事業の特別積み合せ貨物に供する建築行為等についての立地申出書:特定の運送事業に関連する建築計画についての書類。
これらの書類は、建築計画の内容や性質に応じて変わる可能性があります。したがって、事前に自治体の指導を受け、必要な書類を正確に準備することが重要です。これにより、市街化調整区域での建築プロジェクトがスムーズに進むことが期待されます。
自治体からの回答とそれに対する対応
市街化調整区域で家を建てる際には、提出された事前相談書に基づき自治体が建築計画を確認し、その内容に応じて建築の可否と許可の要否を判定します。この判定結果により、今後の手続きが異なります。
許可が不要と判定された場合、次のステップは建築確認申請に進むことです。建築確認は、計画された建物や地盤が建築基準法に準拠しているかどうかを確認するプロセスです。ここでは、建ぺい率や容積率の遵守、シックハウス対策、十分な採光の確保などがチェックされます。2020年以降は、省エネ基準の遵守も確認項目に含まれるようになりました。
一方、許可が必要と判定される場合は、都市計画法第34条に該当する建築物と見なされ、開発許可申請または建築許可申請が必要になります。これは、市街化調整区域内での建築に関してより厳格な審査が必要であることを意味します。
開発許可申請
開発許可申請は、都市計画法第29条に基づくもので、土地を掘り起こし整備するなどの開発行為が計画されている場合に必要となります。この申請に先立ち、自治体の関連部署による事前協議が行われます。この協議では、申請内容に対する審査や協議が実施され、開発計画の妥当性が評価されます。もし開発許可が不要な場合は、直接建築許可申請に進むことができます。
建築許可申請
建築許可申請は、都市計画法第43条に基づくもので、開発行為が伴わない場合に適用されます。すなわち、開発許可を受けて開発行為が完了した後、または開発許可が必要ない場合に、建築物の建設に関してこの許可を申請することになります。
また、計画内容によっては開発審査会が設置されることもあり、この場合は審査会の議決を経て申請手続きが進むことになります。
市街化調整区域内の土地を購入する際の注意点
地目の確認をする
市街化調整区域の土地を購入する際、特に重要なのは土地の地目の確認です。地目とは、土地の現状や使用目的に応じて分類される名称で、不動産登記法に基づき土地の登記事項証明書に記載されています。現在、日本では全部で23種類の地目が存在します。
土地の売主と買主は、取引する土地の地目を正確に理解し確認する必要があります。これは、土地の利用目的や制限を理解する上で重要な情報となります。特に、土地の地目が農地の場合、農地転用の許可が必要になるため、特に注意が必要です。
市街化調整区域内で土地を購入する際は、このような地目に関する情報を正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。土地の使用目的や制限を正確に理解することで、土地購入後のトラブルを避けることができます。
特約を設定することを忘れずに
市街化調整区域の土地を購入する際、特約の設定に注目することが重要です。土地が建築に適していることが明らかであっても、不測の事態に備えて売買契約に特約を含めることを推奨します。
特約の一例としては、「特定の期日までに建築許可を取得できない場合に契約を解除する」という内容が挙げられます。このような特約は、もし建築許可が予定通りに下りなかった場合に買主を保護する役割を果たします。
市街化調整区域の物件を扱う仲介会社を利用することも有効です。専門的な仲介会社は、特約に関する適切なアドバイスを提供し、取引の安全性を高めることができます。このような専門的なアドバイスを受けることで、市街化調整区域内の土地購入におけるリスクを減らし、スムーズな取引を実現することが可能になります。
法改正が将来される可能性を考慮する
市街化調整区域での土地購入時、将来的な法改正の可能性を考慮することは非常に重要です。現在開発許可が得られているとしても、法律が変わることでその状況が変化する可能性があります。たとえば、2022年4月1日の都市計画法の一部改正により、市街化調整区域内で災害リスクが高いと判断されるエリアでの開発行為は原則として認められなくなりました。
このような法改正の背景には、降水量の増加や海面上昇による水害など、気候変動に関連する環境問題が影響しています。このため、将来的にも同様の理由で法律が変更される可能性があるため、土地購入時には長期的な視点で慎重に検討することが求められます。
このように、市街化調整区域で土地を購入する際には、現在の法律だけでなく、将来の法改正による影響も念頭に置く必要があります。これにより、長期的な安全性と資産価値の両方を確保することが可能になります。
市街化調整区域に建築する利点
土地価格の安さ
市街化調整区域の土地は、都市計画地区や市街化区域に比べて価格が低いことが大きな魅力です。この低価格の理由は、開発制限により市場における需要が限られるためです。しかし、開発許可の取得条件を満たし、適切な手続きを行うことで、これらの土地を有効に活用する機会が広がります。結果として、広大な土地を低価格で手に入れるチャンスが生まれるのです。
加えて、市街化調整区域の土地は、自然環境に恵まれた静かな地域が多いため、穏やかな生活空間を提供します。開発許可を得た場合、個人的な使用にとどまらず、賃貸物件としての利用も可能になります。これにより、市街化調整区域の土地は、安価な価格で最大限の価値を引き出す手段として魅力があります。
固定資産税の軽減と都市計画税の非課税
市街化調整区域で建築する際には、税制上の優遇措置として固定資産税の軽減と都市計画税の非課税があります。これらの措置を利用するためには、開発許可を取得し、特定の条件を満たす必要があります。市街化調整区域内では土地や建物の評価額が一般的に低く設定されるため、固定資産税もそれに応じて低くなります。
また、都市計画税は通常、都市の発展に対する負担として課税されますが、市街化調整区域は都市計画の主要な対象外であるため、この税金が課されないこともメリットの一つです。このような税制上の優遇措置は、土地の購入や建築にかかるコストを抑えるうえで大きな利点となります。市街化調整区域での開発許可取得に向けた適切な手続きを行うことで、これらの優遇を最大限に活用できます。
静かな環境での生活
市街化調整区域での生活は、静かな環境を求める人々にとって理想的な選択肢となり得ます。開発が厳しく制限されているこの地域では、都市部の騒音や混雑がほとんどなく、豊かな自然に囲まれた穏やかな日々を送ることができます。四季折々の風景が日常生活を彩り、子育て世代にとっては子どもたちの健全な成長に良い環境を提供し、高齢者にとっては心地よい老後を過ごすのに適しています。
ただし、市街化調整区域での生活には、都市部と比較していくつかの欠点もあります。特に生活インフラや公共交通のアクセスが限られていることが挙げられます。そのため、この地域での生活を検討する際には、必要な施設やサービスが利用可能かどうかを事前に確認し、適切な開発許可の申請が必要です。これらの点を十分に考慮した上で、市街化調整区域での生活の可能性を検討することが重要です。
市街化調整区域に建築する場合のデメリット
改築・建て替えの許可要件
市街化調整区域での建築には明確なデメリットがあります。この地域内での新築や建て替えは都市計画法第34条の規定に基づいた厳格な制限があり、特定の条件を満たす地域でのみ可能です。市街化調整区域を購入したものの、これらの制限を事前に確認せずに進めた場合、計画された住宅建設や投資が不可能になるリスクがあります。
このようなリスクを避けるため、市街化調整区域内の土地を購入する前には、必ず自治体で事前確認を行う必要があります。自治体によっては判断基準に差異があるため、その地域の具体的な規制や条件を把握しておくことが重要です。このように、市街化調整区域での土地購入や建築計画を進める際には、法的な制限や条件を十分に理解し、適切な準備を行うことが求められます。
インフラの不足
市街化調整区域での開発には、特定の条件を満たし許可を得ることが求められます。その中で、インフラの不足は大きな課題となります。都市部と比較してライフラインが整備されていない地域が多く、水道、電気、ガスの供給が不足することがあります。例えば、都市ガスが利用できない地域では、プロパンガスの利用など自己対策が必要となります。下水道が整備されていない地域では、浄化槽を設置するなどの対策が求められます。また、電力供給も不安定な地域があり、停電のリスクを常に考慮する必要があります。これらの問題は、開発許可を取得するためにも、そして快適な生活を送るためにも、事前に十分な配慮と申請が必要です。特に、インフラの不足は緊急時の安全対策にも影響を及ぼすため、許可を得る際にはその点も考慮する必要があります。
商業施設の遠さ
市街化調整区域での生活におけるデメリットの一つとして、商業施設へのアクセスの遠さが挙げられます。都市部に比べて、市街化調整区域では商業施設が少ないことが多く、買い物や日常のサービス利用において不便を感じることがあります。特に、飲食店やエンターテイメント施設が限られている地域では、多様なライフスタイルを望む住民にとっては大きな欠点となることがあります。
しかし、市街化調整区域内での生活に関しては、地域によって状況が異なります。そのため、建築許可を得る前に、その地域の商業施設の状況やアクセスの利便性について十分に調査し、自分の生活スタイルに合った地域を選択することが重要です。また、オンラインショッピングの普及により、一部の商業施設の遠さによる不便さは緩和されていることも考慮する価値があります。このように、市街化調整区域での生活を検討する際には、地域の商業施設の状況を含めた総合的なリサーチが必要です。
売却の難しさ
市街化調整区域に存在する物件の売却は、通常の物件と比べて困難な側面があります。これは市街化調整区域の特性と、物件の価値を評価する購入者の視点に起因しています。市街化調整区域は、建築に対する制約が厳しく、開発許可を得るためには知事からの許可が必要であり、そのためには一定の条件を満たす必要があります。これにより、開発が制限され、周囲の生活環境や便益の向上が難しくなります。したがって、市街化調整区域の物件は、一般的な住宅地と比較して魅力が低くなりがちであり、これが売却の難しさにつながります。さらに、市街化調整区域の土地は、建設後も開発許可の変更や取り消しのリスクを孕んでいます。これは購入者にとって不確定要素となり、売却を難しくする要因となります。従って、市街化調整区域での建築には、事前の計画と、将来の売却を見越した戦略が必要となります。
住宅ローン審査の厳格さ
市街化調整区域における建築の計画は、一定の条件を満たすことで許可が必要となります。その中でも、住宅ローンの審査は特に厳しいものとなります。通常の審査よりも一層、厳格な審査が行われ、審査を通過することは容易ではありません。その主な理由は、市街化調整区域では開発許可が必要であり、土地利用が制約されるため、将来性が不確定と見なされるからです。 金融機関は、返済不能となった場合に債権を回収するための物件売却を前提としていますが、市街化調整区域の物件は売却が難しいとされています。ですから、市街化調整区域での生活を望む場合は、申請の必要な開発許可を取得するための自己資金の準備、保証人の確保、信頼性のある金融機関の選定など、住宅ローン審査を通過するための戦略が必要となります。
建物を建てることが難しい場合の市街化調整区域での裏技的活用法
ソーラーパネル設置による太陽光発電
市街化調整区域で家を建てるのが難しい場合、ソーラーパネル設置による太陽光発電は有効な土地活用方法です。都市計画法により、市街化調整区域では開発行為が原則制限されていますが、太陽光発電設備が建築基準法に定める「建築物」に該当しない場合、開発許可や建設確認の必要がありません。
国土交通省による2011年の通達では、土地に自立して設置され、架台下の空間に人が立ち入らない、かつ屋内的用途に供されない太陽光発電設備は建築物に該当しないとされています。このため、フィールド設置型の太陽光発電システムは基本的には建築物と見なされず、開発許可や建設確認を必要としません。
しかし、土地の造成行為(切土や盛土など)は土地の区画形質の変更に該当し、市街化調整区域では開発許可が必要です。したがって、太陽光発電設備を設置する際には、この点を考慮し、必要に応じて開発許可申請の手続きを行う必要があります。
駐車場の設置
市街化調整区域内で家を建てるのが難しい場合、駐車場として土地を活用する方法があります。市街化調整区域では建築制限があるものの、駐車場の設置は比較的容易です。ただし、この区域は郊外に位置することが多く、集客には工夫が必要です。
駐車場には、主に月極駐車場とコインパーキングの二つの形態があります。月極駐車場は、駐車スペースが不足している住宅や職場の近くで需要が見込めます。特に、自宅の敷地内に駐車スペースが確保できない場合の2台目、3台目の車の駐車場として便利です。
一方、コインパーキングは商業施設や駅の近くなど、人の往来が多い場所での需要が期待できます。市街化調整区域内で駐車場を設置する場合、地域の特性やターゲットとなる利用者を考慮した上で適切な土地選びが重要です。
ただし駐車場の利用としては固定資産税が高いというデメリットがあります。土地の上に建物を建てる場合には、土地の固定資産税は土地の利用が制限されることから、更地の場合の1/6になっています。一方で更地の駐車場においては、建物がある場合の6倍の固定資産税負担がかかることとなります。
墓地の設置
市街化調整区域で家を建てるのが難しい場合、土地を墓地や霊園として貸し出すのは一つの効果的な選択肢です。この区域の土地は比較的安価であることが多く、墓地や霊園の設置に適しています。特に、価格が高騰する傾向のない土地には墓地や霊園が適しており、業者にとってもメリットがある選択となり得ます。
墓地や霊園としての土地利用を考える場合、ある程度の広さが求められます。また、他の土地活用方法と比較して、墓地や霊園の場合はより高い賃料を期待できる可能性があります。
ただし、墓地や霊園として土地を貸し出す際には、長期間にわたって土地が返還されないことを理解しておく必要があります。一般的に、墓地や霊園は数十年単位で土地を利用するため、この点を考慮して土地の貸し出しを決定することが重要です。
資材置き場として利用する
市街化調整区域において家を建てるのが難しい場合、資材置き場として土地を活用するのは有効な方法の一つです。この方法の利点は、建物を建てる必要がなく、整地も不必要な場合があるため、市街化調整区域に適しています。場合によっては、資材置き場として土地を貸し出した際に、貸借契約の一環として貸主が簡易的な整地を行ってくれることもあります。
しかし、資材置き場の活用には立地条件による制限があります。市街化調整区域であればなおさら、周辺に資材置き場を必要としている企業や工事現場が存在するかどうかが重要です。そのため、土地を資材置き場として活用する際には、その地域の需要やアクセスの良さなど、立地条件を慎重に検討する必要があります。
家以外の建物を使った市街化調整区域の有効利用方法
サービス付き高齢者向け住宅施設を建てる
市街化調整区域での土地活用において、高齢者施設の建設は有効な方法の一つです。特別な許可を取得できれば、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの施設を建てることが可能です。市街化調整区域の土地は、周辺の住民の需要やニーズを考慮して、自治体が高齢者施設の建設を必要と判断すれば、建設許可が下りる可能性があります。
高齢者施設は、施設内に必要な設備が一通り揃っているため、郊外である市街化調整区域でも需要が落ちにくい利点があります。このような施設の建設は、市街化調整区域内の土地を社会的なニーズに応じて有効活用する方法として考慮されます。
特別養護老人ホーム等の公的施設を建てる
市街化調整区域での土地活用方法の一つとして、特別養護老人ホームなどの公的社会福祉施設の建設が考えられます。このような公的施設は、市街化調整区域内の土地でも、適切な事前協議と届け出を行うことで建築が可能です。これは、一般的に建築許可が下りにくい市街化調整区域でも、社会福祉施設の建設を検討している法人があれば、土地の賃貸収入を得るチャンスがあることを意味します。
一般的には、土地の持ち主が自ら建物を建て、その土地と建物を合わせて貸し出す方法が多く見られます。これには高額な初期投資が必要ですが、比較的高い利回りでの貸し出しが期待できます。
ただし、この方法にはリスクも伴います。事業者が数年以内に撤退や倒産をするリスクがあり、その場合、建物の他の用途への転用が難しくなる可能性がある点に注意が必要です。そのため、社会福祉施設としての建物建設を検討する際には、将来的なリスクも考慮に入れた上で計画を進めることが重要です。
医療施設を建てる
市街化調整区域内での土地活用として、医療施設の建設は有効な選択肢の一つです。医療施設は、公益上の必要性が認められる建物として、適切な事前協議と届け出を行うことで建築許可を得ることが可能です。このプロセスは、社会福祉施設の建設時と同様です。
市街化調整区域の土地に医療施設を建てる場合、その地域に医療施設のニーズがあるかどうかが重要です。医師や医療法人など、開業を希望する医療関係者が周辺地域に存在し、需要がある場合には、土地の活用が有望となります。一般的に、土地の持ち主が建物を建設して、その土地と建物を合わせて医療関係者に貸し出す方法が多く採られています。
医療施設の建設には初期投資が必要ですが、長期的に安定した収入を見込むことができる可能性があります。ただし、医療施設としての建物の建設と運用には、特定の規制や基準が適用されるため、これらを十分に理解し計画を立てる必要があります。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)