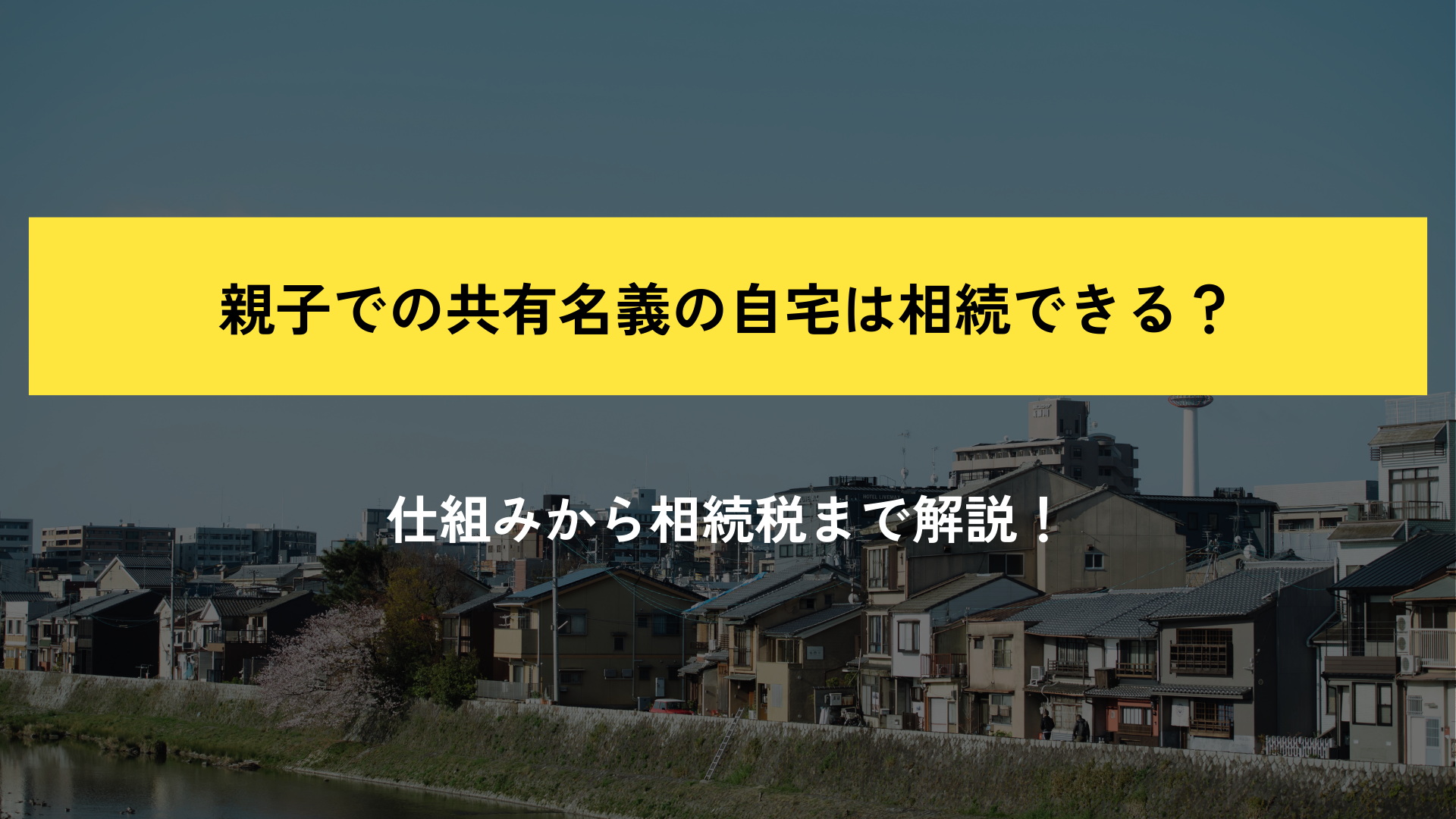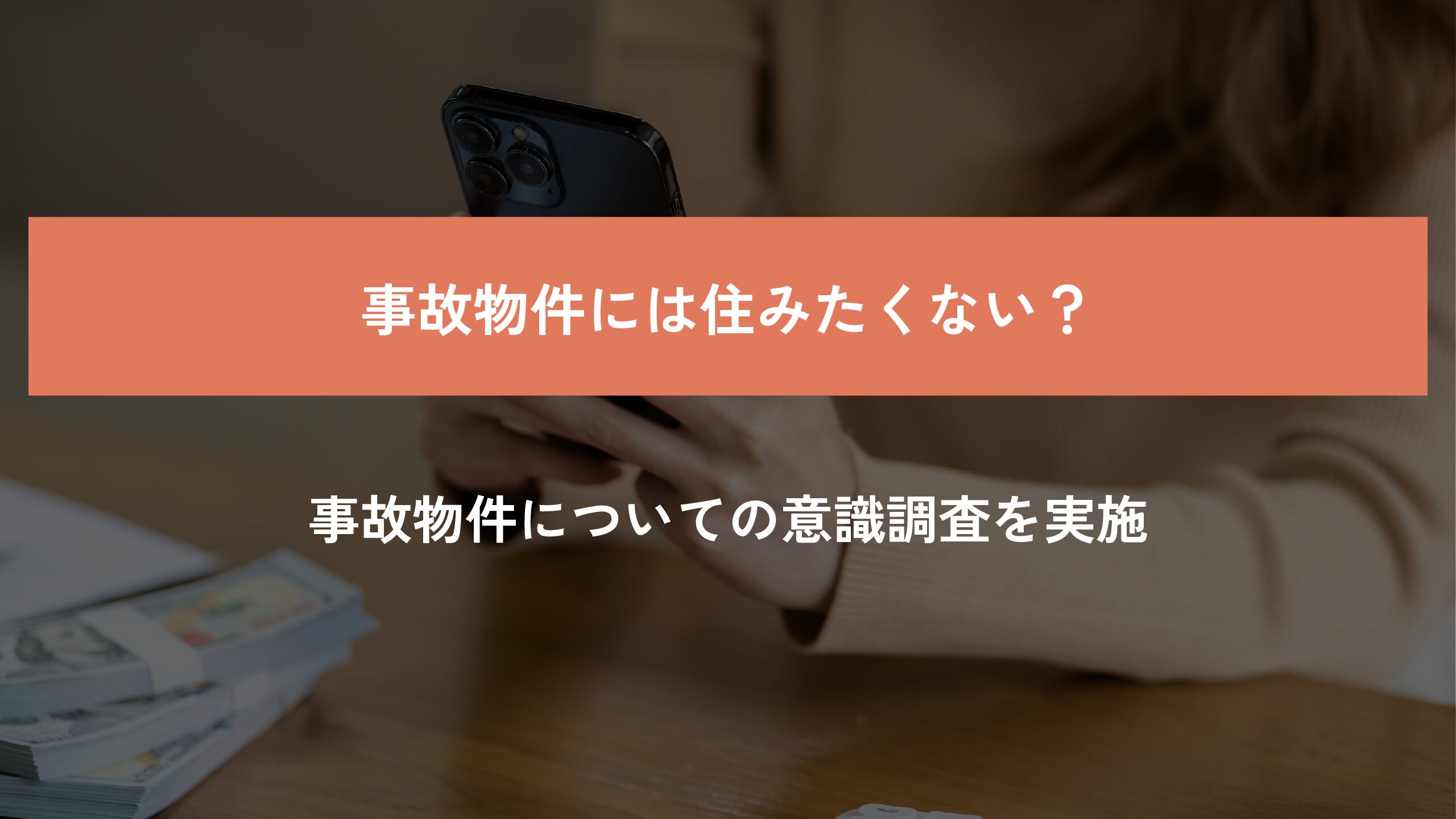親子間で共有名義の自宅を相続する際には、不動産の共有持分の扱いや相続税の計算方法が重要になります。この記事では、共有者が亡くなった場合の手続きや相続税軽減の方法、さらにはトラブルを避けるための生前対策まで、基本から応用までをわかりやすく解説します。親子共有名義の不動産を持つ方々にとって、相続発生時に知っておくべきポイントを網羅しています。
不動産の共有とは
不動産の共有とは、一つの不動産(土地や建物など)が複数の人によって所有されている状況を指します。この所有形態では、「持分」と呼ばれる割合で不動産が分割所有されます。例えば、父親と長男が共同で4000万円の二世帯住宅を購入し、双方が2000万円ずつ支払った場合、所有権は父親と長男それぞれに半分ずつ(1/2持分)帰属することになります。この方式により、不動産は共有名義として管理され、相続などの際にはこの持分に基づいた手続きが必要となります。
共有者が死亡した場合の共有持分の扱い
共有不動産の持分について、一般的に共有者の死亡に伴いその持分が自動的に他の共有者に移転すると誤解されがちですが、実際には死亡した共有者の持分は相続財産とみなされ、相続人によって相続されます。このため、例えば親子間で共有されている自宅の場合、親が亡くなった際には、子がその持分を相続することは可能ですが、自動的に移転するわけではありません。また、故人に他の相続人がいる場合(兄弟姉妹や配偶者など)、これらの相続人との間で遺産分割協議が必要になります。
共有持分のある不動産の相続発生時のデメリット
相続人間での遺産分割協議が円滑に進まない場合、兄弟間の不和の原因となったり、最悪の場合、法的な争いに発展するリスクもあります。特に、遺産分割協議を複雑にする要因として、連絡が取れない相続人、判断能力が乏しい相続人の存在が挙げられます。相続税の納付期限が相続発生から10ヶ月以内であることを考えると、相続に関するトラブルは時間的、精神的、財政的負担を増大させます。加えて、複数の名義人がいる不動産は、一人が亡くなった場合、不動産の今後の利用や売却にあたってもトラブルの発生が懸念されます。
もし共有不動産の持分を特定の共有者に確実に移転させたい場合は、遺言による指定が効果的です。遺言で自分の持分を特定の共有者に相続させる、または遺贈することを明記しておくことで、意図した相続が実現します。遺言の作成は、将来の不確実性を減らし、意図に沿った財産の移転を確実にするために重要です。
親子共有名義の不動産と相続税の仕組み
親子共有名義の不動産では「親の持分」にのみ相続税が課される
不動産を親子で共有名義で購入する場合、投資した資金の比率に応じて各自の「持分割合」が決定されます。たとえば、家族構成が「親と子の二人」で、この親子が共有名義で不動産を所有している状況を想定しましょう。親が亡くなった場合、相続対象となるのは親の持っていた不動産の持分に限られます。この方式により、もし不動産を一人で所有していた場合に比べ、相続税の負担を軽減することができます。親子で不動産を共有名義で購入することは、相続税の面で大きな利点となり得ます。親が不動産購入を検討しているなら、親子共有名義での購入を考えると良いでしょう。また、親子共有名義による不動産購入が原因で、親の持つ財産の総額が相続税の基礎控除額を下回る場合、相続税が免除される可能性もあります。
法定相続人の定義と相続の順位
法定相続人とは、民法によって相続権が認められている被相続人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などの血縁関係にある親族です。法定相続人には、相続における優先順位があり、これは民法で明確に定められています。
相続人の優先順位は以下の通りです:
- 第一順位は被相続人の子供です。子供が既に亡くなっている場合は、その子供(孫)が相続人となります。
- 第二順位には被相続人の父母が位置し、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
- 第三順位は被相続人の兄弟姉妹で、亡くなっている場合はその子供たちが相続人となります。
法定相続分、つまり相続人が受け取る遺産の割合は、以下のように定められています:
- 配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が1/2、子供が1/2の割合で相続します。子供が複数いる場合は、その1/2をさらに分割します。
- 配偶者と父母(または祖父母)が相続人の場合、配偶者が2/3、父母(または祖父母)が1/3の割合で相続します。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で相続します。
法定相続分と異なる分配を希望する場合は、法定相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議」が必要です。これにより、法定相続分に従わない特定の分配比率で遺産を分割することが可能になります。しかし、全員の合意がない場合、親の共有持分を子供が単独で相続することはできません。相続におけるこれらの規則を理解することは、相続トラブルを避けるために非常に重要です。
特別縁故者の相続権
法定相続人が一人も存在しない場合、被相続人と特別な関係にあった「特別縁故者」が遺産を相続することが可能です。特別縁故者とは、被相続人の生前に密接な関係を持っていた人々を指し、具体的な例としては、被相続人の内縁の配偶者、子の配偶者(義理の子)、または被相続人の療養看護に尽力した人などが挙げられます。
特別縁故者が遺産を相続するためには、家庭裁判所に「相続財産清算人の申立」を行い、法的手続きを通じて相続権を認めてもらう必要があります。この手続きにより、特別縁故者が正式に遺産を受け継ぐことができます。
特別縁故者の例
e-Gov法令検索「民法958条」
被相続人の「内縁の配偶者」
被相続人の「子供の配偶者(義理の子供)」
被相続人の療用看護に務めた人
共有者としての法定相続人
不動産を配偶者や親族間で共有名義にしているケースが多く、これにより共有者は通常、法定相続人となります。特に親子間での共有名義では、生前に共有していた子が、亡くなった親の遺産として法定相続人に該当します。
しかし、被相続人と血縁関係がない第三者が共有者である場合でも、被相続人の法定相続人や特別縁故者が存在しない状況では、その第三者が共有持分を相続することが認められています。これは民法第255条に基づくもので、被相続人の財産に対する権利と義務が、特定の条件下で他者に移転することを可能にしています。
第三者が共有持分を相続する際は、特別縁故者が相続財産清算人として申立を行う必要がある場合と同様に、家庭裁判所に「相続財産清算人の申立」を提出する必要があります。この手続きを通じて、遺産の管理や分割に関する公正な審理が行われ、共有持分の適切な相続が可能となります。
参照元:民法第255条
共有名義の不動産を持つ親が亡くなった際の相続税計算例
相続税の計算には、次の3ステップが必要です。
- 課税遺産総額の確定
- 法定相続分に基づいた相続税額の算出
- 実際の遺産取得割合に応じた相続税の按分
まず、全ての遺産(預貯金、不動産、株式等)の評価額を確認し、債務や葬儀費用など控除可能な費用を差し引きます。最終的に、基礎控除額(3,000万円+法定相続人数×600万円)を適用して、課税遺産総額を求めます。この額が基礎控除額を超えない場合、相続税は発生しません。
複数の相続人がいる場合、課税遺産を法定相続分で分割し、それぞれの相続税額を計算します。その後、これらの税額を合計し、実際の遺産取得割合に応じて相続人間で按分します。相続人が一人の場合は、法定相続分100%に基づき税額を計算します。
親子で共有名義の不動産があり、「親ひとり・子ひとり」の場合で不動産持分が50:50の場合を例に取ると、相続する遺産の総額は、共有不動産の評価額(5,000万円)とその他の遺産(2,000万円)を合わせ、親の持分に該当する部分を考慮して4,500万円となります。葬儀費用を控除後の課税遺産総額は4,350万円で、基礎控除後の課税遺産総額は750万円です。相続税率10%を適用すると、相続税は75万円になります。
この計算例から、親子での共有名義による不動産所有が、単独名義の場合と比較して相続税の節税につながることがわかります。共有名義ではなかった場合、相続税額は大幅に増加するため、節税対策として親子共有名義の検討が有効です。
不動産の共有者が亡くなった際の対応手順
不動産共有者の死亡時に取るべき手順
不動産共有者の死亡を受け、相続手続きを円滑に進めるためには、まず遺言書の存在とその内容を確認することが重要です。
公正証書遺言が作成されている場合は、その遺言書は法務局に保管されています。遺言書が存在するかどうかは、「遺言書保管事実証明書」を請求することにより確認できます。
一方で、自筆証書遺言の場合、保管場所(例えば金庫や書棚等)を探し出す必要がありますが、発見しても自己の判断で開封することはできません。自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所において検認手続きを行う必要があり、この手続きを経ずに開封した場合、遺言の内容が無効とされる可能性があるため注意が必要です。適切な手順を踏むことで、不動産の相続に関わる遺言書の内容を正しく把握し、後続の相続手続きに移行することができます。
遺言書がない場合の遺産分割協議の進め方
遺言書による指定がない場合、相続に関わる全ての相続人は遺産分割協議を行う必要があります。この協議は全相続人の一致した合意があって初めて成立するため、まずは法定相続人を特定し、相続財産を全て把握することが重要です。
法定相続人には、被相続人の配偶者、子供、親、兄弟姉妹などがおり、それぞれの相続権は民法で定められています。法定相続人を明確にするためには、戸籍謄本などを通じて家族関係を調査します。
次に、被相続人名義の財産(預貯金、不動産、自動車、株式等)を調査し、財産の総額を算出します。この段階では、金融機関の記録や法務局、市区町村役場から不動産の登記情報を収集することが必要です。
相続人および相続財産の調査が完了次第、遺産の分配についての協議を開始します。この協議では、財産の分配方法、共有不動産の扱い方など、さまざまな点について話し合い、全員の合意形成を目指します。
共有名義の不動産に関しては、相続人間で持分をどのように分け合うか、必要に応じて分割や代償支払いに関する合意を形成する必要があります。遺産分割が複雑な場合や合意形成に難しさがある場合は、弁護士への相談が推奨されます。
相続登記の重要性と手続き
遺産分割協議が無事に合意に至った後は、その決定に基づいて相続財産の正式な移転手続き、特に不動産に関する手続きを行います。このプロセスは「相続登記」と称され、故人の名義で登記されている共有不動産の持分を正式に相続人の名義に変更することを指します。
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が法的に義務化されます。この変更により、不動産を相続した場合、法定の期限内に相続登記を完了させなければならなくなります。この義務化は、不動産取引の透明性を高め、将来的な紛争を防ぐ目的があります。
相続登記を行うためには、遺産分割協議書、被相続人の死亡証明書、相続人の戸籍謄本など、必要な書類を準備し、法務局に提出する必要があります。手続きは複雑な場合が多いため、不明点がある場合は司法書士や弁護士に相談することが推奨されます。相続登記を適切に行うことで、不動産の正式な所有権の移転が確実になり、将来のトラブルを防ぐことができます。
親子共有名義の不動産に関する相続税軽減の方法
同居している家庭用宅地に「小規模宅地等の特例」適用可能性
不動産を相続する際に、対象不動産が「小規模宅地等の特例」の適用条件を満たす場合、土地の評価額を最大で80%減額することが可能です。この特例の適用は、宅地の利用目的に応じて異なり、上限面積や減額率もそれぞれ設定されています。相続が近づいている場合には、事前の確認が重要です。以下に、主な対象宅地のカテゴリーとその条件を示します。
- 特定事業用宅地等:上限面積400㎡、減額率80%(例:自営業の事務所)
- 特定同族会社事業用宅地等:上限面積400㎡、減額率80%(例:被相続人が経営する企業用土地)
- 貸付事業用宅地等:上限面積200㎡、減額率50%(例:賃貸マンションの土地)
- 特定居住用宅地等:上限面積330㎡、減額率80%(例:戸建て自宅の土地)
多くの場合、住宅用途や貸付用途の宅地がこの特例の適用を受けることが多いですが、注意点として、特例の適用は土地に限られ、建物本体には適用されません。特に分譲マンションの場合は、敷地権が減額の対象となります。この制度を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
子の名義で土地の持分を多くすることで相続税軽減が見込める
「小規模宅地等の特例」の適用外である広範囲の土地や建物を親子で共有名義で購入する場合、子の持分を多めに設定することで、将来的に相続税の節税が可能になるケースがあります。特に、土地の評価が高くなりがちなエリアでは、子の持分比率を高く設定しておくことが税負担の軽減につながります。しかし、このアプローチを取る際は、土地のみの所有では住宅ローン控除の恩恵を受けられない点を留意する必要があります。親子共有名義での不動産購入は予算の柔軟性を増しますが、住宅ローン控除を考慮に入れて、適切な持分割合を決定することが重要です。
相続トラブルを未然に防ぐための生前対策
複数の相続人がいる場合、共有名義の不動産は相続トラブルの温床になり得ます。このようなリスクを回避する一つの方法として、「生前贈与」が有効です。これは、所有者が生前に不動産の名義を子ども等の特定の相続人に変更することで、相続発生時の紛争を防ぎます。
生前贈与には、以下の2つの方法があり、それぞれ税負担を抑える効果が期待できます。
- 暦年課税による持分の贈与
- 相続時精算課税による持分の贈与
加えて、不動産や遺産の公平な分配を保証するために、生前に遺言書を作成しておくことも推奨されます。遺言書を通じて、所有者の意志が明確に反映され、相続人間の不公平感を減少させることが可能です。しかし、遺言書が法的効力を持たない場合もあり得るため、公正証書遺言の作成を検討することが賢明です。公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成され、その内容の正確性と法的有効性が保証されます。また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度もあり、これにより遺言書の紛失や偽造を防ぐことができます。適切な制度を選択し、専門家と相談しながら、生前対策を講じておくことが重要です。
暦年課税を利用した贈与の戦略
「暦年課税」とは、1年間に受け取った贈与総額が110万円以下の場合に贈与税が非課税となり、贈与税の申告が不要になる制度です。例えば、計画的に毎年110万円ずつ贈与することで、長期にわたり大きな資産を移転することが可能になります。この方法では、20年かけて合計2,200万円を贈与することができます。
ただし、贈与の実施にあたっては注意が必要です。一度に大きな金額を贈与すると、それが定期贈与と見なされ遡及して贈与税が課されるリスクがあります。また、あらかじめ特定額の贈与を行う契約を結んでいる場合、計画的な贈与とみなされて遡及課税の対象となることがあります。贈与の日付や金額にバリエーションを持たせること、あえて少額の贈与税を支払う戦略など、インターネット上には様々な情報がありますが、実際のところ国税局の判断に委ねられるため、明確な基準は存在しません。
特に不動産のような高価な資産の贈与に際しては、暦年課税を利用することのリスクを理解し、事前に専門家のアドバイスを求めることが重要です。不動産贈与において暦年課税を適切に活用するためにも、税理士や弁護士などの専門家と相談し、計画的な贈与戦略を立てることをお勧めします。
相続時精算課税制度を活用した贈与のメリット
相続時精算課税制度は、生前贈与に際して特定の条件下で贈与税の負担を軽減するための制度です。この制度を利用することで、生前に最大2,500万円までの財産を特定の相続人に贈与し、その贈与された財産が被相続人の死亡時に相続財産として再評価され、最終的な相続税の計算に含められます。この方法では、生前に贈与された財産について贈与税は発生せず、被相続人の死後に相続税の対象として精算されます。
2024年1月からの改正により、相続時精算課税制度において、2,500万円の特別控除に加えて、年間110万円の基礎控除が新たに認められました。これにより、年間110万円までの贈与は贈与税が非課税となり、さらに相続税の計算時にも足し戻しの対象外となります。
この制度の適用を受けるためには、60歳以上の贈与者から18歳以上の受贈者への贈与であることが必要です。また、相続時精算課税制度の選択をするにあたっては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書と必要な書類を税務署に提出する必要があります。
特別控除額の2,500万円を超えた贈与に対しては、超えた分について20%の贈与税が課税されます。これにより、贈与者と受贈者は贈与の計画を慎重に立てることが求められます。
相続時精算課税制度を利用する際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。これにより、適切な生前対策を講じることで、相続時の税負担を軽減し、相続トラブルを防ぐことが期待できます。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)