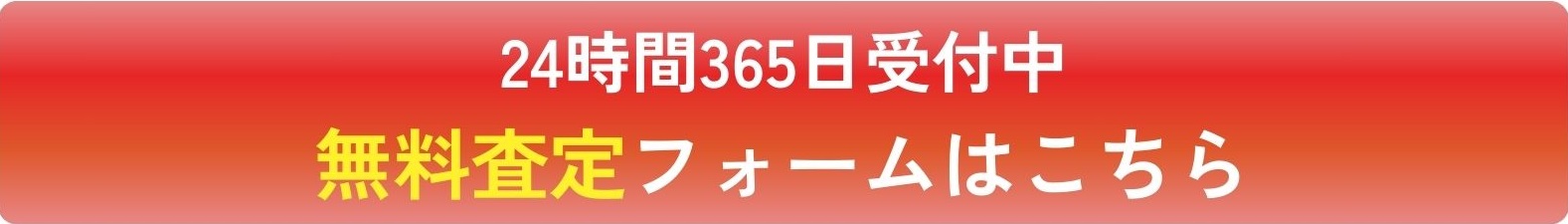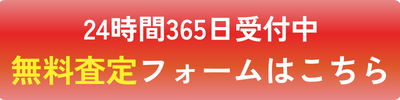不動産を共有する際、意見の相違や利害の衝突は避けられない問題です。共有物分割訴訟は、これらの紛争を解決するための法的手段を提供します。本記事では、共有物分割請求の基本から、不動産共有の問題点、分割請求の手続きと流れ、さらには訴訟のメリットとデメリットに至るまで、詳細に解説します。価格賠償、現物分割、換価分割などの解決策や、訴訟を提起された際の対応方法も紹介し、過去の裁判事例を通して理解を深めます。
共有物分割請求とは何か?
共有物分割請求とは、共有者間で共有されている不動産の所有権を明確に分割し、共有状態を解消する手続きのことを指します。不動産の共有は一般的な状況であり、家族やビジネスパートナー間でよく見られます。しかし、この共有状態は、意見の相違や将来の計画に関する不一致など、様々なトラブルの原因となり得ます。
そのため、共有物分割請求は、既存のトラブルを解決し、または将来的な不和を防ぐために重要な手段となります。共有者間での円滑な話し合いによる合意が得られない場合、共有物分割訴訟を通じて裁判所が介入し、公正な分割を決定することがあります。
このプロセスを通じて、共有者は共有不動産に関する権利と義務を明確にし、それぞれが独立した所有権を持つことができるようになります。共有物分割請求は、共有状態の解消を希望する共有者にとって、平和的かつ公正な解決策を提供する重要な法的手段です。
不動産の共有がなぜ問題になるのか?
不動産の共有が引き起こす問題点は多岐にわたりますが、特に共有者間での意見の不一致が生じやすい状況を3つ挙げて解説します。
まず、不動産の売却や賃貸に関して、共有者全員の合意が必要となることが挑戦です。不動産の売却や重要な賃貸契約の締結、大規模な改修などは全ての共有者の同意が必要であり、一人でも反対する共有者がいる場合、これらの行動を実行することができません。この同意の必要性は、共有者間で意見が分かれる原因となります。
次に、不動産の管理や修繕に関して、共有者の過半数の同意が必要になる点も問題です。日常的な賃貸管理や賃料の調整、修繕作業なども、共有者の過半数の支持がなければ進められないため、意見の対立が管理の効率を損なうことがあります。特に、管理と改修の区別が曖昧なケースでは、判断が難しい場面もあります。
最後に、相続による権利関係の複雑化も大きな問題点です。共有不動産が相続によりさらに多くの共有者に分割されることで、権利関係が複雑化し、意見の統一や共有の解消が一層困難になります。代を重ねるごとに共有者が増え、関係が遠くなるほど、共有物の管理や変更を巡る合意形成は難しくなるでしょう。
これらの問題は、共有不動産を持つ者にとって避けがたい課題であり、適切な解決策を見つけることが重要です。解決策が見つからない場合には、不動産法務に精通した専門家や弁護士に相談することが賢明です。
不動産の共有が生じる主な要因
不動産の共有が発生する主要な原因は、主に共同購入と相続の二つです。これらの要因は、不動産の所有に関して複数の人々が関与することにより、共有状態を生み出します。
共同購入による共有は、複数の個人が共同で不動産を購入し、その投資額の比率に基づいて共有持分を持つ場面で見られます。この共有形式は、夫婦、親子、あるいは兄弟姉妹間でよく見られ、共有者の間で資金を出し合って不動産を取得します。共有持分は通常、拠出した資金の割合に応じて決定され、この比率に基づき不動産の所有権が分配されます。夫婦間や親子間での共有は、将来的な問題を避けるため、遺言書を用いて共有持分の扱いを事前に定めるなどの対策が推奨されます。
相続は、不動産の共有が発生するもう一つの大きな原因です。相続によって不動産が複数の相続人によって共有されることになり、これは特に複数の相続人がいる場合に顕著です。相続人が不動産を現物分割、代償分割、あるいは換価分割によって相続する場合、それぞれの方法には長所と短所があり、相続財産の特性や相続人の状況に応じて最適な方法が選択されます。しかし、遺産の内訳や相続人の事情によっては、共有相続という形を取ることもあります。
共有不動産を扱う際は、将来の問題を回避するために、事前の対策と計画が重要です。夫婦間や親子間での共有では、遺言書による事前の取り決めが有効であり、相続時には適切な分割方法を選択することが、後のトラブルを避ける鍵となります。共有状態を避けるための対策として、不動産の一方が離婚や相続の際に他方の持分を買い取る、または遺言書によって共有持分の扱いを明確にすることが推奨されます。
共有物を解消するための3ステップ
不動産の共有状態を解消するためには、複数のアプローチが考えられます。ここでは、そのステップを詳細に解説します。
第一段階: 当事者同士での話合い
最初のステップとして、共有者同士での円滑な対話が推奨されます。例えば、共有不動産を持つ兄弟がいた場合、一方がもう一方に対して不動産の一部を金銭で買い取る提案をするなど、双方が納得する形での共有状態の解消を目指します。このプロセスでは、共有者間の良好な関係が解決への鍵となります。共有者間で合意に至れば、共有状態を無償または有償で解消することが可能ですが、土地の利用方法や共有者間の関係に対立がある場合、交渉が難航することもあります。そのため、弁護士に相談して事前に対話の方向性を定めることが有効です。
第二段階: 共有物分割請求調停
話合いだけでは解決しない場合、共有物分割請求調停の選択肢があります。これは、裁判所の調停委員が介在し、双方の話し合いをサポートする手続きです。調停では、裁判所が直接決定を下すわけではありませんが、調停委員の存在が冷静な対話を促進し、合意に至った際の調書には法的効力があります。共有物分割請求においては調停前置主義が適用されないため、調停をスキップして訴訟を提起することも可能ですが、調停による解決が望ましい場合も多いです。
第三段階: 共有物分割請求訴訟
当事者間の話合いや調停を経ても合意に至らない場合、共有物分割請求訴訟が最終手段として考えられます。この訴訟を通じて、裁判所に共有状態の解消方法を決定してもらうことになります。訴訟過程でも和解が可能であり、裁判所が下す判決によって共有状態が法的に解消されます。
共有不動産の共有状態を解消する方法は、当事者同士の協議から始まり、調停や訴訟といった法的手段に進むことがあります。各ステップでは、共有者間の合意形成を目指し、適切な解決策を見出すことが重要です。
共有物分割請求の3つの類型
共有物分割請求訴訟では、共有不動産の扱いについて裁判所が下す判決には主に三つのパターンが存在します。これらは、共有者間で公平な解決を図るために設けられています。以下で、これらの判決パターンを解説します。
価格賠償による解決
このパターンでは、共有者の一方が自身の持分をもう一方に譲渡し、代わりに金銭の支払いを受ける形式です。例として、もし土地が二人の兄弟によって半分ずつ共有されている場合、一方がもう一方の持分を買い取り、全土地を一人の単独所有にすることができます。この方法は、双方が合意に至れば、比較的スムーズに共有状態を解消できる手段です。
現物分割による解決
現物分割は、土地自体を物理的に分割し、それぞれの共有者が独自の部分を所有することになる方法です。例えば、500平方メートルの土地を250平方メートルずつに分割し、一方の共有者が土地の一部を、もう一方が残りの部分をそれぞれ単独で所有する形です。ただし、土地の形状や利用可能性によっては、この方法が適用できない場合もあります。
換価分割による解決
換価分割は、共有物を売却し、その売却益を共有者間で分配する方法です。この場合、土地は市場に出され、得られた売却金額を共有者が分け合います。この方法は、共有者が土地の利用について異なる意見を持っており、他の方法で合意に至れない場合に有効です。ただし、競売による売却は市場価格よりも低くなるリスクがある点がデメリットです。
共有物分割訴訟のメリット
共有物分割請求訴訟の提起には明確なメリットがあります。これらのメリットは、共有不動産に関連する問題を解決する上で重要な役割を果たします。
1.強制的な解消方法の決定
2.納得しやすい解消方法の実現
共有物分割請求訴訟は、共有者間での合意が難しい場合に、共有状態を効率的かつ公平に解消するための有効な手段です。裁判所による強制的な解決方法の決定と、それによってもたらされる納得しやすい解消方法は、共有不動産に関する対立を解決する上で大きなメリットを提供します。
強制的な解消方法の決定
共有物分割請求訴訟を提起する最大のメリットは、裁判所が共有状態の解消方法を強制的に決定してくれることです。
通常、共有不動産の状態を変更するためには、全共有者の同意が必要とされます。しかし、共有者間で意見が一致せず、合意に至らない場合でも、訴訟を通じて裁判所が解消方法を決定することで、共有状態を解消することが可能になります。
これにより、長期間にわたる対立や不確実性を解消し、共有者各自の権利を守ることができます
納得しやすい解消方法の実現
共有物分割請求訴訟による共有状態の解消は、裁判所による決定を通じて行われるため、共有者全員が納得しやすい解決を見つけることができます。
この手続きの大きなメリットは、共有者間での主観的な見解や価値判断が交錯し合う代わりに、客観的かつ専門的な評価に基づいた裁判所の判断によって共有状態の解消が図られる点です。具体的には、不動産鑑定士などの専門家による適正な不動産価格の評価が行われ、その結果を基に裁判所が最も公平と判断する解消方法を決定します。
このプロセスにより、共有不動産の価値に関して意見が分かれる場合でも、公正な第三者の介入により、共有者全員が公平な扱いを受けると感じることができます。さらに、裁判所の決定は法的な拘束力を持つため、決定された解消方法に対しては、共有者間で後になって意見が変わるということが防げます。
共有物分割訴訟のデメリット
共有者との関係が悪化する可能性極めて高い
共有物分割請求訴訟の提起は、共有不動産に関する問題を解決する一つの方法ですが、その過程で共有者間の人間関係が悪化するリスクがあります。裁判を通じて問題解決を図ることは、共有者間の対話による解決が困難な場合に有効な手段ですが、訴訟の性質上、公開の場での対立が避けられません。
訴訟に至ると、共有者間での協議や交渉が公に争う形へと移行し、これにより関係がさらに悪化することがあります。特に、互いに対立する主張や証拠が公開されることで、元々あった亀裂が修復不能なほどに広がる可能性があります。
ただし、共有者間の関係が既に悪化している、または話し合いによる解決が見込めない場合には、裁判による解決が適切な選択肢となることもあります。その一方で、まだ対話による解決の余地がある場合は、訴訟を避け共有者間での協議や第三者を介した調停など、他の解決手段を探求することが望ましいと言えます。
共有物分割請求訴訟の提起は、共有不動産の問題を解決するための一つの手段ですが、共有者間の人間関係への影響も十分に考慮し、慎重に進める必要があります。
共有持分の解消まで時間がかかる
共有物分割請求訴訟を進める際の一つの大きなデメリットは、共有状態の解消に要する時間が長引く可能性がある点です。このプロセスは、短期間で解決することが難しく、最短でも半年程度、場合によっては数年を要することがあります。
訴訟の長期化の主な原因には、共有者間での意見の相違、詳細な事実確認の必要性、および複数回にわたる口頭弁論が挙げられます。これらのプロセスを経ることで、解決までの時間が延長し、関係者にとって精神的な負担となることは避けられません。
さらに、裁判が長期化すると、それに伴う弁護士費用の増加も避けられず、経済的な負担が大きくなる恐れがあります。このような時間とコストの両面での影響を考えると、「迅速な解決を望む」場合には、共有物分割請求訴訟以外の解消方法を検討することが推奨されます。
共有状態の解消を目指す方は、訴訟以外にも、協議による解決や調停など、さまざまな手段を考慮することが大切です。これらの代替手段は、時間と費用の節約につながり、共有者間の関係をより良好に保つことにも寄与する可能性があります。
弁護士報酬が発生する
共有物分割請求訴訟を進める際の重要なデメリットの一つは、弁護士に支払う必要がある報酬です。訴訟手続きは複雑で専門的な知識が必要とされるため、ほとんどの場合、専門家である弁護士に依頼することが一般的です。
弁護士費用は、依頼する案件の性質や不動産の価値、さらには訴訟の複雑さによって大きく変動します。一般的な共有物分割請求訴訟では、弁護士費用が50万円から始まり、訴訟が複雑である場合や不動産の価値が高い場合は、100万円を超えることも珍しくありません。
この費用は、訴訟にかかる全体のコストの一部に過ぎず、裁判所の手数料や必要に応じて依頼するかもしれない不動産鑑定費用など、他の経費も考慮する必要があります。このため、共有物分割請求訴訟を検討する際には、事前に十分な費用見積もりを得て、全体の経済的負担を慎重に評価することが重要です。
当事者双方どちらかにとって望まない形での決着となる
共有物分割請求訴訟を起こす際には、提起者の望む判決が必ずしも得られるとは限らないという点を理解しておく必要があります。裁判所は、提出された証拠や事実に基づいて、全ての関係者に公平な解決策を見つけるために中立的な立場から判断を下します。
このプロセスの結果、以下のような状況に直面する可能性があります:
- 不動産を売却しなければならなくなる場合
- 共有者全員が金銭的な損失を被る可能性がある
特に、「換価分割」の判決が下された場合、共有不動産が市場価格より低い価格で競売にかけられ、結果として共有者全員が期待していたよりも少ない金額を手にすることになるリスクがあります。このような判決は、不動産を維持し続けることや、金銭的に有利な条件での解決を望む共有者にとっては、望ましくない結果となることがあります。
そのため、共有状態の解消を目指す場合は、訴訟による解決のみならず、協議や調停などの他の方法も検討することが推奨されます。これにより、共有者全員が納得できる解決策を見つける可能性が高まります。
共有物分割請求訴訟の流れ
まずは共有物分割協議で合意を目指す
有物分割協議では、共有者全員が共有物の分割方法について話し合い、具体的な分割内容について合意を目指します。この協議は、共有者自身やその代理人が直接会合して行うことも、書面を通じて意見を交換することも可能です。書面による協議の場合は、共有物分割の請求や提案を含む「通知書」を作成し、それをもとに話し合いが進められます。
重要なのは、共有物分割が共有者全員の合意に基づいて成立する点です。したがって、協議により合意に達した内容は、その後の手続きや実行において大きな意味を持ちます。このため、合意に至った分割方法や条件を明確に記録し、全員が署名した「合意書」を作成することが重要です。合意書には、分割される共有物の具体的な内容、分割後の所有権の帰属、必要な場合は金銭的な調整に関する条項などが含まれます。
この合意書は、共有物分割協議の結果を正式に確定する文書として機能し、後日生じるかもしれない紛争を防ぐための法的根拠となります。したがって、共有物分割をスムーズに進めるためには、協議による合意形成とその書面化が不可欠です。
合意が難しいときは共有物分割請求訴訟に入る
共有物分割請求訴訟は、共有者間での協議を通じて合意に至らない場合、または共有物の性質が複雑で単純な分割が難しい場合に提起されます。この種の訴訟は、共有者の一方が裁判所に分割を求めるもので、他の共有者の同意を得る必要はありません。訴訟は、訴状を裁判所に提出することで開始され、訴状はその後、共有者全員に通知されます。
共有物分割請求訴訟は形式的形成訴訟と呼ばれる特殊な種類の訴訟で、裁判所が当事者間の実体法上の権利関係を変更する判決を下すことが可能です。裁判所は、当事者の主張を考慮しつつも、最終的には裁判所自身が適切と判断する分割方法(現物分割、換価分割、代償分割など)を命じることができます。
実務上、多くの共有物分割請求訴訟は判決に至る前に和解によって解決されることが一般的です。その際、当事者が提案する合理的な分割案に基づいて和解が成立するケースが多く見られます。この過程では、分割内容に関する有力な主張と立証が極めて重要となります。
訴訟を進める際の戦略や主張のポイントは、具体的な事案や当事者の意向、そして共有物の特性によって異なります。したがって、共有物分割請求訴訟を検討する際には、事前に専門家の意見を聞くなどして、適切な戦略を立てることが重要です。
地方裁判所へ訴訟の申し立て
共有物分割請求訴訟を進める際の具体的な手続きは、まず地方裁判所に訴訟の申し立てを行います。これは、協議や調停を通じても共有物の分割についての解決が図れなかった場合の次のステップです。
訴訟の申立て先は、共有不動産が位置する場所、または訴訟の被告の住所地を管轄する地方裁判所になります。この選択は、訴訟の手続きを円滑に進めるためにも重要です。
訴訟を申し立てる際に必要な書類は以下のものが挙げられます:
- 訴状の正本および副本:訴訟の内容を詳細に記載した書面です。通常、専門知識を要するため、弁護士によって作成されます。
- 固定資産評価証明書:共有不動産の価値を示すために、所轄の役所から取得します。
- 全部事項証明書(登記簿謄本):不動産の登記情報を証明する書類で、法務局で取得できます。
- 収入印紙:訴状に貼付するために必要なもので、郵便局やコンビニエンスストアで購入可能です。
- 郵便料金:訴状を裁判所や被告に郵送する際に必要な料金です。
裁判所からの呼び出し状
訴訟を申し立てた後、通常1か月程度で裁判所から共有者全員に「呼出状」が送付されます。この呼出状は、裁判の期日や手続きについて当事者全員に知らせる重要な書面です。
呼出状の概要:
- 目的:裁判の期日や必要な手続きについて当事者全員に通知する。
- 内容:口頭弁論の日時や答弁書の提出期限など、裁判所の手続きに関する具体的な情報が記載されています。
口頭弁論について:
- 目的:当事者が自らの立場や主張を裁判所に直接述べる機会。
- 内容:訴状の内容に誤りがないかを確認し、当事者の主張を裁判所が聞く過程。
答弁書について:
- 目的:訴訟に関する自らの認識や意見を書面で裁判所に提出する。
- 内容:口頭弁論への出席を代替する形で、当事者の立場や反論を記載した書面。
呼出状に記載された期日に口頭弁論に出席するか、答弁書を提出することが求められます。どちらの手続きも行わない場合、裁判所は当事者が訴訟における主張を放棄したとみなし、結果として相手方の主張が判決に大きく影響する可能性があります。このため、裁判所からの呼出しには迅速かつ適切に対応することが不可欠です。
口頭弁論及び裁判所の判決
裁判の日には、担当弁護士が代表して「口頭弁論」に出席することになりますが、もし本人も出席を希望する場合は、弁護士と共に裁判所に行くことが可能です。訴訟の過程で、他の共有者からの反論や新たな事実確認の必要性が生じた場合、複数回にわたる口頭弁論が実施されることがあります。
裁判所からの判決について: 裁判所は、口頭弁論や提出された答弁書の内容を基に、共有不動産の分割方法についての判決を下します。この際、裁判所は共有物の状態を解消するために最も適切な方法を決定する責務がありますが、その結果が必ずしも当事者の望む通りになるとは限りません。
共有物分割請求訴訟の判決によっては、競売による分割など、共有者全員に金銭的な損失をもたらす結果になる可能性もあります。このため、判決が下される前に、可能であれば共有者間で妥協点を見つけることが望ましいとされます。
判決内容に関しては、裁判所がどのような分割方法を選択するか(現物分割、換価分割、代償分割など)により異なります。これらの分割方法については、それぞれのメリットとデメリットを理解し、共有者が納得できる解決策を模索することが重要です。
過去の裁判事例の紹介
東京地判平成26.5.22(ウエストロー・ジャパン)
東京地裁の平成26年5月22日の裁判例(ウエストロー・ジャパン)は、共有物分割請求訴訟における価格賠償方式の分割が認められた事例です。この事例では、鉄骨造4階建ての小規模共同住宅事務所に関する訴訟が取り扱われました。この建物は、ある個人が所有していたが、その死亡により相続が発生し、結果的に複数の共有者が生じました。その後、共有持分の一部が譲渡され、特定の共有者が大部分の持分を有する状態になりました。
共有者の一方が、他方に対して共有物の分割を求めましたが、拒否されたため、価格賠償による分割を求めて訴訟が提起されました。裁判所は、物理的に現物分割が不可能であること、また、建物内の各区画を区分所有建物として現物分割することも一つの解決策であるが、共有者間の対立や管理上の困難が予見されるため、経済的価値を損なう恐れがあると判断しました。
裁判所は、共有者の一方が建物を所有し、他方に対してその共有持分に相当する適正価格を支払うこととする価格賠償方式の分割を認めました。この判断は、共有物の管理や使用に関する具体的な計画や理解が不足している共有者がいる場合、また、共有者間でのコミュニケーションが取れていない場合に、共有物の価値を最大限に保護するための適切な方法とされました。
この裁判例は、共有物分割請求訴訟における裁判所の判断基準や、共有者間での対立が共有物の経済的価値に与える影響について理解する上で有用な事例です。
最高裁平成25年11月29日判決・共有物分割等請求事件
最高裁判所の平成25年11月29日の判決では、共有物分割請求訴訟において、遺産の共有持分と他の共有持分が併存する状況について、その解消方法に関する重要な指針を示しています。
この判決は、遺産分割が未了である状態の遺産共有持分と、他の共有持分が存在する土地に関する共有物分割請求訴訟に関するものです。土地の共有者の一部が死亡し、その遺産が共有状態にある中、残る共有者が土地の分割を求める事案でした。本件土地は、物理的な現物分割が不可能であることから、価格賠償による分割が提案されました。
最高裁は以下のように判断しました:
- 共有物分割と遺産分割の関係:共有者が遺産共有持分と他の共有持分の解消を求める場合、民法258条に基づく共有物分割訴訟が適切であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与される財産は、遺産分割の対象となります。
- 賠償金の性質:遺産共有持分と他の共有持分の分割判決がされた場合、賠償金は遺産分割の対象となるべきであり、遺産共有持分権者は、遺産分割が行われるまで賠償金を保管する義務があります。
- 非訟事件の性質と裁判所の裁量:共有物分割訴訟は非訟事件の性質を持ち、裁判所は共有者間の公平を保ちつつ、共有物の性質や共有状態の実情に適合した分割を実現するために適切な裁量を行使する必要があります。
この判決は、共有物の分割に関する複雑な問題、特に遺産共有の状態にある共有物の扱いについて、法的な指針を提供しています。また、共有物分割請求訴訟において裁判所が取るべき態度と、遺産共有持分権者の責任についても明確にしています。
逆に共有物分割訴訟を提起されたとき
共有物分割請求訴訟が提起された場合、裁判所は分割方法について判決を下す権限を持っています。この過程で、裁判所が選択する分割方法は、当事者が望まないものである可能性があります。たとえば、不動産が市場価格以下で競売にかけられる場合、最終的には不動産が失われ、その売却代金が共有者間で持分割合に応じて分配される結果となることもあります。
このような状況を回避するためには、共有持分が競売により売却される前に、該当する不動産を自ら買い取るという対策が有効です。このアプローチにより、不動産を保持し続けることができ、不利益な売却を防ぐことが可能になります。
共有物分割請求訴訟は、訴訟当事者間での和解によって解決されるケースが一般的です。そのため、訴訟が提起された場合には、それを放置するのではなく、自らが望む分割方法や解決策を積極的に主張し、和解に向けて努力することが重要です。このプロセスを通じて、共有者双方にとって公平かつ実行可能な解決策を見つけ出すことができます。
共有物分割請求訴訟の法的性質を理解する
共有物分割請求訴訟は、固有必要的共同訴訟という特殊な類型に分類されます。これは、共有物を持つ全ての共有持分権者が訴訟の当事者として参加する必要があることを意味します。その結果、訴状は裁判所から共有者全員に送付され、全員が訴訟過程において一定の役割を果たします。
この訴訟は、一般的な民事訴訟とは異なり、形式的形成訴訟と称される独特の法的性質を持ちます。形式的形成訴訟は、実質的に非訟事件として扱われ、共有物の分割を求める申立てが主要な目的となります。この場合、申立てる際に分割の具体的方法を指定する必要はなく、単に分割を求めることだけで足ります。これは、通常の訴訟においては請求内容を明確に特定する必要があるという点とは対照的です。
さらに、裁判所は当事者の提案に拘束されず、分割方法について自由に判断を下すことが可能です。これにより、裁判所は合理的かつ実行可能な分割方法を判決によって命じることができ、共有物の公平な分割を実現するための柔軟性が確保されます。この訴訟の法的性質は、共有物の分割問題を解決する際に、当事者間の合意が得られない状況でも、適切な解決策を見出すための枠組みを提供します。
裁判所の判決を理解する
共有物分割請求訴訟に際して裁判所が下す判決は、当事者の提案に拘束されないものの、実際には当事者の合理的な意見や共有物の利用状況など、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。以下は、裁判所が分割方法を選択する際に特に重視する事情の概要です
- 当事者の希望:裁判所は、各当事者が主張する分割方法の中から、最も妥当と考えられる方法を選択します。これには、当事者の要望や分割後の利用計画などが考慮されます。
- 持分割合:当事者間で持分が大きく偏っている場合、現物分割ではなく金銭的な補償による解決が選ばれることがあります。これは、持分比率に基づいた公平性を保つためです。
- 共有物の形状:共有物の物理的特性、例えば形状や高低差、周囲の道路との接続なども、分割方法の決定に影響します。分割後も実用的な利用が可能であることが重視されます。
- 共有物の利用状況:共有物を利用している共有者の状況、例えば居住や事業の運営なども考慮され、利用状況の変更を最小限に抑える分割方法が選択されることがあります。
- 経済的価値:分割方法は共有者間の経済的公平を図ることも目的としています。そのため、現物分割時には各共有者が得る土地や建物の価値が均等になるよう努められます。平等性を確保できない場合は、金銭的な補償を通じて調整されます。
共有物分割請求訴訟は、裁判所による判決よりも和解によって終結することが一般的です。和解では、当事者が合意に至った分割方法が採用されます。このため、当事者は自らの立場から合理的で実現可能な分割案を提案し、積極的に交渉を進めることが求められます。分割案を巡る主張は、具体的な事案や当事者の意向に応じて適切に行われるべきです。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)