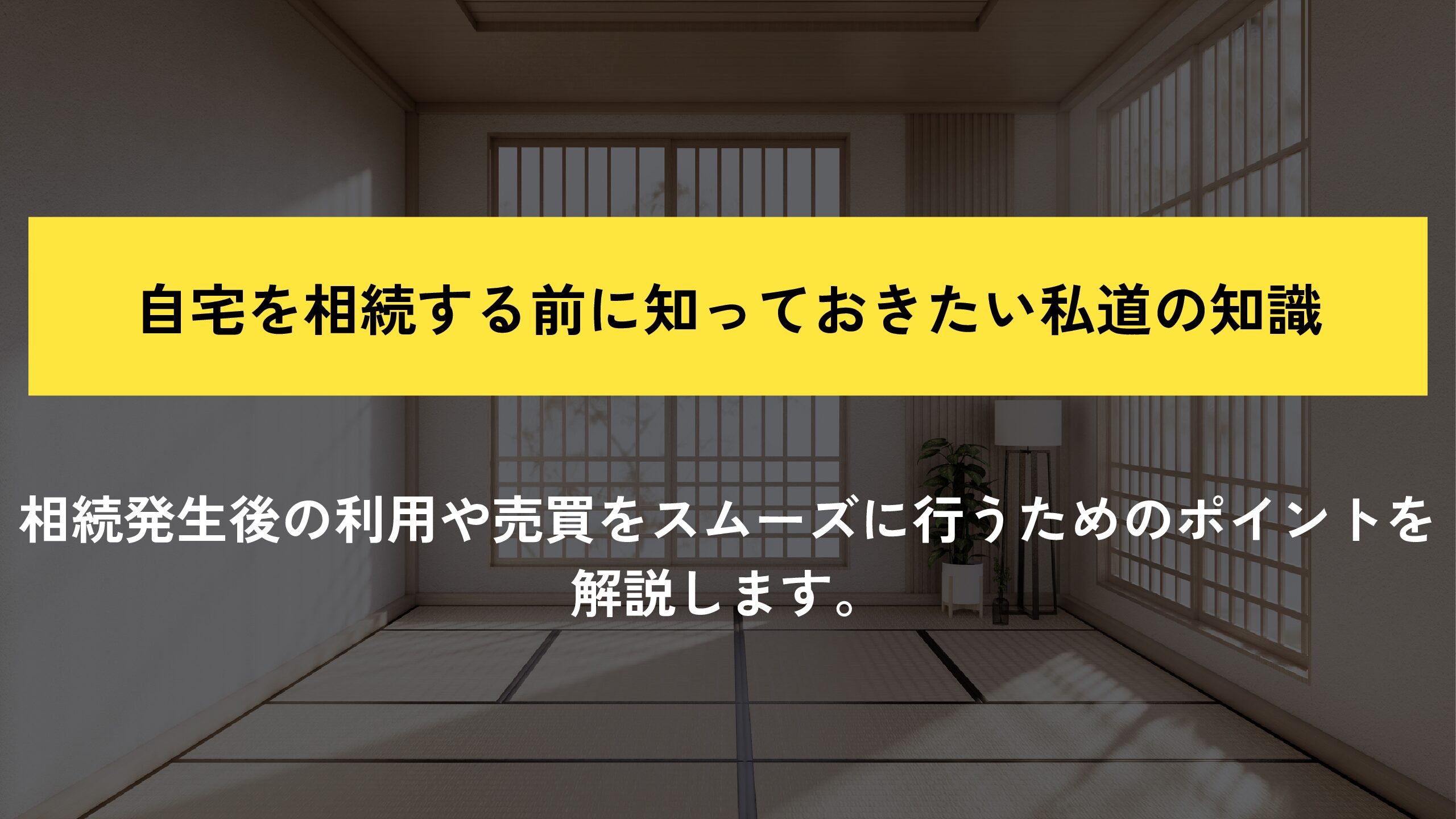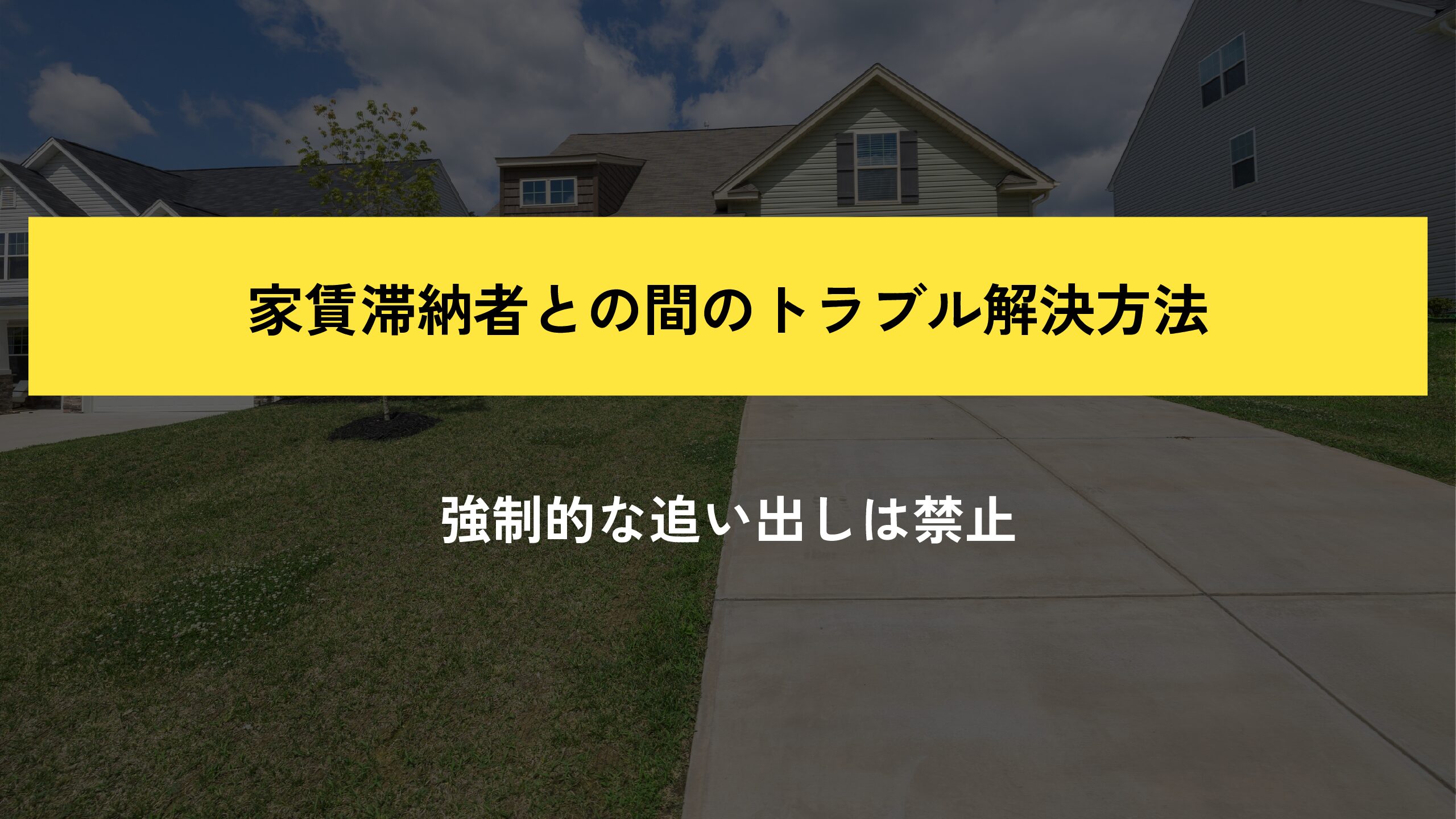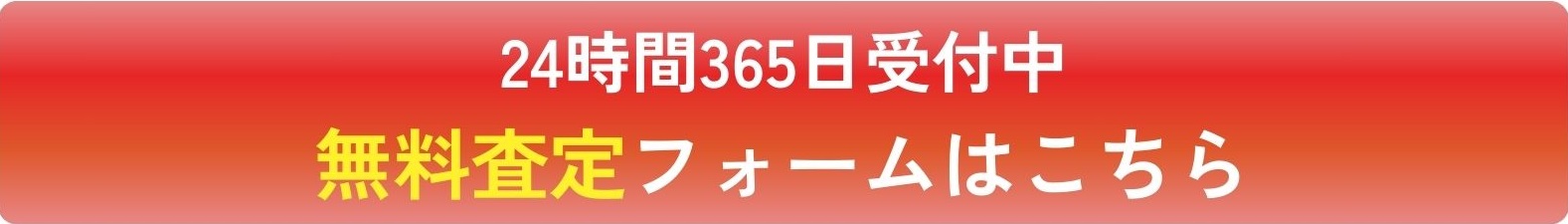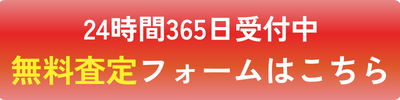実家やご自身が所有する不動産が「再建築不可」と知り、どうすれば良いか悩んでいる方は少なくないでしょう。リフォームして住み続けるべきか、それとも売却するべきか…判断に迷うのも無理はありません。
再建築不可物件は、リフォームの範囲が限られる、売却価格が下がってしまうなど、一般的な不動産に比べて不利な状況です。しかし、だからといって何もできないわけではありません。
このブログでは、再建築不可物件でも可能なリフォームの規模や範囲、そして安易な判断で違法な増改築をしてしまった場合のリスクについて詳しく解説します。
再建築不可物件の所有でお悩みの方は、ぜひこの記事を参考に、今後の対策について考えてみてください。
再建築不可物件って増築できるの? 意外と多いその実態とは
再建築不可物件とは、今ある建物を壊して、新しく建て替えることができない物件のことです。
なぜ再建築不可になるのか?
再建築不可となる理由は、接道義務という建築基準法のルールを満たしていないからです。
接道義務とは、簡単に言うと、建物が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。これは、災害などが起きた時に、緊急車両がスムーズに通行できるように、また、避難経路を確保できるように、という目的で定められています。
しかし、この法律ができる前に建てられた建物や、昔は都市計画区域でなかった地域に建てられた建物の中には、この接道義務を満たしていないものが今でもたくさん残っています。
再建築不可物件、実はこんなに身近に!
再建築不可物件とは、建て替えができない物件のことですが、実はその数は想像以上に多いのです。
ある調査によると、都市計画区域や準都市計画区域内にある物件のうち、約5%が再建築不可物件と見られています。
これは、建築基準法の厳格化や都市計画の変更などにより、古い住宅が現在の基準を満たしていないケースが多いことが原因です。
例えば、東京都23区は全域が都市計画区域に指定されており、総務省の調査によると、23区内の住宅数は約490万戸。そのうち、約24万戸が再建築不可物件と疑われています。
これは、23区内の住宅の約5%に相当し、いかに再建築不可物件が身近な存在であるかが分かります。
増築はできるの?
再建築不可物件は、建て替えができないだけでなく、原則として増築もできません。ただし、例外的に、小規模な増築や修繕であれば可能な場合もあります。
再建築不可物件は、価格が安いなどのメリットもありますが、建て替えや増築ができないという大きなデメリットもあります。購入を検討する際は、これらの点に注意し、専門家に相談するなどして、慎重に判断するようにしましょう
再建築不可物件のリフォーム、どこまでできる?
再建築不可物件は、建て替えができない物件ですが、リフォームは可能です。ただし、どこまでできるのか、注意が必要です。
建築確認申請が必要な工事はNG
再建築不可物件では、原則として建築確認申請が必要な増改築はできません。ごく小規模なリフォームであれば、申請なしで可能です。具体的には、
- 防火・準防火地域以外
- 10平方メートル以内の増改築
- 建物の1/2以内の修繕・模様替え
これらに該当する場合です。
屋根や外壁の全面補修はできる?
10平方メートルを超える増改築や、建物の1/2を超える修繕は、再建築不可物件ではできません。屋根や外壁の全面的な補修も、この範囲を超える場合はNGです。
例外:4号建築物なら大規模リフォームもOK
例外的に、4号建築物と呼ばれる小規模な建物は、建築確認申請が不要なため、再建築不可物件でも大規模なリフォームが可能です。
4号建築物は、
- 木造の場合: 2階建て以下かつ床面積500平方メートル以下
- 木造以外の場合: 平屋かつ床面積200平方メートル以下
と定義されています。多くの再建築不可物件は、この4号建築物に該当するため、外壁や屋根の全面補修も可能です。
セットバックで再建築不可を解決!
再建築不可物件でも、セットバックという方法を使えば、増築できる可能性があります。
セットバックとは、建物を道路から後退させて建てることで、接道義務を満たすための「みなし道路」を確保する方法です。
セットバックが必要なケース
- 道路に面している幅は十分だが、道路幅が4m未満の場合
- 道路の向かい側に建物がある場合
セットバックの方法
道路の向かい側に建物がある場合は、道路の中心線から2m後退させることで、接道義務を満たしたとみなされます。
一方、道路の向かい側が河川や崖などの場合は、不足している道路幅分だけセットバックする必要があります。
例えば、道路幅が3mの場合、1m不足しているので、
- 向かい側が宅地なら0.5mセットバック
- 向かい側が河川や崖なら1mセットバック
が必要になります。
注意点
セットバックを行うには、建築基準法などの法規制を遵守する必要があります。また、セットバックによって建物の面積が減ってしまう可能性もあります。
再建築不可物件の増築を検討する際は、専門家(建築士など)に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
セットバックの手続きや費用については下記のブログでも解説しています。ぜひ参考にご覧ください。
隣接地購入で再建築不可を解消!
再建築不可物件が道路に2m以上接していない場合、隣接する土地を購入するという方法で、接道義務を満たし、再建築可能にすることができます。
隣接地購入のメリット
- 再建築が可能になる: 接道義務を満たすことで、建て替えや増築が可能になります。
- 物件の価値が上がる: 敷地面積が広がることで、物件全体の価値が向上します。
- 理想の住まいを実現できる: 敷地面積が広がることで、より自由度の高い間取りやデザインが可能になります。
隣接地購入の注意点
- 近隣との交渉が必要: 隣接する土地の所有者との交渉が必要になります。不動産会社などの専門家に依頼し、スムーズな交渉を進めることが大切です。
- 費用がかかる: 土地購入には費用がかかります。予算と照らし合わせて、慎重に検討しましょう。
まとめ
再建築不可物件でも、隣接地購入という方法で、再建築が可能になる可能性があります。
ただし、近隣との交渉や費用面など、注意すべき点もあります。専門家に相談しながら、慎重に進めるようにしましょう。
再建築不可物件の購入を検討している方は、ぜひこの方法も視野に入れてみてください。
再建築不可物件でも諦めないで!接道義務の例外規定「但し書き」とは?(43条但し書き規定)
再建築不可物件だからといって、必ずしも建て替えができないわけではありません。実は、接道義務には例外規定があり、条件を満たせば再建築が可能になる場合があります。
接道義務の例外規定「但し書き」とは?
建築基準法第43条には、接道義務の例外規定「但し書き」が定められています。これは、緊急車両の通行や避難経路の確保に支障がないと認められれば、接道義務を満たしていなくても再建築を許可できるというものです。
具体的には、以下の2つのケースが該当します。
- 幅4m以上の道に2m以上接しているが、利用者が少ない小規模な建物で、特定行政庁が安全上問題ないと認めた場合。
- 敷地の周囲に広い空地(公園や広場など)がある建物で、特定行政庁が安全上問題ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合。
但し書きの適用を受けるには?
但し書きの適用を受けるには、特定行政庁(都道府県や市区町村)の許可が必要です。近くに広い空間があるからといって、必ずしも許可されるとは限りません。
各自治体ごとに決められた基準があルため、各自治体に問い合わせることが必要になります。詳細は下記の記事をご覧ください。世田谷区について一部解説を行なっています。
専門家への相談を
再建築不可物件でも、但し書きの適用を受ければ、再建築が可能になる可能性があります。しかし、手続きは複雑で、専門的な知識も必要です。
もし、あなたの物件が但し書きに該当する可能性がある場合は、まずは役所や建築士などの専門家に相談することをおすすめします。
再建築不可物件の購入・増築、知っておきたい注意点
再建築不可物件の購入や増築には、いくつかの注意点があります。事前にしっかりと把握し、安心して計画を進めましょう。
耐震性の問題
再建築不可物件は、古い建物が多く、現在の耐震基準を満たしていないケースが少なくありません。増築によって既存の建物との間に耐震性の差が生じると、かえって倒壊リスクが高まる可能性もあります。
増築前に必ず耐震診断を行い、必要であれば耐震補強工事を行いましょう。
建築基準法の遵守
増築には、建ぺい率や容積率など、建築基準法の規定を遵守する必要があります。建ぺい率は敷地面積に対する建物面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を示し、地域や用途によって上限が定められています。
増築計画が法規制に適合しているか、必ず自治体や専門業者に確認しましょう。
固定資産税の増加
再建築不可物件は、資産価値が低いため、固定資産税が安く設定されています。しかし、セットバックや隣接地購入などで再建築が可能になると、固定資産税も一般的な水準に上がります。
増築や再建築の際には、工事費用だけでなく、固定資産税の増加も見込んで予算を組みましょう。
再建築不可物件について建築確認申請を取らずに建築するとどうなるか?
住宅の増築には、原則として建築確認申請が必要です。これは、建物の安全性を確保し、建築基準法に適合しているかを確認するための重要な手続きです。
建築確認申請とは?
建築確認申請とは、建物の構造や耐久性、地盤の強度などが建築基準法の基準を満たしているかを、専門機関(自治体や民間の検査機関)がチェックする手続きのことです。
通常、10平方メートルを超える増築や大規模なリフォームを行う際には、この申請が必要となります。申請手続き自体は、建築士や施工業者といった専門家が代行するため、施主が直接行うことはありません。
なぜ建築確認申請が必要なの?
建築確認申請は、建物の安全性を確保し、そこで暮らす人々や近隣住民の安全を守るために必要不可欠です。建築基準法に適合した建物を建てることで、地震や火災などの災害から人々を守ることができます。
建築確認は、通常、建築計画の段階と工事完了後の2回に分けて行われます。計画段階で問題がないかを確認し、完成後に計画通りに工事が行われたかをチェックすることで、建物の安全性を二重に確認します。
無許可増築のリスクとは?
再建築不可物件であっても、建築確認申請が必要な増築は、必ず申請を行いましょう。無許可で工事を行うと、以下のようなリスクがあります。
- 行政指導: 自治体から是正勧告や工事の中断・中止命令を受ける可能性があります。
- 罰則: 行政指導に従わない場合、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があります。
- 安全性の問題: 建築基準法に適合していない建物は、地震や火災などの災害時に安全性が確保できない可能性があります。
違法建築の不動産は住宅ローンが組めない!
違法建築の不動産は、既存不適格物件とは異なり、原則として住宅ローンを利用できません。
これは、違法建築が建築基準法に違反しているため、金融機関が融資のリスクを負えないことが主な理由です。
住宅ローンが利用できないということは、売却の際に大きなデメリットとなります。現金一括で購入できる人にしか売ることができないため、買い手候補が大幅に限定されてしまいます。
その結果、売却価格を大幅に下げざるを得ない状況に陥る可能性も高いです。
まとめ:再建築不可物件の活用、お任せください!
再建築不可物件は、小規模なリフォームやリノベーションであれば可能な場合が多いですが、その範囲は限定的です。そのため、物件の利用や売却に制限が生じ、一般の方への売買は難しくなる傾向があります。
しかし、再建築不可物件だからといって諦める必要はありません。弊社では、再建築不可物件の売買や投資家への販売を積極的に行っております。
豊富なリフォーム実績を活かし、物件の価値を最大限に引き出すご提案が可能です。再建築不可物件をお持ちの方、ぜひお気軽にご相談ください。お客様のニーズに合わせた最適な活用方法をご提案させていただきます。
再建築不可物件の売却・活用でお悩みの方は、ぜひ一度弊社にご連絡ください。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)
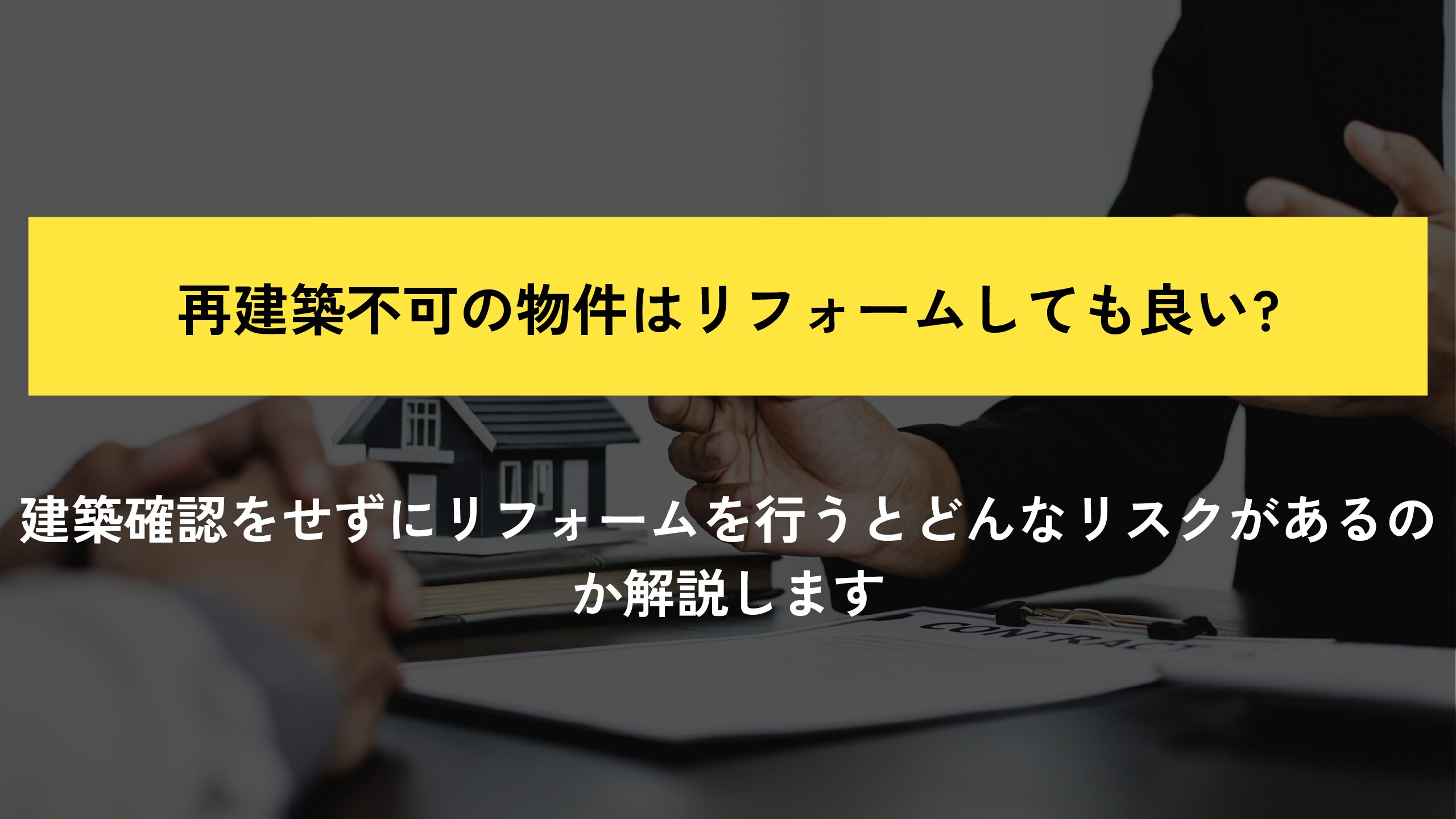
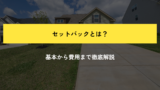
とは?再建築不可物件の救済措置!-160x90.png)