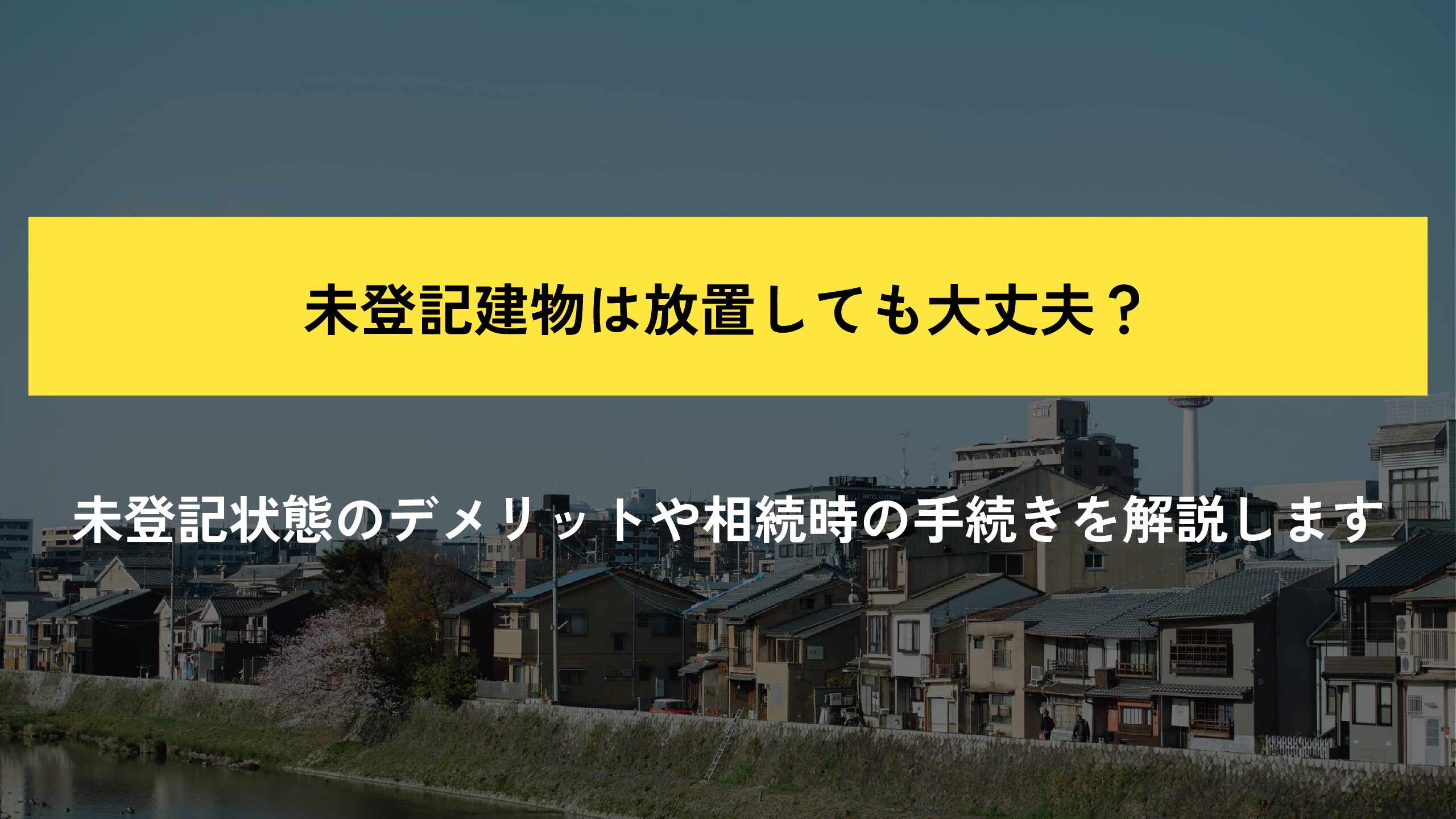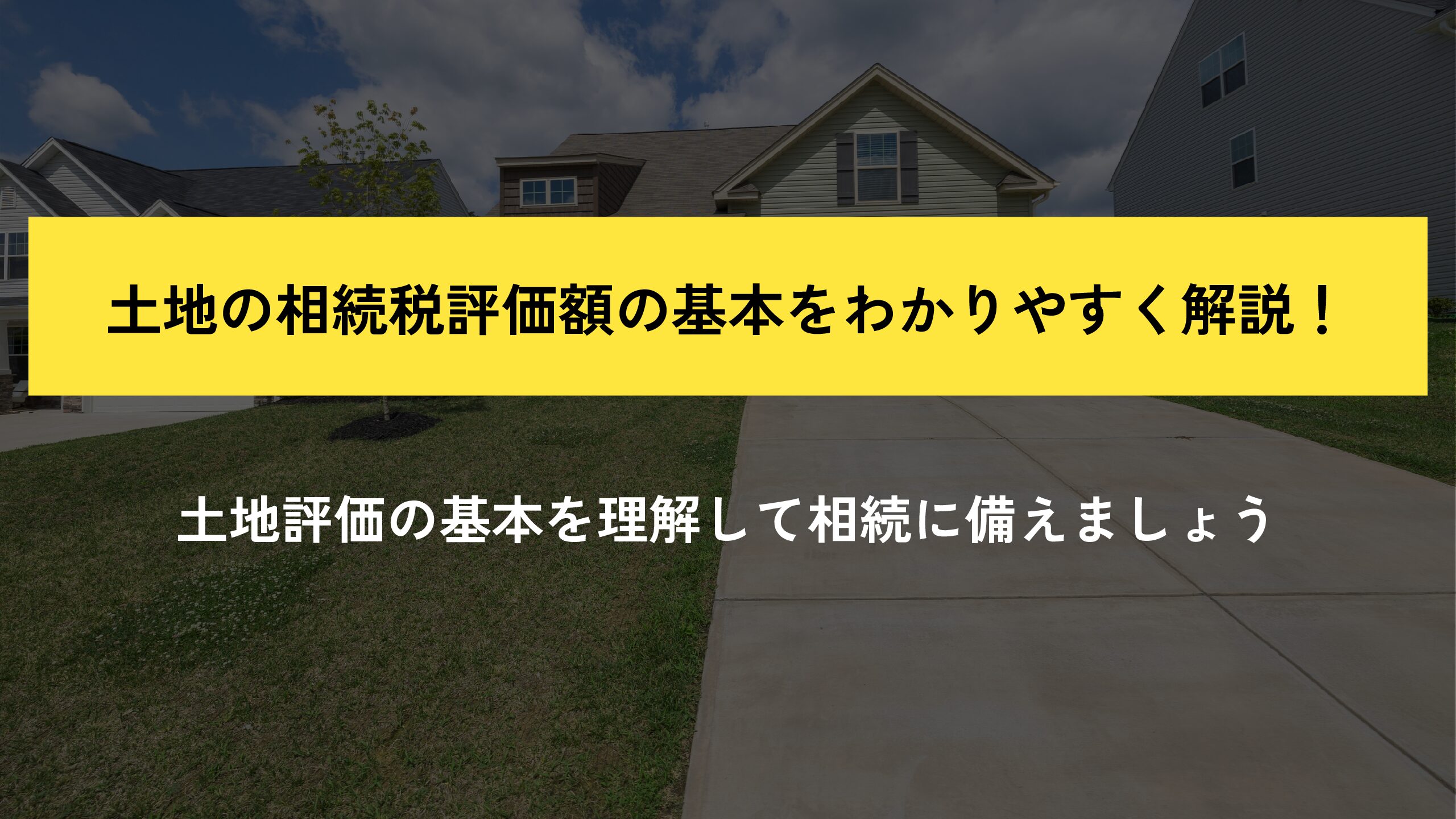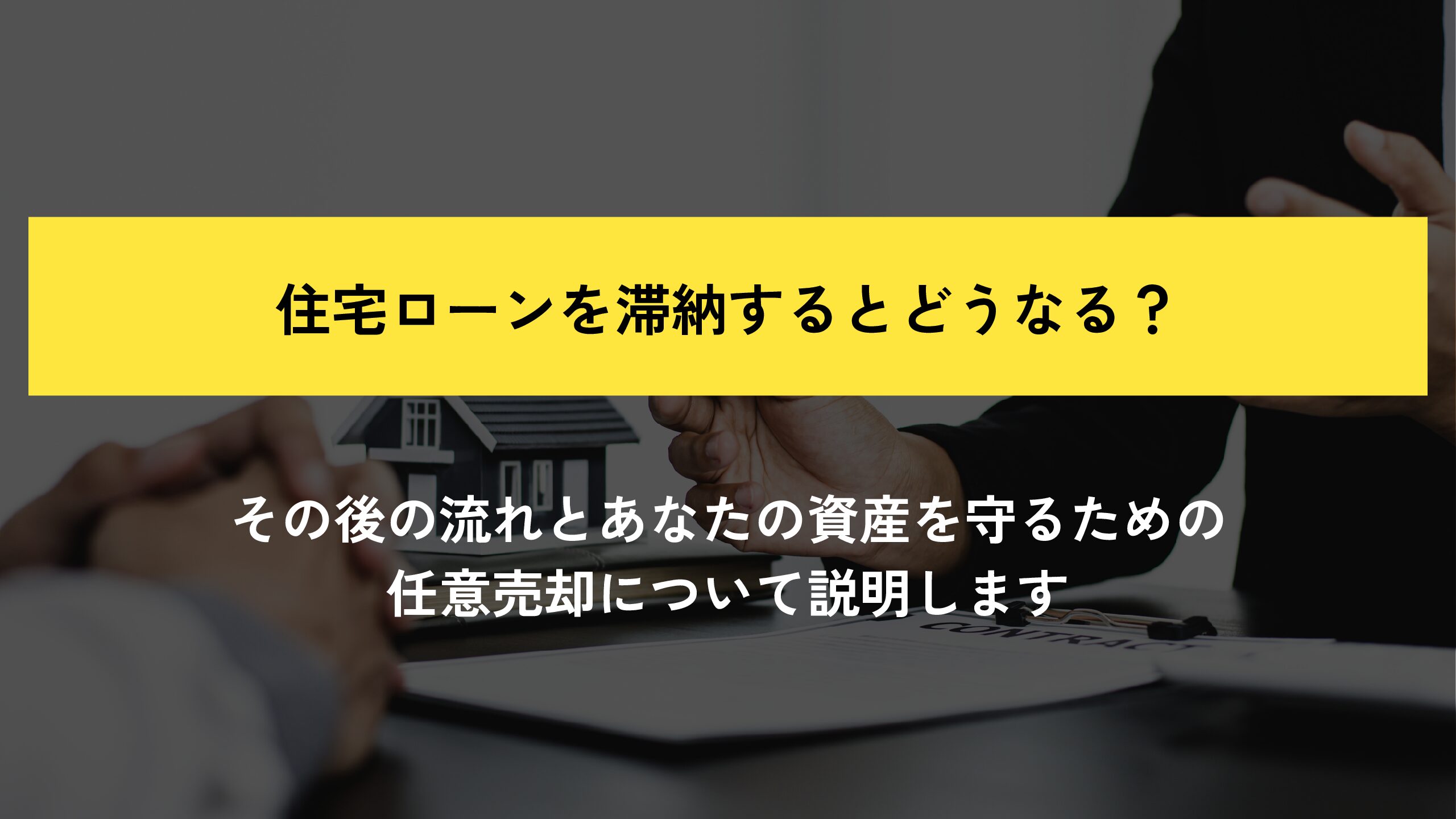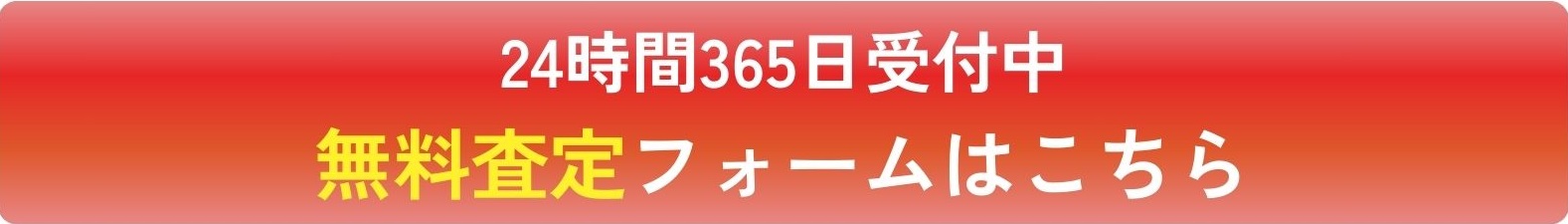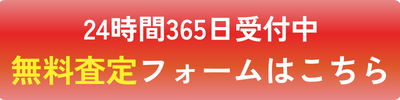2024年4月より相続登記が義務化され、未登記不動産の登記申請が進むと予想されます。しかし、相続時に未登記だった建物の登記は、通常の相続登記とは異なる手続きが必要です。本ブログでは、これらの手続きについて詳しく解説していきます。
相続した建物が未登記だった!
未登記建物とは
不動産登記とは、土地や建物の所有者を公的に明確にするための記録です。登記を行うと、土地と建物はそれぞれ個別に登記され、登記簿謄本が作成されます。
登記簿謄本は、「表題部」(不動産の所在地や種類など)、「権利部(甲区)」(所有者)、「権利部(乙区)」(抵当権などの権利)の3つの部分に分かれています。 土地の購入や建物の新築時には、1か月以内に「表題登記」を行うことが法律で義務付けられています。しかし、この義務が履行されず、登記されていない、表題登記のみで権利登記がされていない、表題部の内容が古いままになっている建物が存在します。このような、登記記録上で所有者や所在地が不明確な建物を「未登記建物」と呼びます。
未登記となってしまう原因
1つ目の理由は、自己資金で建物を建てた場合です。住宅ローンを利用する場合は、金融機関が抵当権を設定するため登記が必要ですが、自己資金の場合は登記の必要性が薄いため、未登記のまま放置されることがあります。そのため、未登記建物は住宅ローンが普及する前に建てられた古い建物に多く見られます。
2つ目の理由は、意図的に「表題登記」のみを行ったケースです。表題登記は義務ですが、「権利登記」は任意であり、登録免許税の支払いも発生するため、意図的に表題登記のみを行う人がいたようです。 その他、母屋は登記されているものの、増築部分の登記を忘れたまま未登記となっているケースも存在します。
未登記建物の手続きを怠るとどうなる?
「表題登記」は法律で義務化されており、不動産登記法47条1項では、建物の所有権取得後1か月以内に表題登記を申請するよう定められています。さらに、第164条では、申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられると規定されています。
しかし、実際には未登記の建物は多く存在し、違反者への厳格な取り締まりは行われていないのが現状です。とはいえ、法律違反の状態を放置することは望ましくありません。未登記建物には様々なデメリットがあるため、適切な登記手続きを行うことが重要です。
未登記でも固定資産税はかかる
未登記の建物であっても、固定資産税は課税されます。固定資産税は現況に基づいて判断されるため、市町村の職員が現地調査で建物を確認した時点で課税対象となるのが一般的です。自治体は過去の航空写真との比較など、様々な方法で課税対象となる不動産を常に調査しています。
登記をしないことによるデメリット
担保的価値がないため融資が受けられない
最大のデメリットは、融資を受けられないことです。つまり、住宅ローンを組むことができません。未登記建物には所有権や抵当権を設定できないため、担保がなく、融資の対象外となります。未登記物件でも、リフォーム費用を現金一括で支払える場合は問題ありませんが、数百万円から数千万円という高額な費用を一度に支払える人は稀でしょう。
固定資産税などの減免措置を受けられない
住宅が建っている土地には、固定資産税と都市計画税の減額措置が適用されますが、建物の登記がない場合はこの恩恵を受けられません。固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3の減額が可能なので、登記をしていないと、本来受けられるはずの減額を受けられず、損をしてしまう可能性があります
未納分の固定資産税の請求リスク
未登記の建物で固定資産税を支払っていない場合、自治体が建物の存在を把握すると、過去の未納分の固定資産税が請求される可能性があります。建物の築年数が古いほど未納期間が長くなり、支払額が膨らむ可能性もあるため、注意が必要です。
自分のものと主張できない(対抗要件を満たさない)
未登記建物は、所有権を第三者に主張するための対抗要件を満たしていません。例えば、借りた土地に未登記の建物を建てて住んでいる場合、土地の所有者が変わると、新しい所有者から立ち退きを求められても、建物の所有権や借地権を主張することが難しくなります。未登記のままでは、自分の権利を守ることができない可能性があるのです。
建物の取引が難しくなる
未登記建物は、法的には売買可能ですが、現実的には難しいと言えます。登記情報がないため、所有権移転登記ができず、登記上は所有者不明のままです。購入しても所有権を主張できず、買い手が金融機関からの融資を受けることもできません。これらの理由から、未登記建物をそのまま売却することは困難と言えるでしょう。
売却しづらい
未登記建物は、買い手も住宅ローンを利用できないため、現金で支払える相手を探す必要があります。数百万円から数千万円を現金で支払える人は限られるため、相場よりも安く売却したり、買い手が見つかるまで長期間待つ可能性があります。 現金を持っている投資家などが見つかれば良いですが、現実的には難しいでしょう。また、第三者に対する対抗要件を満たしていない不動産の取引はリスクが高く、購入を希望する人は少ないです。通常の取引では、売却は困難と言えるでしょう
相続手続きが面倒
相続時に建物を売却したり、リフォーム資金の融資を受ける予定がない場合は、未登記のままでも問題ありません。しかし、将来的に売却やリフォームを検討している場合は、登記が必要です。未登記のまま所有者が亡くなった場合、建物の図面や建築確認済証、評価証明書などが紛失している可能性があり、必要書類の準備に時間がかかる場合があります。
登記に想定外の費用がかかる
不動産登記には、「表題部登記」(未登記の土地や建物の新規登記)と「権利部登記」(所有権やその他の権利に関する登記)の2種類があります。書類の準備は数か月から数年かかる場合もあり、多大な時間と労力を要します。そのため、通常は土地家屋調査士や司法書士に依頼することになりますが、その費用は数万円から数十万円に上ります。
未登記建物の登記手続きと費用
普通の相続登記との違い
不動産相続における登記手続きは、通常、登記簿謄本に記載の所有者名義を被相続人から相続人に変更する「所有権移転登記」です。しかし、未登記の建物では、この所有権移転登記の前に、建物の「表題登記」を行う必要があります。
表題登記では、建物の所有権を証明する資料の提出が必要ですが、古い建物ではこの資料の入手が困難な場合があり、手続きが複雑化することがあります。
未登記建物も遺産分割協議を行う必要がある
未登記の建物も相続財産に含まれます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が引き継ぐか決定する必要があります。未登記建物の存在を知らずに遺産分割協議が終了し、後から発見された場合、改めて協議が必要になります。遺産分割協議がスムーズに進んだとしても、再度話し合いを行うのは負担が大きいため、未登記建物の可能性がある場合は、事前に調査することが重要です。
未登記建物がどうかの確認方法
未登記建物の有無を簡単に確認するには、固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書をチェックする方法があります。「家屋番号」の欄が「空白」または「未登記家屋」と記載されている場合、その建物は未登記です。登記済みの建物であれば、家屋番号には数字が記載されています。納税通知書が見つからない場合は、「名寄帳」で確認することも可能です。
登記は国の法務省が管理しますが、固定資産税は市町村が管理します。登記は所有者が自ら申請するものであり、法務局が新築不動産を把握して自動的に登記するわけではありません。一方、市町村は独自に調査を行い、登記の有無に関わらず課税します。そのため、未登記でも課税対象となる場合があります。
登記費用
登記は、多大な時間と労力を費やせば自身で申請することも可能ですが、通常は土地家屋調査士や司法書士に依頼します。費用は依頼先や不動産の状況によって異なりますが、ここでは一般的な戸建て住宅を例に、費用の内訳を詳しく解説します。
表題登記の費用
司法書士に依頼する場合、費用は2~3万円程度が目安となります。加えて、登録免許税として1~3万円の実費がかかります。登録免許税は、自分で登記する場合でも必要です。 一方、土地家屋調査士に依頼する場合は、費用は8~10万円程度が目安です。表題登記には登録免許税などは発生しないため、自分で行えば費用はかかりません。
所有権保存登記の費用
司法書士に依頼する場合、費用は2~3万円程度が目安となります。加えて、登録免許税として1~3万円の実費がかかります。登録免許税は、自分で登記する場合でも必要です。
抵当権設定登記の費用
抵当権設定登記を依頼する場合、費用は3~5万円程度が目安となります。さらに、登録免許税として2~20万円程度の実費がかかります。登録免許税の金額に幅があるのは、住宅ローンの借入額によって変動すること、条件によって税率が4倍も異なることが理由です。
まとめ
未登記建物を相続すると、その後の相続手続きで必ず表題登記が必要になります。相続登記と同時に表題登記を行うなど、手間がかかるため、事前に表題登記を済ませて未登記状態を解消しておくことをおすすめします。また、相続発生前に不動産を売却する場合など、未登記建物は売却が非常に困難です。いざという時にスムーズに建物を処分できるように、早急に登記を行い、未登記状態を解消することが望ましいでしょう。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)