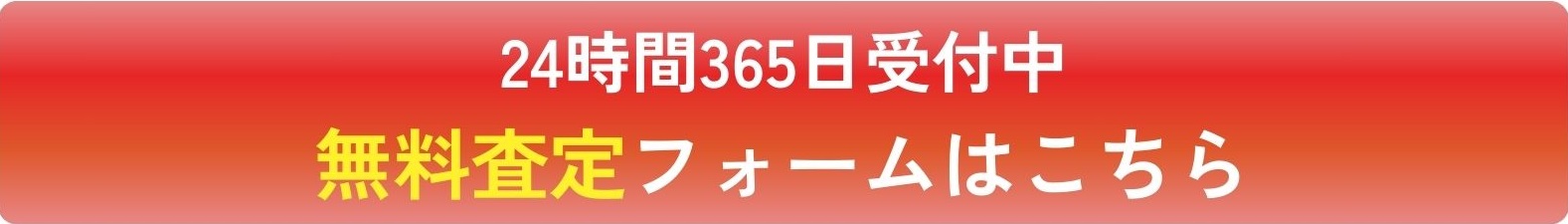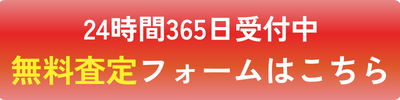建築基準法の42条と43条は、建物の立地に関わる重要な条文ですが、その内容は複雑で理解しにくいことが多いです。この記事では、建築基準法の道路に関する規定と接道義務についてわかりやすく解説しています。42条では、建築基準法上の道路の種類とその特徴について、43条では接道義務の基本から市区町村の独自基準までを詳しく説明します。建築計画を立てる際に必要な基本情報を、この記事で押さえましょう。
建築基準法の道路と接道義務の総論
土地の売買において、その土地に建物を建てることが可能かどうかは、価格にも大きく影響する重要なポイントです。この判断には、建築基準法における道路と接道義務が鍵を握ります。
道路は、通行のためだけでなく、日照・通風の確保や緊急時の避難路としての役割も担います。このような道路の役割を規定する法律には、民法、道路法、そして建築基準法があります。民法は囲繞地通行権(人の通行権)に焦点を当て、道路法は道路の管理に関して定めています。
建築基準法では、建物の利用者のために、日照、通風、安全を確保する目的の道路を規定しています。建築基準法で定める道路に2m以上接道していないと、建物を建てることはできません。具体的には、幅員4m以上の道路に2m以上接道することが必要です(建築基準法第42条・43条)。4mの幅員は、車がすれ違うためや、救急車や消防車などの緊急車両が通行可能な幅を意味します。2m以上接道するとは、道路に十分に隣接している状態を指します。
ただし、この接道義務は都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用され、都市計画区域外では適用されません。このため、郊外の地域では道路に直接接していない家も見られます。
道路の範囲と幅員について、道路幅員は実際に通行している部分の長さを指し、側溝は幅員に含まれますが、水路は原則として含まれません。道路に接しているかどうかの判断は、外観だけでなく、公図を確認して行う必要があります。
最終的に、不動産が接道義務を満たしているかどうかの調査は、その土地が建築基準法上の道路に適切に接しているかを確認するために重要です。
建築基準法42条の解説、道路とは何か
建築基準法第42条は建築基準法における道路を規定しています。
建築基準法42条1項
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
建築基準法42条柱書
建築基準法における「道路」とは、具体的に建築基準法第42条1項で定められた道路の種別を指します。この法律における道路の種類は以下の通りです:
- 幅員4m以上の道路(42条1項1号): 国や都道府県、市町村等が管理し、路線認定を受けた道路。これは「道路法上の道路」と呼ばれます。
- 42条1項2号の道路: 都市計画法等に基づく道路で、一般に「開発道路」として知られています。
- 42条1項3号の道路: 建築基準法施行時の基準日(昭和25年11月23日)に既に存在した道路。これらは「既存道路」と称されます。
- 42条1項4号の道路: 2年以内に完成予定の道路。これらは「計画道路」と呼ばれています。
- 42条1項5号の道路: 基準日以降に私人によって作られ、位置指定を受けた道路。これらは「位置指定道路」として区分されます。
これらの道路の種類と特徴を理解することは、建築基準法における接道義務を遵守するために不可欠です。
建築基準法42条1項1号(道路法条の道路)
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路建築基準法42条1項
建築基準法42条1項
「建築基準法42条1項1号道路」とは、幅員4m以上であり、道路法の規制を受ける公道を指します。これは一般に「道路法上の道路」と呼ばれ、国道、県道、市道、区道など、国や都道府県、市町村によって認定および管理される道路を含みます。
この種の道路は、建築基準法上の道路であり、同時に道路法上の道路でもあります。ただし、建築基準法上の道路と道路法上の道路は、それぞれ異なる目的を持っています。
所有者が市町村であり、幅員4m以上あり、建築基準法上の道路でない場合公衆用道路として登記されている道路でも、建築基準法上の道路と認められないケースが存在します。この場合、そこに家を建てることはできません。建築基準法上の道路とは、建物を利用する人々のために日照や通風、安全性を確保する観点から、住宅建築が許可される道路を指します。4mの幅は、車同士のすれ違いや緊急車両の通行に必要な最低限の幅です。
一方で、道路法上の道路は、歩行者や車両の安全な通行を保証するために、行政が管理する道路です。道路法上の道路が、建築基準法上の道路としての要件を満たす場合、それは42条1項1号道路と認められます。
中古物件の場合、一般的な道路が42条1項1号道路に該当し、不動産の間口がこの道路に2m以上接していれば、建築が許可されます。
しかし、この接道義務は都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用され、それ以外の地域では適用されません。これが田舎地域で道路に接していない家が存在する理由です。
建築基準法42条1項2号(開発道路)
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
建築基準法42条1項2号
「建築基準法42条1項2号道路」は、主にデベロッパー(開発業者)による大規模な宅地開発の際に造られる道路を指します。これらの道路は、接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道する必要がある)を満たすために設計され、通常、原則として幅員6m以上が求められます。
このカテゴリの道路は「開発道路」として知られており、初めは開発業者の所有する「私道」として機能します。多くの場合、開発完了後に地方自治体に寄付され、公道(42条1項1号道路)に変わります。
42条1項2号道路は、役所に引き継がれるまでの過渡期に存在する幅員4m以上の私道と見なすことができます。特に新築の分譲住宅を購入する際にはこの種の道路が見られますが、中古物件ではあまり一般的ではありません。
ただし、引き継ぎが行われない場合もあり、このような場合は道路は私道のままとなります。私道であっても、42条1項2号道路は建築基準法上の道路として認識され、不動産の間口が2m以上接していれば、建物の建築や建て替えが可能です。
しかし、私道のみに接する不動産の場合、将来の建て替え時に上下水道やガス管の工事を行う際には、道路の所有者から掘削に対する同意や承諾、場合によっては料金を求められることがあります。
また、42条1項2号道路と42条1項5号道路(位置指定道路)は、いずれも宅地開発された分譲地内の道路ですが、42条1項2号道路は道路法上の道路となることが前提で、原則として6m以上の幅員が必要です。一方、42条1項5号道路は接道義務の充足を目的とし、原則4m以上の幅員で問題ありません。
開発許可の要否によって、大規模開発は42条1項2号道路、小規模開発は42条1項5号道路と分類されることがあります。
これらの接道義務は42条1項1号と同じく、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用され、それ以外の地域では適用されません。これが、田舎地域で道路に接していない家が見られる理由です。
建築基準法42条1項3号(既存道路)
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
建築基準法42条1項3号
42条1項3号道路は、建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前から存在し、幅員が4m以上の道路を指します。これらの道路は国道・県道・市道・区道ではなく、国や都道府県、市町村によって認定または管理されていないものが含まれます。これらの道路は「既存道路」として知られています。
この種の道路があなたの不動産の間口に2m以上接している場合、現在も幅員が4m以上あり、周囲の建物と整合性がある場合、役所は通常、そのままの幅員で家を建てることを許可します。
しかし、他人が所有する(私道である)42条1項3号道路にのみ接している不動産の場合、今後の建て替え時には、上下水道管やガス管の引き込み工事を行うために道路の所有者からの掘削同意や承諾、場合によっては掘削承諾料の支払いが必要になる可能性があります。(接道義務とは別)
役所が「家を建てても良い」との判断を下した場合は、その道路が住宅建築に問題ないと認識されていることを意味します。
特記事項として、42条1項3号道路かどうかの判断基準日は、当該地域が建築基準法施行以前から都市計画区域である場合は1950年11月23日となります。しかし、この日以降に都市計画区域に指定された地域では、指定日時点での道路の存在が基準となります。
これらの接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用され、それ以外の地域では適用されません。そのため、都市計画区域外では道路に接していない家が見られることがあります。
建築基準法42条1項4号(計画道路)
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
建築基準法42条1項4号
42条1項4号道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法または密集市街地整備法に基づいて計画され、新たに造られる予定の道路、または既存道路の変更(拡幅)を行う道路を指します。一般的には、都市計画道路が事業決定され、都市計画施設に該当する敷地が買収されると、その敷地は42条1項4号道路になります。この指定は2年以内に事業が執行される予定のものですが、予定通りに進行しない場合でも、指定が取り消されない限り効力を持ち続けます。
役所での調査においては、調査物件及び近隣の建築計画概要書を確認し、道路の状況を把握します。特に、都市計画道路の「事業決定済かつ買収済」の状態であれば、42条1項4号道路になっている可能性が高いです。また、指定道路調書や拡幅予定線図などの資料を確認することが重要です。
ただし、買収後に42条1項4号道路として告示されるまでにタイムラグがある場合、該当する土地はまだ建築基準法上の道路ではない点に注意が必要です。この状態では、建物の建築は不可というわけではありませんが、具体的な建築許可の可否は役所に確認することが必要です。
都市計画道路が計画決定段階か事業決定段階かによって、調査する項目が異なります。計画決定段階では、計画道路の名称・番号、幅員、決定年月日、告示番号、建築制限の確認、特例許可の有無、事業化優先路線や公拡法届出の対象などを確認します。一方、事業決定段階では、計画道路の進捗状況や建築許可の有無などを調べます。
42条1項4号道路は、現在は道路ではないが将来道路になる予定の土地を指し、「計画道路」や「大規模開発道路」とも呼ばれます。都市計画道路には幹線道路などが多く含まれ、その幅員は通常20m、30mなど大きなものが多いです。この土地に建物を建築することは基本的に許可されませんが、計画決定段階では条件付きで建築が可能な場合もあります。
ただし、接道義務は都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用され、それ以外の地域では適用されません。そのため、都市計画区域外では道路に接していない家が見られることがあります。
建築基準法42条1項5号(位置指定道路)
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
建築基準法42条1項5号
42条1項5号道路は、都市計画法等に基づく開発許可によって造られる道路(42条1項2号道路)ではなく、民間の私人、例えば不動産業者などが、宅地造成を目的として造る道路です。当初は「私道」として造られますが、後に役所に寄付され、「公道」となり、42条1項1号道路に変わることもありますが、役所に引き継がれないケースも多くあります。
役所での調査では、「建築計画概要書」と共に「位置指定申請図」や「位置指定道路廃止(変更)図」を入手し、位置指定道路図(道路位置図)、地積測量図、現地状況を照らし合わせて確認します。位置指定年月日、位置指定番号、位置指定内容(指定幅員、指定延長、自動車転回広場、道路断面図)を特に確認することが重要です。建築指導課にて、図面と現地状況の一致についてヒアリングすることが推奨されます。
42条1項5号道路の指定基準には、以下の条件が含まれます:
- 道路は通り抜けが可能である必要がありますが、例外として道路延長が35m以下、幅員が4m以上、突き当りが自動車転回が可能な広場であれば行き止まりでも許容されます。35mを超える場合は自動車転回用スペースが必要です。
- 接続する道路との交差部は隅切りを行う必要があります。
- 道路は砂利敷きやぬかるみにならない構造である必要があり、通常アスファルトで敷かれます。
- 道路傾斜は一定以下であり、階段状でないこと。
- 排水のための側溝等の設置が必要です。
42条1項5号道路は、主に小規模な開発において見られ、開発許可が不要な場合の4m以上の道路に該当します。開発業者が自らの所有地に造る道路であり、建築基準法上の道路として認識されるため、道路に2m以上接していれば家を建てることが可能です。
ただし、役所からの「位置指定申請図に従った現地復元」の指導があり得るため、現地の状況と位置指定図が一致しているかを確認する必要があります。この場合の復元とは、建築基準法上の条件に満たない場合において、これらの条件を満たすようにセットバックを行ったり、外壁を取り壊すことなどを言います。
42条1項5号道路と42条1項1号道路の両方が重なる場合、再建築の際には位置指定道路としての復元義務が生じる可能性があります。このような状況においては、役所に個別案件ごとに確認することが必要です。
接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見られるのはこの理由によります。
建築基準法42条2項(2項道路・みなし道路)
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法42条2項
建築基準法42条2項に定められる道路は、建築基準法施行日の1950年(昭和25年)11月23日以前から存在し、幅員が4m未満の道路です。これらの道路は、都市計画区域等の指定・変更等により建築基準法第3章の規定が適用された時点で既に存在していたものですが、幅員が4m未満のため、建築の際には敷地後退(セットバック)が必要になります。
この種の道路は「2項道路」または「みなし道路」と呼ばれ、救済措置としてすでに建物が建っていた場合は4m未満でも建築基準法上の道路として認められています。しかし、新たに建物を建築する際には、幅員4m以上の道路にするためにセットバックが必要です。
セットバックによって道路部分として提供される敷地は、建築物の敷地面積に含めることができず、建ぺい率や容積率の計算はセットバック部分を除いた面積を基に行われます。セットバックされた道路部分には、建物だけでなく門や塀も建築できません。
敷地後退(セットバック)の必要性は、土地の実際の利用面積を減少させ、不動産価値に影響を及ぼします。特に道路の反対側が川や崖、線路などの場合は、どのように後退する必要があるか注意が必要です。
また、幅員4m以上の42条2項道路も存在し、セットバック済みであれば道路幅員は4mあるはずですが、現況幅員が4m以上でも42条2項道路であればさらにセットバックが必要かどうかを確認することが重要です。
調査方法に関しては、役所で42条2項道路の後退方法(セットバックか一方後退か)を確認し、関連する地積測量図や建築計画概要書を参考にします。道路中心線の位置確認や、セットバックまたは一方後退する場合の具体的な方法についても、役所に確認が必要です。
この接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用され、都市計画区域外では適用されません。田舎で道路に接していない家が見られるのはこのためです。
建築基準法42条3項(水平距離指定道路・3項道路・42条2項道路の特例)
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
建築基準法42条3項
建築基準法42条3項には、特定の状況下で幅員が2.7mまで緩和される道路が定められています。これは42条2項道路(昭和25年11月23日以前から存在していた幅員4m未満の道路)の特例として存在します。土地の状況により、将来的にも4m幅員を確保することが不可能な場合に適用され、特に狭い場合は1.35mのセットバックで2.7mの道路幅を確保する「水平距離指定道路」や「3項道路」とも呼ばれます。
この特例の道路は、傾斜地や線路、河川、公園に沿う地形など、物理的に道路拡幅が困難な場所に設けられることが多いです。また、古くからの市街地内で自動車の通行が少なく、歴史的な町並みを保持する必要がある場合にも指定されることがあります。これにより、建物の建替え時にも現状の道幅を維持し、街並みの雰囲気を保持することが可能になります。
42条3項道路の指定は、建築審査会の同意を必要とし、厳密な手続きを要求されます。これにより、建物の前面部分の保存が可能となり、街並み自体の破壊を防ぐことができます。
セットバックに関しては、道路中心線から1.35mの敷地後退が必要で、この部分は建築物の敷地面積に含めることができず、建ぺい率や容積率の計算に影響を及ぼします。このため、建物の再建築計画を立てる際には、土地の実際の利用面積や不動産価値にも影響を与えることになるため、慎重な調査が必要です。
調査方法についての詳細は、「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明されていますので、参照すると良いでしょう。
建築基準法42条4項(6m区域内の特例)
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
建築基準法42条4項
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
建築基準法42条4項では、特定の区域内で幅員6m未満でも4m以上ある道路が、特定行政庁によって指定される場合があります。これらは6m区域内で例外的に建築基準法上の道路として認められる道路です。6m区域は、法律で定義された用語ではなく、通称で、この区域内では通常、道路は幅員6m以上が最低基準とされています。42条1項柱書きに()内に、「特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。」と記載がされています。
しかし、実際には6mの幅員を確保することが現実的に困難な場合もあるため、特定行政庁が地域の気候や風土、土地の状況を考慮し、特定の基準に基づいて幅員4m以上の道路を建築基準法上の道路として指定することができます。これにより、例えば積雪地域での除雪の必要性や、整然とした街並みを形成するための柔軟な対応が可能になります。
42条4項道路は、以下のようなケースで建築基準法上の道路として認められることがあります:
- 避難や通行に支障がないと認められる幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定を受けた場合。
- 地区計画等に適合する幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定を受けた場合。
- 6m区域指定時に既に建築基準法上の道路とされていた道路(幅員にかかわらず)。
実際の6m区域の指定例は限られており、多くの場合は「幅員4m以上」の基準が適用されます。しかし、例外的に42条4項道路の指定が行われることがあります。例えば、埼玉県春日部市では建築基準法第42条第1項に基づく幅員6メートルの区域を指定し、この特例を適用しています。
建築基準法42条5項(6m区域内の特例)
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法42条5項
建築基準法42条5項では、特定の条件下で6m区域内において幅員4m未満の道路が例外的に認められる場合が定められています。これは、本来6mが最低基準とされる6m区域内で、特定の状況下において幅員4m以上の道路が認められる特例です。6m区域は、通称で用いられる表現であり、法律上の明確な定義はありませんが、一般的には6m以上の幅員が必要とされる区域を指します。
この区域内では、建築基準法第42条1項に基づき、幅員4m以上の道路が必要ですが、地方の気候や風土、土地の状況に応じて、都道府県都市計画審議会の議を経て、特定行政庁により6m以上の幅員が求められる場合があります。しかし、現実には6mの幅員を確保することが困難なケースもあり、このような場合に42条5項の例外規定が適用されることがあります。
42条5項道路は、以下のような条件で建築基準法上の道路として認められます:
- 特定行政庁が指定した避難や通行上支障がないと認められる幅員4m以上の道路。
- 地区計画等に適合する幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定を受けた場合。
これにより、6m区域内であっても、例外的に4m未満の道路が許容される場合があります。ただし、6m区域の実際の指定は少なく、42条5項道路の指定例も限られています。また、6m区域内の2項道路におけるセットバック距離は通常3mですが、特定の状況下ではこの要求が緩和されることがあります。
建築基準法42条6項(6項道路・2項道路の特例)
6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
建築基準法42条6項
建築基準法42条6項は、特に狭い道路に関する特例を定めています。この項目では、建築基準法施行日の1950年(昭和25年)11月23日以前から存在していた幅員が4m未満、具体的には1.8m未満の道路について規定しています。これらの道路は、原則として建物の建築が難しいため、救済措置として特別な取り扱いがなされています。
通常、4m未満の道路に接している土地では、建築基準法により建物の建築が許可されません。しかし、42条2項道路として、すでに建物が建っている場合は例外的に建築が認められることがあります。これらの道路は「2項道路」または「みなし道路」とも呼ばれ、建物の再建築の際には、道路幅員を4m以上にするための敷地の後退(セットバック)が必要です。
42条6項道路は、42条2項道路の中でも、現状の幅員が特に狭い1.8m未満の道路を指します。これらの道路は「6項道路」と通称され、建築審査会の同意が必要です。6項道路は、建築基準法上では「42条2項道路」として扱われますが、特別な条件下でのみ建築が許可されます。
例えば、滋賀県大津市の柴屋町遊郭跡地周辺のような、昔の狭小な街路が多い街区では、6項道路の指定が救済措置として用いられることがあります。このような地区では、歴史的な町並みを維持しつつ、建物の建替えや修繕が可能になるように考慮されています。
42条とその後の確認手続き
建築基準法上の道路の確認が完了したら、関連する資料や図面の取得が重要です。これには建築計画概要書や検査済証(台帳記載証明書)などが含まれます。また、道路の種類に応じて、位置指定申請図、位置指定廃止図、指定道路調書、道路中心線図なども必要になります。
不動産売買契約時に必要な重要事項説明書では、「敷地等と道路との関係」の項目で、その道路が「公道」か「私道」かを記載します。土地の所有者によって公道か私道かが判断されるのが一般的ですが、市道管理されていない公道や、私有地であっても市道管理されている道路も存在します。したがって、役所でいう「公道」と一般的な定義は必ずしも一致しないことに注意が必要です。
市が管理する道路の種類は主に次の3つです:
- 市道として認定されている道路(道路法に基づく)。
- 道路部分の土地寄付がなくても、無償使用承諾書に基づき市道として認定され、市が表面管理を行う道路。
- 市道の認定はないが、市有通路や認定外道路などとして市が管理する通路。
取得可能であれば、道路台帳平面図、土地境界図、道路区域図を取得し、市道の名称や路線番号、認定幅員を確認します。
2m接道しているかどうかの確認は現地調査が必要です。境界に関する知識を持ち、適切な調査方法を用いて、敷地と道路との接続状況を確かめる必要があります。具体的な現地調査方法については、「土地の境界の不動産調査方法」で詳しく説明されていますので、参照すると良いでしょう。
建築基準法第43条(接道義務) の解説
建築基準法43条1項(接道義務の原則)
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
建築基準法43条1項1号、2号
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
建築基準法第43条1項に定められた接道義務は、建物の敷地が4m以上の幅員を有する建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。この規定は、道路が公道であるか私道であるかには影響されません。重要なのは、道路が建築基準法上の道路であり、その幅員が4m以上であることです。
また、敷地内に建築物を建てる際、道路に面する間口は2m以上必要です。ただし、マンションなどの大規模建築物の場合、接道義務は6m以上となり、接道の長さの基準も異なります。
この接道義務は、「都市計画区域」や「準都市計画区域内」の建築物に適用されます。逆に、都市計画決定されていない区域、すなわち都市計画区域外では、接道義務は発生しません。これは、都市計画区域内で安全な環境を確保し、整備された開発を促進するための措置であり、整備の必要性がない都市計画区域外では適用されないためです。
接道義務は、1950年(昭和25年)の建築基準法制定時から設けられており、その主な目的は建築物が道路に接していない場所に立ち並ぶことを防ぐためです。これにより、地域住民の快適な生活や緊急車両の通行を確保し、特に災害時の救命活動や消火活動に必要な空間を提供することを目指しています。
「旗竿地」に関しても注意が必要です。旗竿地は、道路に接している部分だけでなく、敷地全体が2m以上の幅員を有していなければ、建築確認申請の許可が下りず、建物を建てることができません。このため、旗竿地の購入や建築計画を立てる際には、接道義務を満たしているかを確認することが重要です。
建築基準法43条2項(但し書き通路)
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
建築基準法43条2項柱書
建築基準法43条2項は例外規定となっています。いわゆる2項道路、というもので、2項道路に該当すると接道義務が免除され再建築可能な不動産となります。
建築基準法43条2項1号、2号
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
建築基準法43条2項1号,2号
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
建築基準法第43条2項には、特定の条件下で接道義務を満たさない敷地でも建築が許可される「みなし道路」の規定が含まれています。これらの道路は、「43条但し書き道路」とも呼ばれ、以下のようなケースで建築審査会の許可を得て建築が認められます:
- 敷地の周囲に公園や緑地などの広い空地がある場合。
- 建築基準法上の道路ではないが、農道など公共用途に供される道路に接している場合。
- 建築基準法上の道路に通じる通路に接しており、避難通行上安全と認められる場合。
特定行政庁は、交通上、安全上、防火上、衛生上の面で支障がないと判断し、建築審査会の同意を得て許可することによって、これらの条件を満たさない敷地にも建物を建築することを可能にします。接道義務を満たさない土地は通常、建築が許可されないため、43条但し書き道路の規定は、そうした敷地に対する救済措置として機能します。これにより、特定の条件を満たす土地においても、建築計画が進められる可能性があります。

建築基準法43条2項但書きについては下記のブログに詳細の記載がございますので、ぜひご覧ください。
建築基準法43条3項(その他の市区町村独自の基準)
地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
一 特殊建築物
建築基準法43条3項
二 階数が三以上である建築物
三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
建築基準法第43条3項では、特定の用途や規模に特殊性を持つ建築物に関して、市区町村が独自に敷地と道路との関係に関する追加の制限を設けることができます。この規定は、特定の建築物に対して標準的な接道義務規定が適切でない場合に適用されるものです。
例として、群馬県建築基準法施行条例には、以下のような条項が設けられています:
- 第6条(大規模の建築物の敷地と道路との関係):大規模建築物に対する敷地と道路との関係に特別な規定を設ける。
- 第7条(路地状敷地):路地状の敷地に関する特別な規定。
- 第9条の2(劇場等の敷地と道路との関係):劇場など特定の用途を持つ建築物に対する敷地と道路との関係に関する規定。
- 第21条(物販店舗の敷地と道路の関係):物販店舗に関する敷地と道路との関係に特別な規定を設ける。
これらの条例による規制は、建築基準法上の「道路」とみなされる道に面して建てられる建築物が、前面道路の幅員に関する容積率規制や道路斜線制限に適合している必要があります。このように、建築物の用途や規模に応じて、市区町村は建築基準法の一般的な規定に加えて、独自の制限を設けることが認められています。これにより、地域の特性や安全性、利便性を考慮した適切な建築規制が可能になります。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)


とは?再建築不可物件の救済措置!-160x90.png)

とは?再建築不可物件の救済措置!-120x68.png)