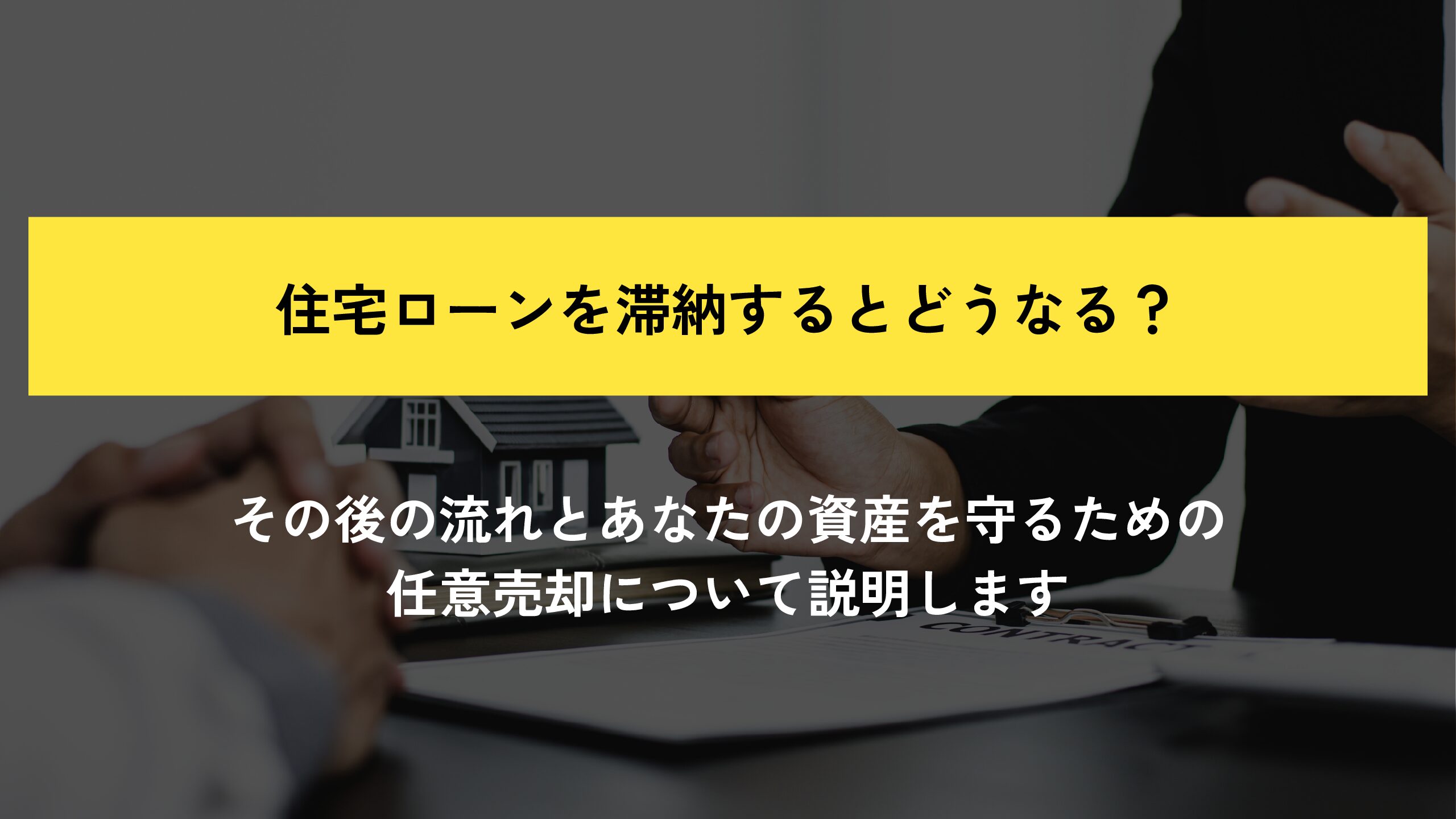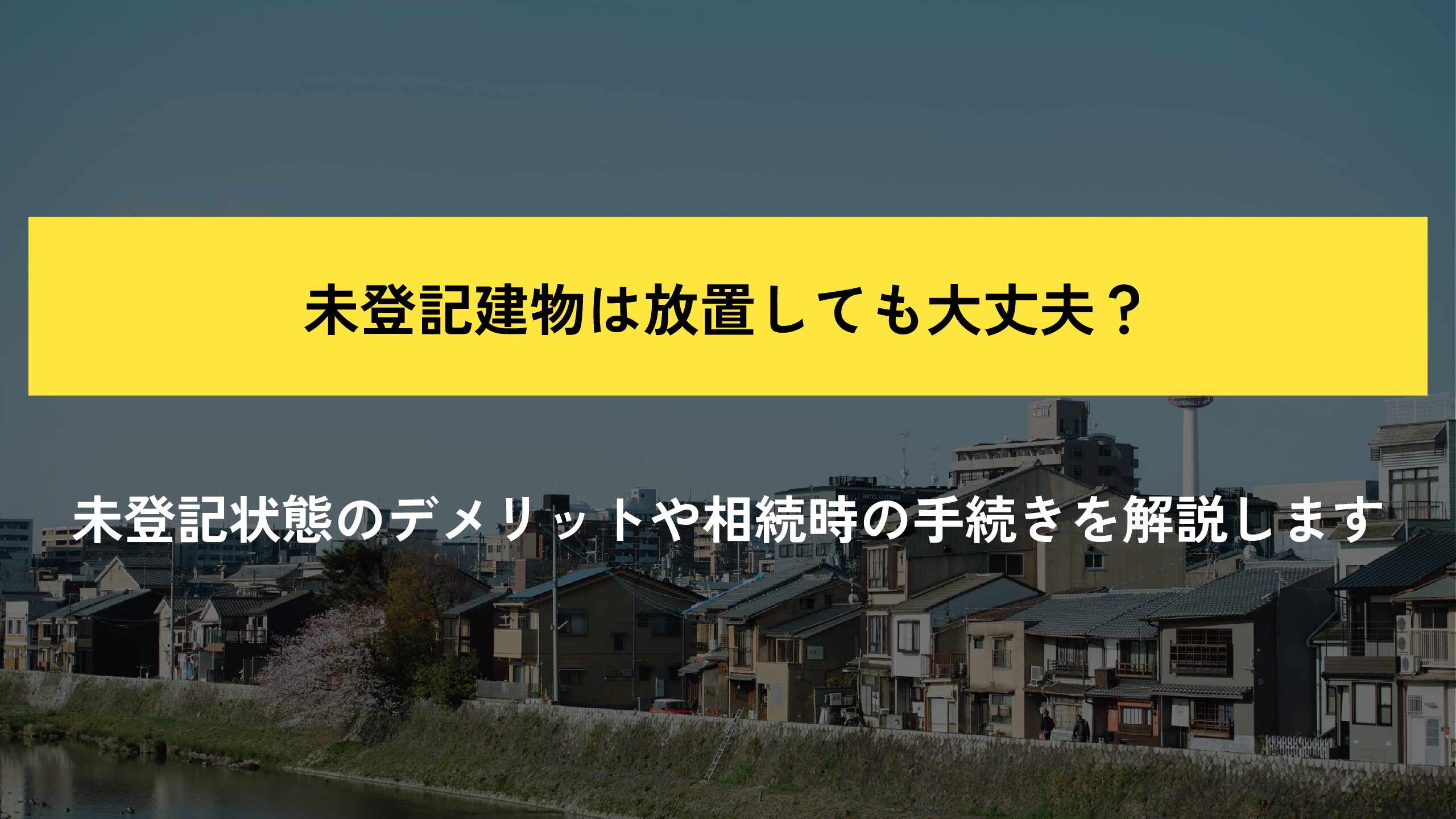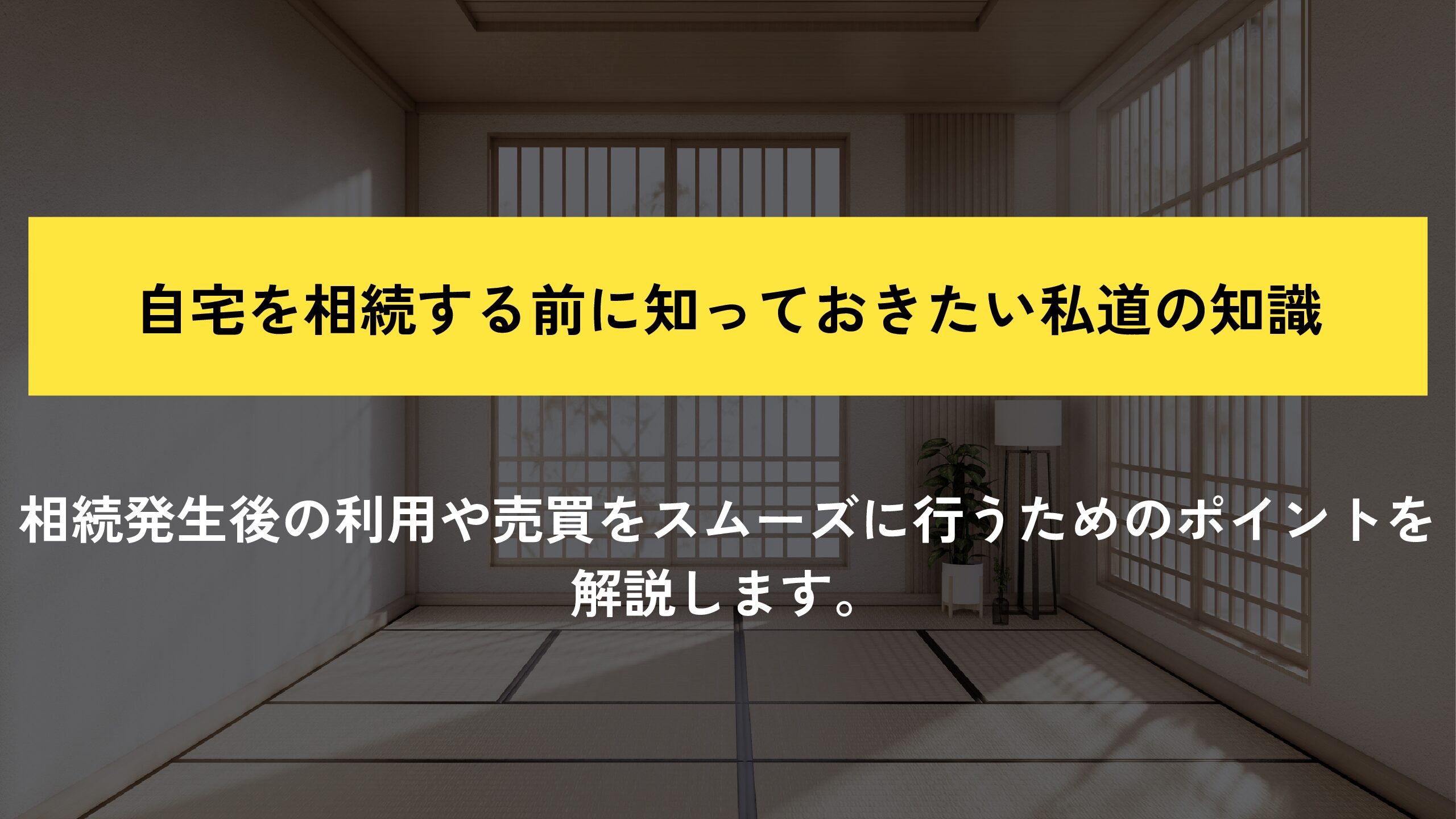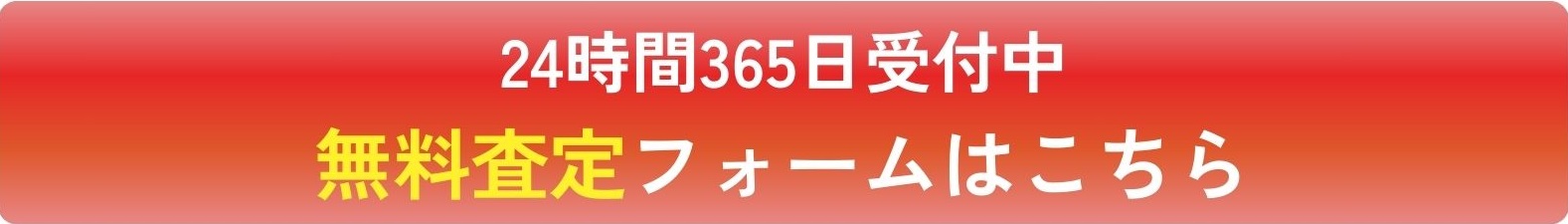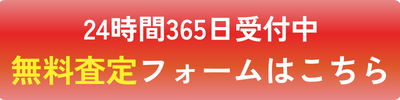「住宅ローンの返済が苦しい…」
そんな状況に陥ってしまった時、一体何が起こるのか、あなたは知っていますか?
放置すると、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。
住宅ローン滞納で起こる恐ろしいこと
- 遅延損害金が発生する: 滞納期間が長引くほど、雪だるま式に膨らんでいきます。
- 期限の利益喪失で一括返済を求められる: 分割返済の権利を失い、残りのローンを一括で支払わなければならなくなります。
- ブラックリストに載り、新たな借入が困難に: 信用情報に傷がつき、クレジットカードの利用や新たなローンの借り入れが難しくなります。
- 競売で強制退去: 最悪の場合、自宅が競売にかけられ、強制的に退去させられる可能性があります。
これらのリスクを回避するためには、早期の対応が重要です。
中でも、任意売却は、あなたの大切な家を、あなたの意思で守るための有効な手段です。
滞納初期(1ヶ月から3ヶ月)
うっかり残高不足や、仕事や家庭の事情で住宅ローンの返済が遅れてしまうこと、誰にでもありますよね。でも、そんな時、金融機関はどう対応するのでしょうか?
一般的には、返済日から1か月ほど経つと、金融機関から電話やメールで連絡が来ます。慌てずに、まずは事情を説明し、いつまでに支払えるか伝えましょう。
1か月程度の遅れであれば、金融機関も事情を考慮してくれることが多いです。ただし、金融機関によっては、数日遅れただけでも遅延損害金や延滞利息が発生する場合があります。
なので、返済が遅れそうな時は、早めに金融機関に相談することが大切です。
遅延損害金とは?
住宅ローンの返済が遅れてしまうと、「遅延損害金」というペナルティが発生します。これは、約束の期日までに返済できなかった場合に、借り手(債務者)が貸し手(債権者)に支払う損害賠償金のことです。
遅延損害金は、住宅ローン契約時に締結する「金銭消費貸借契約」に記載されており、一般的には年14.6%という高めの利率で設定されています。この利率は日割り計算で適用されるため、たとえ1日でも返済が遅れれば、その分の遅延損害金が発生してしまいます。
遅延損害金は、「遅延利息」や「延滞利息」とも呼ばれます。住宅ローンの契約書には、以下のような文言で規定されていることが多いです。
「元利金の返済が遅れたときは、お客様は返済の遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の遅延損害金を支払うものとします。」
つまり、返済が遅れた場合、遅延している元金に対して日割りで遅延損害金が計算され、請求されるということです。
例えば、100万円の元金の返済が1日遅れた場合、100万円 × 14.6% ÷ 365日 = 約40円の遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、返済が遅れた元金に対してのみ発生し、利息部分には発生しません。
遅延損害金の計算方法
- 遅延損害金 = 借入残高 × 遅延損害金利率 × 遅延日数 ÷ 365日
【計算例】
- 住宅ローンの元金部分:8万円
- 遅延損害金利率:15%
- 滞納日数:15日
この場合、遅延損害金は 8万円 × 15% ÷ 365日 × 15日 = 約500円 となります。
短期の遅延でも油断は禁物!
短期間の遅延であれば、遅延損害金自体は少額かもしれません。しかし、金融機関からの信用低下につながる可能性があるため注意が必要です。
通常、遅延損害金は次回の請求額に上乗せされます。遅延しないように、余裕を持った返済計画を立てましょう。
督促状が届く
督促状には、毎月の返済額に加えて遅延損害金が上乗せされた支払い請求書が同封されていることが多いです。督促は、はがきや手紙だけでなく、電話で行われる場合もあります。
この時期の督促は比較的穏やかですが、信用情報機関にはすでに滞納情報が登録されています。たとえ1か月分の滞納であっても、信用情報に傷がつく可能性があるため注意が必要です。
3か月以上の滞納や、短期間の滞納の繰り返しは、金融機関から要注意先とみなされる原因となります。いわゆるブラックリスト入りの状態です。ブラックリスト入りすると、クレジットカードの審査落ちや新規借り入れの制限など、様々な不利益が生じる可能性があります。
住宅ローンだけでなく、自動車ローン、クレジットカード、携帯電話料金などの滞納も、住宅ローンの利用に悪影響を及ぼす可能性があります。
住宅ローン滞納3~4か月で状況が深刻化!
住宅ローンの支払いが3~4か月滞ると、銀行から催告書が届きます。催告書の内容は、これまでの督促状よりも厳しく、「期限までに滞納額を支払わないと、分割返済の権利を失い、一括返済を求める」といった警告が記載されます。場合によっては、2か月程度の滞納で催告書が届くこともあります。
ここで重要なのが「期限の利益の喪失」という言葉です。これは、住宅ローンを分割で返済する権利を失うことを意味します。つまり、残りのローン残高を一括で支払わなければならなくなるのです。
一括返済が困難な場合、最悪の場合、自宅が競売にかけられる可能性もあります。こうなると、自宅を失うだけでなく、残った借金を払い続ける必要も出てきます。
滞納が3~4か月に及ぶと、状況は非常に深刻です。もし支払いが困難な場合は、すぐに銀行に相談し、解決策を模索しましょう。専門家の力を借りることも有効です。
住宅ローン滞納5~6か月で期限の利益喪失!
住宅ローンの支払いが5~6か月滞ると、「期限の利益喪失通知」が届きます。これは、分割返済の権利が完全に失われたことを意味し、残りのローン残高を一括で返済する義務が生じます。場合によっては、4か月程度の滞納で通知が届くこともあります。
一括返済の相手は、保証契約の有無によって異なります。
- 保証契約がある場合: 保証会社が一括返済を引き受け、その後、あなたに対して返済を求めます。
- 保証契約がない場合: ローンを借りた金融機関に直接、一括返済しなければなりません。
住宅ローン滞納6~7か月で保証会社が介入!
住宅ローンの支払いが6~7か月滞ると、保証会社を利用している場合は「代位弁済通知」が届きます。これは、保証会社があなたの代わりに住宅ローンの残金を銀行に支払ったという通知です。これにより、返済相手が銀行から保証会社に変わります。
保証会社を利用していない場合は、ローンを借りた金融機関から直接、一括返済の請求が来ます。
いずれの場合も、その後、残りのローンや遅延損害金などを一括返済できなければ、最悪の場合、自宅が差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。
代位弁済とは?
代位弁済とは、保証会社が債務者(あなた)の代わりに債権者(銀行)に借金を支払うことです。これにより、保証会社はあなたに対して、支払った金額の返済を求める権利を持つことになります。
住宅ローン滞納8~9か月で競売申し立て!
住宅ローンの支払いが8~9か月滞り、保証会社への返済も滞ると、金融機関や保証会社は裁判所へ「競売の申し立て」を行います。
競売申し立てとは?
競売申し立てとは、住宅ローンなどの借金を返済できない場合に、債権者(金融機関や保証会社)が裁判所を通じて、担保となっている不動産(自宅など)を強制的に売却する手続きを開始することです。
競売申し立てが認められるとどうなる?
競売申し立てが認められると、対象の不動産が差し押さえられます。差し押さえられた不動産は、所有者の自由な処分が制限され、債権者の管理下に置かれます。
すぐに退去させられるわけではない
不動産が差し押さえられても、すぐに強制退去させられるわけではありません。しかし、競売手続きが進むと、最終的には自宅を明け渡すことになります。
住宅ローン滞納9~10か月で競売開始!
住宅ローンの滞納が9~10か月に及ぶと、競売手続きが本格的に始まります。
競売開始決定通知
競売の申し立てから数週間で、裁判所から競売開始決定通知が届きます。これは、競売手続きの開始を知らせるもので、拒否することはできません。
現況調査通知
競売開始決定通知の後、裁判所から現況調査通知が届きます。これは、裁判所の執行官と不動産鑑定士が物件を調査し、競売の基準価格を決定するためのものです。
入札期間の通知と競売の開始
現況調査が終わると、入札期間の通知があり、約1週間~1か月ほどで競売物件が一般公開されます。その後、入札期間中に競売が行われ、最高額で入札した人が落札者となります。
競売の確定と所有権の移転
落札者が代金を納付し、裁判所が所有権移転と抵当権抹消の登記手続きを行うと、競売が終了し、物件は落札者の所有となります。
住宅ローンの滞納を防ぐ5つの方法
住宅ローンの滞納は、深刻な事態を引き起こす可能性があります。しかし、事前に対策を講じることで、滞納を未然に防ぐことができます。以下に、5つの効果的な対処法を紹介します。
- 収支を見直す
家計の収入と支出を細かく確認し、無駄な支出を減らす努力をしましょう。固定費の見直しや節約を心がけることで、返済に充てる資金を増やすことができます。
- 金融機関に相談する
返済が困難だと感じた場合は、すぐに金融機関に相談しましょう。返済計画の見直しや、一時的な返済額の減額など、状況に応じた対応策を提案してもらえる可能性があります。
- 住宅ローンを借り換える
現在の住宅ローンの金利が高い場合は、借り換えを検討しましょう。金利が低いローンに借り換えることで、毎月の返済額を減らすことができます。
- 公的な融資制度を利用する
自治体や国の融資制度を利用することで、低金利で借り換えができる場合があります。条件に該当する場合は、積極的に活用を検討しましょう。
- 専門家に相談する
ファイナンシャルプランナーや弁護士などの専門家に相談することで、より具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。
競売を回避!任意売却で自宅を守る
住宅ローンの返済が困難になった場合、まず考えられるのが自宅を売却してローンを完済する方法です。しかし、売却してもローンが残ってしまう場合は、任意売却を検討することになります。
任意売却とは?
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった所有者が、金融機関の同意を得て、自宅を売却し、その売却代金をローン返済に充てる方法です。
メリット
- 市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い: 一般的な不動産売買と同じように売却活動を行うため、競売よりも高値で売れる可能性があります。
- 売却時期や条件を交渉できる: 金融機関と交渉することで、売却時期や引越し時期などを調整できる場合があります。
- 近隣住民に知られずに売却できる: 競売のように公にされないので、プライバシーを守ることができます。
デメリット
- 手続きに時間がかかる: 金融機関との交渉や手続きに時間がかかる場合があります。
- 残債が残る可能性がある: 売却代金でローンを完済できない場合、残債が残ることがあります。
競売とは?
競売は、裁判所が不動産を差し押さえ、強制的に売却する手続きです。
メリット
- 手続きが比較的早く進む: 裁判所の手続きに従って進められるため、任意売却よりも早く売却できる場合があります。
デメリット
- 市場価格よりも低い価格で売却される: 競売では、一般的に市場価格よりも低い価格で売却されるため、損失が大きくなる可能性があります。
- 売却時期や条件を選べない: 裁判所の手続きに従って進められるため、売却時期や条件などを自由に決めることはできません。
- 近隣住民に知られてしまう: 競売情報は公開されるため、近隣住民に知られてしまう可能性があります。
- 残債が残る可能性が高い: 売却代金でローンを完済できない場合、残債を一括で返済する必要があります。
任意売却と競売、それぞれのメリット・デメリット
| 特徴 | 任意売却 | 競売 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い | 市場価格よりも低い価格で売却されることが多い |
| 手続き期間 | 所有者と金融機関の合意形成が必要なため、時間がかかる場合がある | 裁判所の手続きに従って進められるため、比較的短期間で売却される |
| プライバシー | 近隣住民に知られずに売却できる | 近隣住民に知られてしまう可能性がある |
| 残債の処理 | 売却代金でローンを完済できない場合、残債の返済方法について金融機関と交渉できる | 残債は原則として一括返済となる |
| 所有者の意向 | 売却価格や時期など、ある程度所有者の意向を反映できる | 所有者の意向は反映されない |
任意売却の注意点:トラブルを避けるために知っておきたいこと
任意売却は、住宅ローンの返済が困難な状況でも、自分の意思で自宅を売却できる方法です。しかし、注意点を知らずに進めると、売却が完了しなかったり、売却後も生活に支障が出たりする可能性があります。
1. できるだけ早く売却活動を開始する
任意売却は、金融機関の同意を得て行いますが、いつまでも待つことはできません。なぜなら、任意売却と並行して競売の準備が進められることも珍しくないからです。
早期に売却活動を開始することで、希望に近い価格での売却や、残債の負担軽減の可能性を高めることができます。また、滞納期間が長引くほど遅延損害金も増えるため、早期売却は経済的な負担を減らすことにもつながります。
2. 任意売却物件の実績の多い業者を選ぶ
任意売却は、通常の不動産売買よりも複雑な手続きが必要です。法律や金融機関との交渉に詳しい、実績豊富な不動産会社を選びましょう。弁護士や司法書士と連携している会社であれば、より安心して任せることができます。
3. 信用情報に登録されるリスクがある
住宅ローンの滞納は、信用情報機関に遅延情報として登録される可能性があります。これは任意売却に限ったことではありませんが、今後の金融取引に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
4. 任意売却には期限がある
任意売却には、金融機関が設定した期限があります。多くの場合、競売の入札開始日の前日までに売却を完了する必要があります。期限内に売却できない場合は、競売にかけられてしまうため、早めの行動が重要です。
任意売却の期間と流れと手続き
任意売却の流れを事前に理解しておくことは、より早く、少しでも高く売るために非常に重要です。
この章では、任意売却が完了するまでの期間と流れを解説します。
任意売却の流れと期間の目安
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 金融機関からの督促 | 滞納後3~4か月 |
| 2 | 現状の把握(金融機関との相談・協議) | 数日 |
| 3 | 不動産会社の選定と価格の査定 | 約1~2週間 |
| 4 | 債権者(金融機関)への確認(売却活動中も継続) | 約1か月 |
| 5 | 任意売却の開始(販売活動) | 約1~3か月間 |
| 6 | 売買契約の締結 | 売却開始から約1~3か月 |
| 7 | 不動産の決済・引渡し | 契約から約1か月 |
| 8 | 残債務の返済(残債が残った場合) | ケースによって数年 |
ステップ1:金融機関からの督促
住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関から督促状や督促の電話が届きます。
もし返済が難しいと感じたら、この時点で金融機関に相談し、任意売却を検討し始めることをおすすめします。
放置すると、早ければ3か月、遅くとも6か月ほどで、保証会社(住宅ローンを借りる際に保証会社を利用している場合)から代位弁済の通知が届きます。
ステップ2:現状の把握(金融機関との相談・協議)
金融機関に連絡し、住宅ローンの滞納状況や残債額など、現状を詳しく把握しましょう。
返済が厳しい場合は、督促状が届く前に、できるだけ早く金融機関に相談することが重要です。
また遅くともこの段階で任意売却に詳しい専門業者や不動産会社に相談することをおすすめします。
不動産会社には事情を説明して、査定を依頼しましょう。また、金融機関によっては、任意売却を依頼できる不動産会社を紹介してくれる場合もあります。
ポイント
- 早期に金融機関に相談することが重要
- 専門家(不動産会社など)のアドバイスを受ける
- 任意売却に向けた査定を依頼する
ステップ3:不動産会社の選定と価格の査定
任意売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。任意売却に特化した実績やノウハウを持つ会社を選ぶようにしましょう。
査定の重要性
不動産会社に、任意売却を想定した査定を依頼します。この査定額は、売却価格設定の重要な参考資料となります。
売却価格設定のポイント
売却価格は、査定額や相場を参考に、金融機関と相談しながら慎重に決定します。
- 高すぎる売却価格: 売却までに時間がかかり、競売に移行してしまうリスクが高まります。
- 安すぎる売却価格: ローン残債が残ってしまう可能性が高まります。
不動産会社の選び方
任意売却は、通常の不動産売買よりも専門的な知識や経験が求められます。以下のポイントを参考に、信頼できる不動産会社を選びましょう。
- 任意売却の実績が豊富
- 金融機関との交渉に強い
- 弁護士や税理士と連携している
- 親身になって相談に乗ってくれる
また、こういった任意売却案件の不動産を買い取ってくれる不動産業者に相談することも一つの手です。
ステップ4:債権者(金融機関)の許可を得る
任意売却を行うには、金融機関の許可が不可欠です。売却価格、売却時期、売却後の残債の有無など、様々な条件について金融機関と交渉し、合意を得る必要があります。
売却活動中も、金融機関と密に連絡を取り合い、進捗状況を報告し、必要に応じて条件の調整を行います。
残債が残る場合の返済計画
売却代金でローンを完済できない場合、残債の返済計画についても金融機関と相談します。無理のない返済計画を立てることで、売却後も安心して生活を送ることができます。
ポイント
- 金融機関との交渉は、専門家(不動産会社など)に依頼することも考えましょう。
- 売却後も金融機関との関係は続くため、良好なコミュニケーションを心がけましょう。
- 残債の返済計画は、無理のない範囲で慎重に立てましょう。
ステップ5:任意売却の開始(販売活動)
金融機関の許可が下りたら、いよいよ任意売却の開始です。不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を行います。
売却活動の内容
任意売却でも、通常の不動産売買と同様に、以下のような活動を行います。
- 物件情報の公開: インターネットやチラシなどで物件情報を公開します。
- 内覧対応: 購入希望者に対して、物件内部を案内します。
- 価格交渉: 購入希望者と価格交渉を行います。
早期売却を目指そう
任意売却は、競売を回避するため、できるだけ早期に売却することが重要です。内覧の際には、物件を整理整頓し、好印象を与えるように心がけましょう。
売却期間の目安
媒介契約の種類によって異なりますが、専任媒介や専属専任媒介の場合、契約期間は最大3か月です。
価格変更の可能性
買い手が見つからない場合は、売却期間中に価格を下げるなどの条件変更が必要になることもあります。ただし、価格変更には金融機関の了承が必要ですので、不動産会社と連携して進めましょう。
ポイント
- 早期売却を目標に、積極的に売却活動を行う
- 内覧時には、物件を整理整頓し、好印象を与える
- 買い手が見つからない場合は、価格変更も検討する
ステップ6:売買契約の締結
買い手が見つかったら、売買契約を結ぶ前に金融機関と最終的な調整を行います。売却条件について金融機関の合意が得られれば、晴れて買い手と売買契約を締結できます。
スムーズな合意のためには、売却活動中も金融機関と密にコミュニケーションを取り、進捗状況を共有することが大切です。
任意売却ならではの特約
任意売却では、通常の不動産売買とは異なる特殊な状況を考慮し、売主であるあなたが不利益を被らないよう、以下の2つの特約を盛り込むことが一般的です。
- 債権者から合意が得られなかった場合の白紙解約特約
任意売却では、契約直前になっても、金融機関が売却を許可しない可能性があります。これは、債権者間の調整が難航したり、売却条件が金融機関の想定と異なったりする場合などに起こり得ます。
この特約があれば、万が一金融機関の合意が得られなかった場合でも、契約を白紙に戻すことができ、買い手から違約金を請求される心配がありません。
- 契約不適合責任の免責特約
通常の不動産売買では、売却後に物件に欠陥が見つかった場合、売主が責任を負う「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」があります。しかし、任意売却では、売主に修理費用などを負担する余裕がないことが多いため、この責任を免除する特約を設けます。
ポイント
- 売買契約前に金融機関と最終調整を行う
- 任意売却ならではの特約を盛り込む
- 金融機関とのコミュニケーションを密にする
ステップ7:不動産の決済・引渡し
売買契約が締結されたら、いよいよ不動産の決済・引渡しです。
決済・引渡し日
決済・引渡し日には、売主(あなた)と買主、金融機関、司法書士などが立ち会い、以下の手続きを行います。
- 売買代金の支払い: 買主が売主に対して売買代金を支払います。
- ローン残金の返済: 売主は受け取った売買代金で住宅ローンの残金を返済します。
- 抵当権の抹消: 住宅ローンが完済されたら、金融機関が抵当権を抹消します。
- 所有権の移転: 司法書士が所有権移転登記を行い、物件の所有権が売主から買主に移転します。
残債が残る場合
売却代金でローン残金を完済できない場合でも、物件の引渡しは行われます。ただし、残債の返済については、金融機関と改めて契約を結び、返済を継続する必要があります。
ポイント
- 決済・引渡しは、専門家(司法書士など)の立ち会いのもとで行われます。
- 残債が残る場合は、決済前に金融機関と返済計画について十分に話し合いましょう。
- 引渡し後は、速やかに物件を明け渡す必要があります。
ステップ8:残債務の返済(残債が残った場合)
任意売却後もローン残債が残ってしまった場合は、金融機関と相談し、無理のない返済計画を立てましょう。
返済計画のポイント
- 返済期間や返済額は、あなたの収入や支出を考慮して設定されます。
- 金融機関によっては、元金のみの返済や、金利の減免などの措置が受けられる場合があります。
- 返済が困難な場合は、債務整理などの方法も検討できます。
専門家のサポート
残債の返済については、弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも有効です。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な返済計画を立てることができます。
ポイント
- 金融機関と協力し、無理のない返済計画を立てる
- 必要に応じて専門家のサポートを受ける
その他検討すべきポイント
任意売却の流れがわかったところで、次は売却前後に行っておくと良いことをご紹介します。以下の3つのポイントを押さえて、不安を解消し、新生活の準備をスムーズに進めましょう!
1. マンションの場合は管理費等の清算
売却する物件がマンションの場合、管理費や修繕積立金の滞納があれば、事前に清算しておくのが理想的です。滞納金は買主に引き継がれる可能性があり、売却の条件となることもあります。
もし清算が難しい場合は、売却代金から清算することを前提に、金融機関と相談することも可能です。
2. 売却にかかる費用の確保
任意売却でも、不動産会社への仲介手数料や抵当権抹消登記費用、場合によっては測量費用や修理費用など、通常の売却と同様の費用がかかります。
これらの費用を売却代金から充てるかどうかは、金融機関との交渉次第です。事前に費用について確認し、必要であれば準備しておきましょう。
3. 売却後の引越し・生活の相談
任意売却の場合、金融機関に事情を説明し、交渉することで、売却代金から引越し費用や当面の生活費を捻出できるケースもあります。
しかし、必ずしも費用が確保できるとは限らないため、親戚や知人からの借入など、他の資金調達手段も検討しておきましょう。
住宅ローン滞納で困ったら…任意売却で解決!早めの相談が未来を変える!
住宅ローンの返済が滞ると、最悪の場合、自宅が競売にかけられてしまいます。競売では、売却価格や引渡し時期など、あなたの希望はほとんど反映されません。さらに、売却金額も低くなる傾向があり、売却後の生活資金を確保することも難しくなります。
私たちにお任せください!
当社は、任意売却や返済資金計画の調整など、多数の実績があります。任意売却不動産の一括買取も行い、スムーズな売却をサポートします。
住宅ローンでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家があなたの状況に合わせて、最適な解決策をご提案します。
一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。 あなたの未来を守るために、私たちが全力でサポートいたします。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)