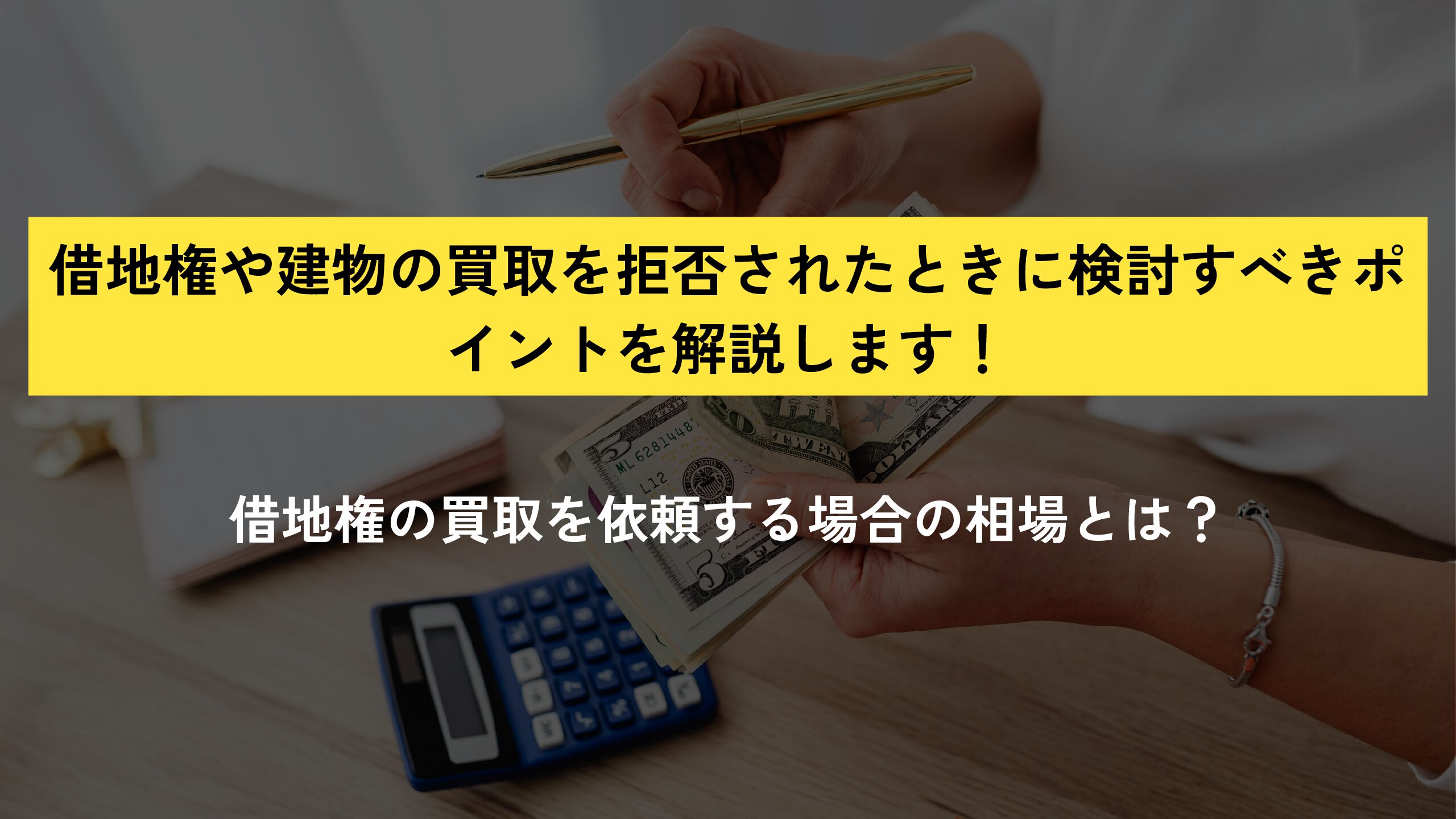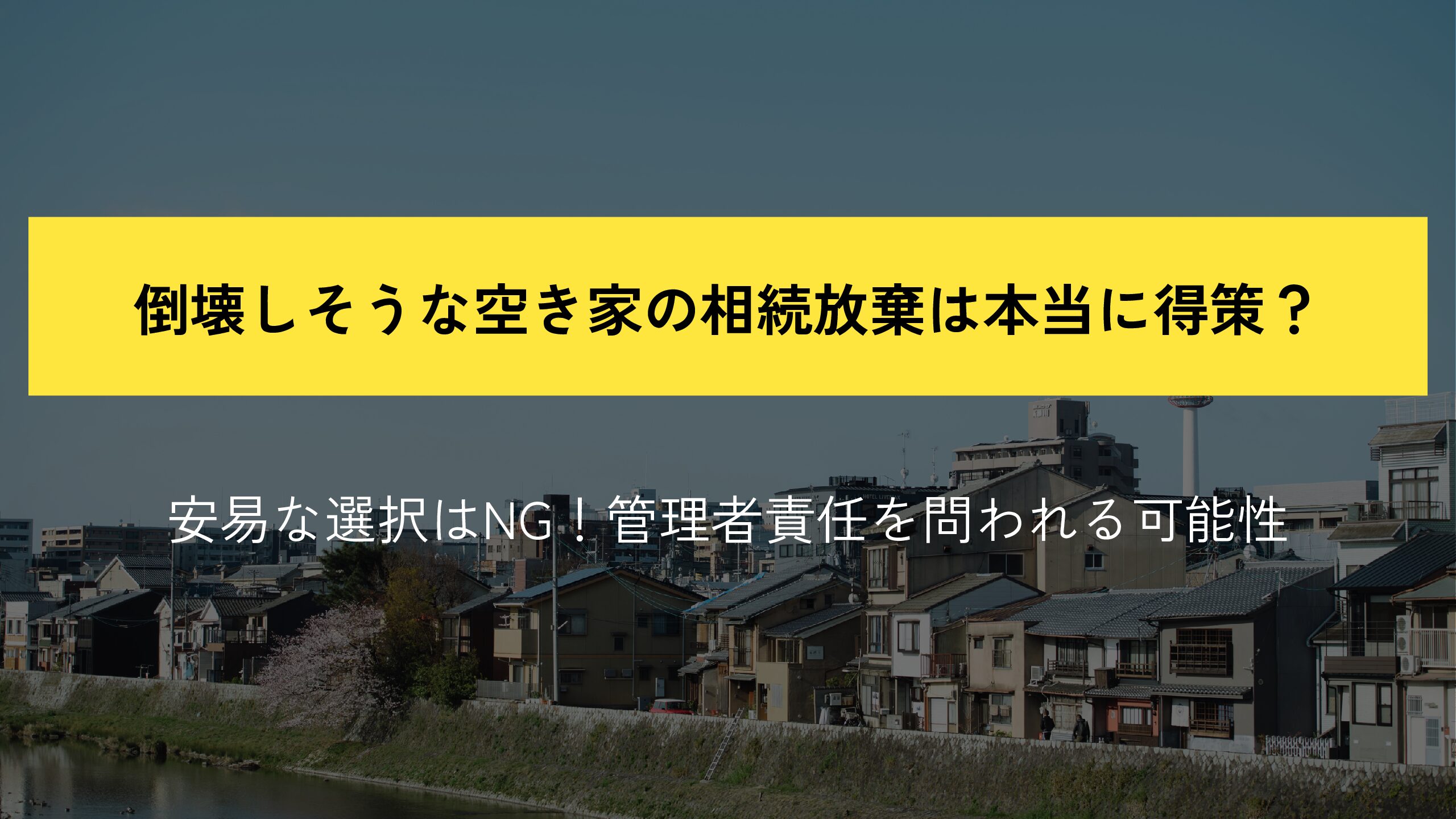借地権とは、土地所有者(地主)に権利金を支払うことで、その土地に建物を建てて利用できる権利のことを言います。しかし、借地権付きの建物を相続したり売却したりする場合、借地権の譲渡が必要となり、これが複雑な問題を引き起こすことがあります。
無許可で建物を売買すると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。借地権譲渡には、一般的に借地権価格の10%程度の承諾料が必要となりますが、地主が承諾しないケースも少なくありません。
そんな時に検討したいのが「借地非訟」という手続きです。本ブログでは、借地権譲渡の要件や借地非訟、地主の持つ「介入権」について詳しく解説し、トラブルを回避するための知識を提供します。
借地権とは?種類、特徴、契約更新、注意点
他人の土地を借りて建物を建てる権利、それが借地権です。土地を貸す「地主」に毎月「地代」を支払うことで、その土地を利用できます。借地権には、主に借地借家法と民法の2種類があります。
借地借家法に基づく借地権:建物を所有するための借地権
借地権の契約時期によって旧法借地権と新法借地権の2種類があります。
旧借地法(1992年8月1日以前)
- 借地人の権利が強い: 契約更新はほぼ自動、地主は不利な立場になりがちでした。
- 存続期間は建物の構造次第: 木造30年、鉄骨造・鉄筋コンクリート造60年と、建物の種類によって異なります。
- 契約期間は更新可能: 契約期間は定められていますが、更新することで半永久的に借りられます。
借地借家法(1992年8月1日以降)
- 契約更新には合意が必要: 更新には地主との合意が必要となり、借地人の権利は弱まりました。
- 存続期間は一律30年: 建物の種類に関わらず、存続期間は30年ですが、更新可能です。
- 新しい種類の借地権: 定期借地権など、新しい種類の借地権が導入されました。
借地借家法上の借地権の種類
新法の借地権はさらに4つの種類があります。これは土地利用にあたって活発な利用と有効活用を目的として設定されました。
- 普通借地権: 契約期限はあるが、更新すれば半永久的に借りられる
- 定期借地権: 一般定期借地権(住宅用)と事業用定期借地権があり、契約期間満了後は更地にして返還
- 建物譲渡特約付借地権: 契約終了時に地主が建物を買い取る特約付き
- 一時使用目的の借地権: 一時的に土地を借りる場合
民法上の借地権:建物所有を目的としない借地権
月極駐車場や資材置き場など、建物を建てない場合の土地の賃貸借です。
借地権の特徴
- 土地の所有権は地主: 土地を借りても、所有権は地主にあります。
- 地代を支払う: 土地利用の対価として、毎月地代を支払います。
- 制限事項: 地主の許可なく建物を売却・建て替えできません。契約期間満了後は更地にして返還する義務があります。
借地権の契約更新
- 旧借地法: 地主に正当な理由がない限り、自動更新されます。
- 借地借家法: 期間満了時に更新するか否か、双方で合意する必要があります。
借地権の譲渡・転貸は地主の承諾が必要
借地権の譲渡・転貸は、地主の承諾が必要な重要な手続きです。
借地権の譲渡とは
借地権の譲渡とは、地主の承諾を得て借地権者の地位を第三者に移転することを言います。借地上に建物が立っていることが借地権の成立要件であり、通常は借地上の建物の所有権の移転と合わせて借地権も譲渡がされます。
法的には建物の所有権の移転自体は地主の承諾なしに可能と解されています。つまり建物の売買と所有権移転登記が完了すれば、建物の所有権は移転し、第三者への対抗要件も具備できます。しかし、借地権の譲渡には地主の承諾が必須です。無断で譲渡すると、借地契約が解除される可能性があります。基本的に建物だけ譲渡して借地権の譲渡を行わない取引は想定されないため、建物の譲渡と合わせて借地権の譲渡を地主から承諾を受ける必要があります。
借地権の転貸(又貸し)とは
借地権の転貸、または借地権の又貸しとは、借地権者が地主との関係を維持したまま、第三者に土地を貸すことです。これは借地上の建物の所有権の移転を伴う場合に限定されます。つまり、借地上の建物の売買にあたって、借地権は移転せずに又貸しする場合が該当します。転貸、又貸なので、借地権者は売却先の第三者から、借地権の利用料を受け取ることとなります。このことにより、借地権の譲渡とほぼ同じ効果を得ることができます。
転貸も譲渡と同様に地主の承諾が必要であり、無断で行うと借地契約が解除される可能性があります。
転貸の範囲
転貸は、転借人から地代を受け取る場合だけでなく、使用貸借(無償で貸すこと)も含みます。また、建物の所有権全体を移転する場合だけでなく、元の借地権者との共有にする場合も転貸に該当します。
ただし、借地の転貸と認められるためには、借地上の建物の名義が転貸人の名義(共有の場合は共有名義)になる必要があります。
親族間での譲渡・転貸
親族間で建物の名義を共有にすることは珍しくありませんが、それが転貸であるという認識がなく、地主の承諾を得ていないケースがあります。裁判所の判断で最終的に借地契約の解除まで認められるケースはあまりありませんが、地主から土地明渡を求められる可能性もあります。
親族間の譲渡・転貸でも、事前に地主の承諾を得るか、承諾に代わる裁判手続きを行うことが重要です。
借地上の建物の賃貸の場合には承諾は不要
借地上の建物を第三者に貸す場合、借地権の譲渡・転貸には該当せず、原則として地主の承諾は不要です。建物の所有権が借地権者のままなので、借地権が第三者に移転することはありません。前章で述べた通り、建物の所有権が変わる場合に、借地権の譲渡か転貸という形で借地権者は地主に承諾を得る必要がありますし、原則として承諾料が必要となります。
賃貸の場合でも例外として確認が必要な場合がある
先ほどは建物を第三者に賃貸する場合には地主に許可を得る必要はないと説明しました。ただし、借地契約書に建物の種類や使用目的が記載されている場合は注意が必要です。例えば、「アパートとしての使用を禁じる」といった条項がある場合、アパートとしての賃貸はできませんが、一軒家を丸ごと貸すことは可能です。
前述の通り、使用目的が限定されている場合にあっては、原則としてその目的外の用途で建物を賃貸した場合には借地契約を解除されてしまう可能性もあります。借地契約書の内容によっては、第三者に建物を貸すために、地主の承諾を得るか、承諾に代わる裁判所の許可が必要になる場合があります。
その他、地主の承諾に注意すべきケース
その他下記のケースにおいては状況により地主の承諾が必要な場合もあるため、注意が必要です。地主の承諾が必要ないと見られるケースにおいても、必ず地主に報告をする必要があります。
相続による借地権の取得
相続人が借地権を相続する場合、原則として地主の承諾は不要です。相続が発生すると被相続人(死亡した方)の財産は一旦、共同相続人(死亡した方の親族など)の共有となります。これは建物に付随する借地権についても同様です。これらの共同物が遺産分割により相続人の誰かに引き継がれることとなりますが、これらについては譲渡とは解されないため、地主の承諾は不要とされています。
しかし、これは相続に限られ、遺贈や死因贈与の場合には原則として地主の承諾が必要となります。遺贈とは遺言により、相続人ではない第三者に遺産の全部または一部を譲ることをいいます。死因贈与は遺贈と似ていますが、自らの死亡を条件として発生する贈与契約を言います。ほとんど同じ意味ですが、遺贈と異なり双方の同意のもの発生する贈与契約である点などに違いがあります。いずれも借地権の譲渡については、地主の承諾が必要となります。
借地権の持分譲渡
借地の共有持分を第三者に譲渡する際には、地主の承諾が不可欠です。承諾なしに譲渡すると、借地契約が解除される可能性があります。
借地の共有とは、この借地権者の地位を複数人で共有している状態を指します。例えば相続により法定相続人で親所有の建物を分割で共有している場合などが考えられます。
無断で共有持分を譲渡された場合、地主は、その第三者を借地権者として認めない可能性があります。この場合、たとえ建物の登記が移転されても、土地の使用権は認められず、第三者は無権利者として扱われないこととなります。
この場合に注意したいことは、借地契約は他の共有者も含めた一つの契約であるため、解除する場合は契約全体を解除することになります。違反した共有持分者のみを対象に借地契約を解除することはできません。これをもう少し詳細に説明します。
借地の連帯責任
借地の場合は、全ての共有持分権者が一つの義務を負う「不可分債務」という概念が存在します。これは、例えるなら連帯責任のようなものです。そのため、一人の共有持分権者が無断で持分を譲渡すると、他の共有持分権者にも責任が生じます。他の共有持分権者が無関係であっても、契約解除によって借地権を失う可能性があるのです。
解除の可能性と対策
借地契約の解除は、必ずしも行われるわけではありません。過去の判例では、他の共有者の協力のもとで持分譲渡が行われたケースで解除が認められなかった例もあります。
しかし、共有持分が偏っている場合や、他の共有者が協力して譲渡が行われた場合など、状況によっては解除される可能性も十分に考えられます。
そのため、共有持分を第三者に譲渡する際には、事前に地主の承諾を得るか、裁判所の許可を得ることが重要です。
無断譲渡された場合の地主の権利
借地が共有でない場合、地主は建物の譲受人に対して、建物の取り壊しや土地の返還を要求できます。しかし、借地が共有されている場合、建物の取り壊し請求は複雑になります。
建物は借地権を持つ共有者と持たない第三者によって共有されている状態となり、地主は建物全体の取り壊しを請求できる可能性がありますが、裁判例は少なく、時間がかかる可能性もあります。
離婚による財産分与
離婚時の財産分与は、夫婦の財産を清算するために行われます。夫名義の財産であっても、実質的に夫婦共有財産とみなされる場合、妻に譲渡されることがあります。
借地権の財産分与と地主の承諾
夫婦が借地上の建物に住んでいて、借地権が夫名義の場合、離婚時に妻に財産分与する場合、原則として地主の承諾が必要です。
しかし、建物と借地が夫名義であっても、実質的に夫婦共有財産と認められるケースがあります。例えば、夫婦が同居し、建物の取得資金を夫婦で負担した場合などです。このような場合、借地権の譲渡は共有者間の譲渡とみなされ、地主の承諾なしでも解除されない可能性があります。
ただし、これはあくまで過去の判例に基づくものであり、必ずしも解除されないとは限りません。特に、収益物件や結婚前から夫が所有していた借地権の場合、実質共有財産と認められない可能性が高いため注意が必要です。
離婚時の財産分与で借地権を譲渡する場合、たとえ解除されない可能性があっても、トラブルを避けるため、事前に地主の承諾を得るか、裁判所の許可を得ることが重要です。
地主の許可が得られない時は借地非訟
借地権の譲渡や転貸には地主の承諾が不可欠ですが、承諾が得られない場合でも諦める必要はありません。「借地非訟」という裁判手続きを利用すれば、地主の承諾なしに借地権の譲渡・転貸が可能になる場合があります。
借地非訟とは?
借地非訟とは、地主の承諾を得られない場合に、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す手続きです。この許可があれば、地主が承諾したのと同じ効力が生じ、借地権の譲渡・転貸が可能となります。
借地非訟は、譲渡許可・転貸許可だけでなく、建て替え許可や借地契約の条件変更許可など、様々なケースに対応しています。
なお非訟とは、訴訟ではない、という意味です。訴訟ではないため、一般傍聴はできませんが、裁判と同様の手続きを行い、審問や書面のやり取りを通して裁判所が判決を下します。
借地非訟の申立てと手続き
借地非訟は、裁判所への申立書の提出から始まり、法廷での手続き、鑑定委員会による現地調査を経て、裁判所の決定に至ります。
申立書は裁判所のホームページからダウンロードできますが、複雑な内容のため、弁護士に依頼して作成することをおすすめします。
申立書が受理されると、法廷で地主側と対面し、裁判と同様の手続きが行われます。地主側が介入権を行使したり、借地権の存在や境界を争うケースもあり、専門的な知識が必要です。
法廷での手続きが終了すると、鑑定委員会が現地調査を行い、承諾料や介入権の金額を決定します。鑑定委員会の意見を参考に、裁判官が最終的な金額を決定します。
借地非訟の申立てに必要な3つの条件
裁判所に借地非訟を申し立てるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 譲渡・転貸前であること:建物の移転登記や引渡し前であれば、借地非訟を申し立てることができます。
- 譲渡・転貸相手が決まっていること:誰に譲渡・転貸するのかが明確でなければ、裁判所は判断できません。
- 借地上に建物が存在すること:借地上に建物がない場合、借地権だけの譲渡・転貸は認められません。
ただし、これらの条件は地主の承諾を得る場合は必ずしも適用されません。地主の承諾があれば、借地上に建物がなくても借地権を譲渡・転貸できます。
裁判所が借地権譲渡を許可する基準
裁判所は、借地権の譲渡が地主に不利益をもたらさないと判断した場合、承諾料の支払いを条件に譲渡を許可します。
譲受人の資力と承諾料
譲受人が地代を支払える能力があり、適切な承諾料が支払われる場合、許可が下りやすい傾向にあります。承諾料は、裁判所が選定した鑑定委員会の鑑定に基づいて決定され、一般的には借地権価格の10%程度とされています。
借地期限と建物の状態
借地期限が迫っている場合や、建物が著しく老朽化している場合は、地主に不利益が生じる可能性があるため、許可が下りない場合があります。これは地主側がその土地を使いたい要望がある場合で、申し込みが借地権の契約期間の満期に近く、現在の借地権者のままであれば更新拒絶が認められそうな場合などが該当します。
譲受人の借地の使用目的
譲渡後の建替え計画が、地主にとって不利益になる場合は、許可が下りない場合があります。特に、分譲マンションへの建替えは、借地非訟の段階で許可されない可能性が高いです。つまり譲渡先の第三者が分譲マンションのディベロッパーなどのケースでは許可されにくくなります。
借地の一部譲渡
借地の一部譲渡は認められますが、建物と一緒に譲渡する必要があります。借地の一部譲渡とは、例えば借地上に複数の建物があり、そのうちの一棟と一緒に借地を譲渡するような場合が該当します。このようなケースで、借地が分割されることで地主が著しい不利益を被る場合は、許可されません。地主にとっての著しい不利益とは、例えば土地の分割により建築基準法違反により再建築ができなくなったり、不整形地となることで不利益を被る場合などが該当します。地主の利益を保護する目的からこれらの一部譲渡で地主が被害を被るケースは許可されにくくなります。
借地権譲渡許可決定後の手続きと地主の不服申立て
裁判所が借地権の譲渡を許可する決定を下した場合、地主からの不服申立て(即時抗告)がなければ、14日で決定が確定します。
確定後の手続き
決定は通常、「確定後○日以内に承諾料を支払うことを条件に許可する」という内容です。指定された期間内に承諾料を支払えば、借地権の譲渡が可能となります。承諾料は、地代の振込口座などに送金すれば支払ったことになります。
借地権者と買主は、通常、地主の承諾を条件として売買契約を締結しています。決定確定後、承諾料を支払い、売買を実行し、建物の登記名義を買い主に移転します。借地権自体は登記されていないため、登記手続きは不要です。建物の登記が移転すれば、借地権も移転したものとみなされ、第三者に対抗できます。
地主の不服申立て(即時抗告)
地主は、許可決定に対して不服がある場合、決定から14日以内に即時抗告を行うことができます。即時抗告は、通常の裁判における控訴に似た手続きです。
即時抗告が行われると、高等裁判所が審理を行います。審理は、1からやり直すわけではなく、通常は借地権者側が反論書面を提出するなどの対応を行います。
高等裁判所が地裁の決定に問題がないと判断すれば、即時抗告棄却の決定を下し、許可決定が確定します。確定後は、最高裁判所に抗告しても決定が覆ることはありません。
借地非訟にかかる時間と早期解決の可能性
借地非訟は、申立てから決定まで平均8ヶ月かかるとされていますが、実際にはそれ以上かかることも珍しくありません。
時間のかかる理由
- 裁判所の鑑定: 裁判所が選任した鑑定委員会による鑑定が必要であり、この鑑定に基づいて承諾料が決定されます。鑑定には時間がかかるため、手続き全体の長期化につながります。
- 地主との交渉: 地主との交渉が難航する場合や、地主が借地権の存在や境界を争う場合は、さらに時間がかかる可能性があります。
早期解決の可能性:和解
例外的に早期解決が可能な場合もあります。例えば、申立て後の早い段階で、借地権者と地主が裁判所での和解によって合意に至るケースです。
和解は、譲渡自体には異論がないものの、承諾料の金額で折り合いがつかない場合などに有効です。裁判官が和解案を提示し、双方が納得すれば早期解決が可能です。
ただし、和解が成立するには、
- 借地権者側がある程度の譲歩をする
- 地主が早期に弁護士に依頼し、弁護士を信頼している
- 双方が感情的にならず、建設的な話し合いができる
といった条件が必要です。
注意点:買い主への説明
借地非訟は時間がかかる手続きであるため、買い主に対して事前に十分な説明を行い、理解と納得を得ることが重要です。手続きが長期化することで、買い主が契約を解除する可能性も考慮しなければなりません。
借地権購入における買主のリスク:売主の不協力
借地権と建物を購入する際、買主は売主(借地権者)の不協力や地主の介入権といったリスクに直面する可能性があります。
売主(借地権者)が積極的に動かない場合のリスク
通常、借地権の売買契約は、地主の承諾または裁判所の許可を条件とするものです。しかし、売買契約を結んだ後、売主が積極的に手続きを進めない場合があります。
通常の土地売買であれば、買主は代金を支払うことで、裁判所を通して土地の引渡しと所有権移転登記を強制的に求めることができます。しかし、借地権の場合は、建物の引渡しや移転登記はできても、地主の承諾がなければ借地契約が解除される可能性があります。この地主の承諾に代わる裁判所の許可申立は、借地権者しか行うことができません。買主は、売主の代わりに申立てたり、申立てを強制したりすることができません。買主が債権者代位権を行使して、売主である借地権者に代わって申し立てをすることが認められていません。
買主の対策
売買契約時に、借地権者が裁判所の許可申立てをしない場合に違約金を支払う条項を盛り込むことが有効です。これにより、売主の不協力に対する一定の抑止力となります。
借地非訟における地主の切り札「介入権」とは?
借地非訟とは、借地人が地主の承諾なしに借地権を譲渡・転貸しようとする際に利用できる裁判手続きです。しかし、地主側にも対抗手段が用意されています。それが「介入権」です。
介入権:地主の権利を守る仕組み
借地権の譲渡・転貸には、本来地主の承諾が必要です。しかし、借地非訟という制度により、地主が承諾しなくても裁判所の判断で譲渡・転貸が認められてしまう場合があります。
介入権は、このような状況から地主の権利を守るために設けられた仕組みです。借地人が借地非訟を申し立てた場合、地主は介入権を行使することで、借地権が信頼できない第三者に移転することを阻止できます。
なぜ介入権が必要なのか?
借地人が誰にでも自由に借地権を譲渡・転貸できてしまうと、地主にとって様々なリスクが生じます。例えば、
- 地代の滞納: 経済的に不安定な借地人が入居し、地代が滞納される可能性があります。
- 近隣トラブル: 問題行動を起こす借地人が入居し、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。
- 土地の利用価値低下: 建物が老朽化したり、不適切な用途で使用されることで、土地の価値が下がる可能性があります。
介入権は、このようなリスクから地主を守るための重要な権利と言えるでしょう。
介入権の行使方法
地主は、借地非訟の申立てがあった場合、裁判所が定める期間内に介入権を行使する旨を申し立てる必要があります。介入権を行使すると、地主は借地権と借地上の建物を買い取る権利を得ます。
介入権行使のメリット
- 第三者への借地権移転を阻止できる
地主にとって、信頼関係のない第三者に借地権が渡ることは大きなリスクです。介入権を行使すれば、このリスクを回避し、安心して土地を管理できます。
- 土地の所有権を完全に取り戻せる
借地権が存在すると、地主の土地利用は制限されます。介入権行使により借地権を買い取れば、地主は完全な所有権を取り戻し、土地を自由に利用・処分できるようになります。
介入権行使のデメリット
- 借地権の対価が高額になる可能性
裁判所が提示する借地権の対価は、市場価格よりも高くなる場合があります。これは、地主にとって想定外の経済的負担となる可能性があります。
- 借地非訟の手続きが煩雑
介入権を行使するには、借地非訟という裁判手続きを経る必要があります。複数回の裁判期日や書面での主張・立証など、時間と手間がかかることは避けられません。
介入権が認められないケース
借地権者と買受予定者が特殊な関係にある場合
例えば、同居する親子間での借地権を譲渡する場合などがあります。このようなケースにおいては、そもそも地主個人にとって信頼関係を破壊する可能性が低く、地主の権利を侵害する可能性も低いということで、地主の承諾がなくても借地契約が解除されない可能性があります。とはいえ、後々のトラブルを避ける目的で、裁判所に地主の承諾の許可を求める申立てをすることがありますが、その際に地主による介入権を認めてしまうと、借地人が非常にかわいそうだということで、地主の介入権が認められていません。
借地権の名義変更について無条件承諾特約が付されている場合
賃借人の都合により本件土地の賃借人の名義を変更する、または転貸する場合、地主が条件を付さないでこれを承認する、いわゆる無条件承諾特約が付されている場合などについても、地主の介入権が認められない場合があります。これらの条件が借地契約上定められていたにもかかわらず地主から譲渡について許可がなされなかった場合に、借地非訟の申し出があった場合に、地主の介入権を認めてしまうと、そもそも契約書に記載した事項が守られません。この場合にも地主の介入権が認められません。
跨がり(またがり)建物が借地上にある場合
跨がり建物とは、所有者の異なる2つの土地の上に1つの建物が建っている状態を指します。つまり、建物の所有者は同じであるにもかかわらず、土地の所有者が複数人いる場合です。
この場合、地主は借地上の建物部分だけでなく、越境している部分を含めた建物全体の買取を請求することはできません。これは自らが所有する土地以外の土地に存在する建物についてまで当該地主が介入する権利がないと考えらるためです。
また、借地上の建物部分のみの買取も、物理的に不可能な場合や、範囲や切断方法を特定することが難しい場合は認められません。
原則として、跨がり建物の場合は地主の介入権行使は認められませんが、介入権が認められないことで地主が著しく不利益を被る場合は、譲渡許可自体が認められない可能性もあります。
まとめ
借地権の譲渡には、原則として地主の承諾が必要となります。借地権は借地人の居住権を保護するための制度ですが、地主の権利も尊重されており、譲渡には両者の合意が不可欠です。
しかし、借地権の譲渡・売買や相続は、権利関係が複雑になりがちです。地主との交渉や手続きには専門的な知識が必要となり、個人で対応するのは困難なケースも少なくありません。
そこで、借地権に関するお悩みは、専門家である私たちにご相談ください。弁護士と連携し、借地権の買取・売買に関する豊富な実績を持つ弊社が、地主との交渉を含め、お客様を全面的にサポートいたします。
借地権の譲渡でお困りの際は、どうぞお気軽にご連絡ください。
簡単入力30秒
「他社で断られた」、
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。
訳あり物件の
スピード査定をしてみる
簡単フォームで30秒

.png)
.png)
.png)